 何がハッピーなんかよう考えたら若干の疑問が残るわけですが何だろうがイチャイチャしてくれればそれだけで私が幸せなのでハッピーハロウィンと世界の中心で叫びたい超絶短こばなし〜次時編〜
何がハッピーなんかよう考えたら若干の疑問が残るわけですが何だろうがイチャイチャしてくれればそれだけで私が幸せなのでハッピーハロウィンと世界の中心で叫びたい超絶短こばなし〜次時編〜2013.11.01 Fri 00:46
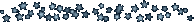
机の上にこんもりと盛られたお菓子の山。
似たような光景を確か今年の2月も見た、と三之助は思った。
「よーしろ」
「あっふぇんぱい、ふぉんにちあ」
もぐもぐと口を動かしつつ挨拶するその後輩の部屋に三之助は勝手知ったるなんとやらで上がりこむ。
「ハロウィンてアレだっけ?確か収穫祭的な意味もあんだっけか?」
「んぐ、、、あ、確かそうだったような」
「そーゆう意味じゃ大漁で喜ばしいな、これ」
「そうですねぇ、これだけいっぱい頂けて幸せです」
嬉しそうに笑う後輩は老若男女に好かれている。小動物を思わせる愛らしさは確かに、普段からやたら食べ物を与えたくなるもので。ましてやこんな行事ごとがあれば尚更。それを微笑ましいと思う一方でしかし、大いに面白くないとも思う。彼を喜ばせるのは自分だけであってほしい。そんな思いを三之助は常々抱いている。
「先輩も食べられますか?」
誰もが癒やしだと口にする笑顔で後輩が差し出したのは棒つきキャンディだった。既にその後輩の口には同種のキャンディがくわえられていた。その姿に普段あまり動かない三之助の表情筋がぴくり、と僅かに動いた。
「んー、じゃあもらおっかな」
そうして三之助が手を棒をとる――が、それは差し出されたものでなく、後輩が口にくわえたものであった。
「ぅえ、あ、せんぱっン、」
突如キャンディを取り上げられる形になった後輩は驚きに丸い瞳をもっと丸くさせた。そして次の瞬間には口を口で塞がれて後輩の瞳はますます丸くなった。
「ふっ、、、、んンっ」
三之助の舌が後輩の口内を思うままに動き回る。頬の内側を舐められ、歯列をなぞられ、上顎をつつかれ、ぬとり、と舌を絡められ、後輩は鼻から抜けるような声を漏らし、びくりと身体を震わせた。
「ごちそーさん」
れろ、と舌を出して三之助は言った。
「お礼に俺もお菓子あげる」
ぐちゃ、ちゅぷ、と、粘着質な水音が部屋に響く。限界近くまで膨れ上がった三之助自身が出入りする度に、そこからとろとろと液体が流れ出す。腰を振る度に柔らかく絡みつく粘膜がもたらす快感に三之助はたまらずはぁ、と息を吐いた。
「ッあぁ、ぁっ、ふぁっ、あンんっ」
がくがくと内側から揺さぶられる度に後輩の口から嬌声が漏れる。そのあまい声に三之助の欲もますます煽られる。
「しろ、甘い?」
「っそ、んなの、わかんっ、あっぁっ」
「でもすげーいっぱい垂れてるし、、、あーこれ全部溶けちゃったかなぁ。しろんなかあちぃから」
「っふぇ、、、っ」
「分かんないならもう一個入れる?飴ちゃん」
「やっ、だぁっ、、、せんぱいっ、もぅっ、」
イヤイヤと首を振る後輩に、三之助は滅多に見られないと誰もが言う笑顔で応えた。
「しろ甘いの大好きだもんな?」
だから遠慮するなと言うその確信犯な先輩に、後輩は本気勘弁して下さいと泣き声で言ったのであった。
「食べ物は、、、っ、あぁっん、粗末に、っしちゃ駄目、、、です、、、っ」
「粗末にしてないよしろが食ってんだから」
おわれよォ!
とりあえず謝るしかないゲスネタサーセン(^q^)
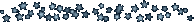
戻る
