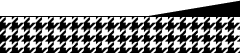千歳は笑顔の俺を不満げな表情で見つめた。この笑顔の意味は、千歳には分からないだろう。誰も知らない理屈で、俺は動く。
「千歳、送ってくれてありがとな」
無理にでも笑っていれば、それがいつか本物になる。俺はそう信じている。
だから最後に俺が笑えるように、あと少しだけ笑い続けるのだ。
そう、あと少し。
明日、俺は謙也に告白する。
家に入る前に何度も頬を擦って、涙の跡を消した。そして大きく息を吸い込んで、渾身の笑顔を作る。俺は負けない。選ぶことの重みに負けない。だから、この笑顔は負けないという強気の表明だ。俺は扉を開けて、大きな声でただいまと言った。赤い目を恥じる必要はない。戦っている俺を、誰も貶めることは出来ないはずだから。
決意を実行に移すには。
部屋で一人、思いを巡らせた。
明日、謙也をどうやって呼び出そうか?
脳内でシミュレーションを繰り返す。
こちらの選択肢よりはあちらの選択肢。
頭の中では何だって選べるし、何度だって選び直せる。行ったり戻ったりして、どんな可能性も考えることが出来る。
だけど、現実はそうじゃない。
一度選んでしまったものは決定事項で、選び間違えるという概念さえない。
選んだものだけが世界に残り、選ばれなかったものは消える。同じ選択は二度となく、同じ結果も二度とない。皆が選択によって作り上げる、一度きりの奇跡がこの世界だ。
だから俺は最高の結果を作れるように、全力で悩む。やり直せない現実のために、何度も想像をやり直す。
謙也の「好き」を聞くためには、どうしたらいいだろう。
自分の勝率を上げるやり方は?
受け手の気持ちに響くやり方は?
「夕飯を食べたら考えよう」はいつの間にか「風呂から上がって考えよう」になり、最終的には「寝るまでに考えよう」ということになった。
悩む夜は更けていく。
考えなど何もまとまっていないのに、振り返った時計は先程見たときより一時間も進んでいた。謙也のような短針だと思えば可笑しかったが、焦りも生まれた。
夜が更けすぎて、もう電話はしにくい。
可能性が一つ消えてしまった。
俺はそれならばメールでと考えたけれど、打てども打てどもまどろっこしい文章しか作れなかった。
携帯の四角い画面がブラックアウトする。
もうダメだ。
額に手を当てて、頭に浮かんだのは絶望の2文字だった。
学校新聞の連載ならあんなにもスラスラ書けるのに、好きな人を呼び出すたった一言の文章が書けないと言うのはどういうことだ。
ベッドの上に倒れこんで、目を瞑った。
時間はもう遅い。
送るなら、明日の朝一が勝負だ。
でも。
悩む頭に「手紙」の文字が浮かび上がった。
そうだ、手紙を書いて渡そう。
あんなにも必死に考えたのに、俺は簡単にそれまでのシミュレーションを放り出した。
この世界が奇跡なら、大きな力に流されるのが一番賢いやり方かもしれない。だから、天恵のように閃いたこのやり方を信じてみよう。
手紙はまた明日書けばいい。どうやって渡すかも、もう何もかも、明日、明日――
考え疲れた俺は、そのまま深い眠りに落ちていった。
次の日、目覚ましもセットせずに眠っていた俺は、友香里に叩き起こされるという屈辱的な朝を迎えた。
「クーちゃんが寝坊とか珍しいなあ」
「は?友香里?……って、朝!?今何時!?」
飛び起きていつもの倍速で忙しなく支度をする。一番気になるのは昨日泣きすぎた自分の目だったけれど、鏡に映せばいつもの目が覗き込んでいた。腫れずに済んだのはきっと昨日、赤目の切原クンが「常用している」と教えてくれたよく効く目薬を差したおかげだろう。
飛び出した外は、気持ちの良い朝だった。
冷たい空気の中を走る。いきなり全力で走ったから、すぐに脇腹が痛くなった。それでも走る。今日と決めた日に、寝坊だけでなく遅刻までするのは気が重い。走り続けたら、先に家を出た友香里の後ろ姿が見えてきて、俺はやっと走るのをやめた。
なんとか遅刻は免れて、教室に入る。
自分の席でクラスメイトと話している謙也の姿をチラリと確認した。
良かった。欠席していない。
謙也も俺に気付いて、席に着いたまま「白石、おはよう」と声をかけてくれた。謙也と俺の席はそこそこ離れているから、かなり声を張り上げている状態だ。クラスの奴が数人、謙也と俺を見た。
「今日遅かったやん」
「ちょっと寝坊してん」
「白石が?珍しいなあ」
「目覚ましかけ忘れた」
「更に珍しいやん」
俺たちが話していると、担任が教室に入ってきた。そのまま朝のHRが始まって、俺たちの会話もそこで打ち切られた。
俺が珍しく寝坊したのは、謙也、おまえのこと考えとったせいなんやで。
変な消しゴムを眺めている謙也の背中に、気持ちをぶつけた。
こんな気持ちも、もう頭の中で考えるだけじゃない。こんな言葉も、もう聞こえないように呟くだけじゃない。
今日、このすべてが現実世界に現れる。
俺は紙を一枚取り出して、授業中のノートの上に重ねた。俺の選んだ結果が、ちゃんと謙也に伝わりますように。願いを込めて、紙の上にペンを走らせた。
完成形だと思うものは、やはり今日も書けなかった。一通の手紙に数時間を費やし、書き直しにいくつもの授業を潰していた。
本題は呼び出した後なのだ。だから、こんなところで躓いている場合じゃない。
大して代わり映えのない文章をいつまでもグズグズと書き続けている自分を叱咤して、とにかくシンプルで一切無駄のない手紙を書いた。
「放課後、屋上に来て」
下に小さく「白石」と書いて、俺はその小さな、そして大きな運命を背負う紙を折った。
あとは、これをいつ渡すかだ。
手渡すのも気まずいが、誰かに頼むほどでもない。しかしそれについては悩む間もなく良い機会があったので適当に解決してしまった。
休み時間、謙也が席を立っている間に、俺は謙也のペンケースの下にその紙を挟んでおいた。
次の授業が始まって、謙也がその紙を広げたところまで確認して俺は目を瞑った。
やるべきことはやった。
あとは放課後だ。
目を開けたら視界の隅に、パッと顔を背ける謙也が映った。
俺は謙也を選びたい。
謙也には、俺に選ばれる覚悟があるだろうか。
屋上に来てくれるだろうか。
不安だったけれど、今は信じるしかなかった。
自分の好きになった人さえ信じられなければ、この世の何も信じられない。
信じることは責任を持つことだと、ふと思う。
これから俺は謙也にフラれるかもしれない。
いつか財前と付き合うかもしれないし、ずっと誰とも付き合わないかもしれない。
どんな未来になるかは分からない。
でも、いつか立ち止まって、ふと過去を振り返る。
「俺はこれで良かったのだろうか?」と思うとき、自信を持って「良かったのだ」と俺は言いたい。
自分の今を肯定し信じることが、選択に責任を持つということだ。
自分は不幸だと思うときも、言い訳をしてはいけない。
残酷でも、自分の選んだ結果が今の自分だ。
自分が不幸なのは誰のせいでもない。
選択を誰かに強制されたから?
誰かに与えられた選択肢だったから?
不幸な理由を誰かに押し付けても、結局自分の不幸までは押し付けられない。
どちらを選んでも地獄のような理不尽な選択を迫られたとしても、言い訳だけは絶対に出来ないのだ。
最後に選ぶのはいつだって自分。
選びたくないのなら、選ばないことを選択すればいい。
選択肢に納得出来ないのなら、納得出来る選択肢を探し出せばいい。
選択は自分が確かに生きた証だから、誰の責任にも出来ない。
過去は変えられない。
どんなときだって選べるのは今だけだ。
いつの間にか今日の最終授業になっていた。
授業中、時々謙也からの視線を感じたが、俺は気付かないフリをした。目を合わせたら謙也がどんな顔をするか、それも少し気になったけれど、俺は姿勢を正して前だけを向いていた。
あと、5分。
時計の針が今はゆっくりと進んでいた。
終わりのチャイムは始まりの鐘だ。
誰の「好き」が結果になるのか。
戦おう、謙也。
「起立、礼!」
「「ありがとうございました」」
俺は極力謙也を見ないように、平常通りに下校の支度をした。教室を後にするとき、やはり席に謙也の姿はなく、俺は視えない屋上を想う。
もう待っているだろうか?
長い廊下を歩いた。
放課後の活気が校舎を包んで、とても賑やかだ。
その中を俺は一人、静かに進む。
階段を上る。
一歩、また一歩、屋上に近付く。
今から、俺と謙也は選択する。
それは終わりではなく、一つの区切りに過ぎないけれど、終わるものもあるかもしれない。
この選択の場に財前のいないことをふと残念に思ったが、俺は小さく首を振った。
呼吸を落ち着けて、重い扉を押し開ける。
青い空が目に飛び込んできた。
手を離した扉が閉まっても、俺は謙也の姿を見つけられなかった。
謙也は俺より早く教室を出たはずだが、どういうことだろう。
俺は左右を見渡し、それからさして広くない屋上をグルリと一周歩いてみた。しかし謙也の姿は見当たらない。
もしかして帰ってしまったのだろうか?
嫌な予感がふと脳裡を掠めたが、俺は信じた。
謙也ならきっと来る。
謙也は選ぶことを怖がらない。
忍足謙也という人間を知っているからそう思ったのではない。
それはただ、自分の好きな人はそうであるはずという決め付けに過ぎなかった。
待つしかない。
覚悟を決めて俺はフェンスに凭れ掛かった。
それからどれくらい経ったのか。何度目かの「暇やな」を呟いて、一応は告白前だと言うのに昼寝してしまいそうなくらいリラックスして座っていた。
すると突然、ゴウン!という乱暴な音がして屋上の扉が全開になった。
現れたのは間違いなく俺が待ち望んでいた人物で、俺は立ち上がって姿勢を正す。
「……スマン、待たせて」
謙也は一体何をしていたのか、走ってきたように息を切らして俺の前に立った。
「ど、どないしたん?大丈夫?」
謙也は膝に手を突いて、ゼェハァと荒い息をついていた。俺に掌を見せるそのジェスチャーは、「大丈夫、気にせんでええ」の意だろうか。息を整え終わったのか、謙也がパッと顔を上げた。
謙也の異様な雰囲気に、告白のムードが出ない。
でも呼んだからには言ってしまわなければいけない。どうせ謙也にもこの呼び出しの意味は伝わっているのだろう。
ここまで来て怖気づくわけにはいかなかった。
「謙也、」
サッと風が吹いたから、今がチャンスだと思った。
「俺、謙也のことが好きや」
【Last Question】
→謙也ルート
→財前ルート
CHOOSEΔ TOP