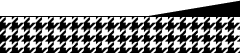次の瞬間に、その気持ちを否定した。
恋が移ろう気配に、誰より一番自分が焦っていた。
目の前にいる人を見て大きく鳴る心臓が信じられなくて、千歳のそばを急いで離れた。
挨拶もしないまま逃げ帰る俺を千歳はどう思っただろう。
家に着いても心臓は黙らなかった。爆発したように噴き出した新たな「好き」を、俺は反射的に押し殺そうとした。けれど押さえても押さえても蓋は浮き上がって、「好き」は溢れ出て、もはや隠すことも無かったことにすることも出来ないのは明白だった。
眠ってしまえば、明日の朝には。
最後の儚い望みに賭けて、俺は目を瞑った。
優しくされて、ふらついただけだ。きっと明日の朝には元通りになっている。
三角関係の中で摩耗していた「好き」という気持ちを、「好きな人」である謙也以外の人間に感じた。
本当はそのことに後ろめたい気持ちを感じる必要などないのかもしれない。
しかし俺はまだ往生際悪く、謙也を好きなのだと自分に言い聞かす。しがみつくように念じることにどんな意味があるのだろう。だが、それが義理だと思う。こんな終わりを誰も許すはずがない。誰が何を裁くというのか、そんなことはくだらないしがらみだと思うのに、俺はそれに囚われたがった。
ふいに瞼の裏に千歳の暗い瞳が浮かんできて、見つめあった。温かい、と感じたら吸い込まれるように眠りに誘われた。
朝、目が覚めたら何もかもを忘れていた。
いつも通り起きて伸びをして、カーテンを開け朝日を浴びる。
そこまでして、やっと俺は最後の賭けに負けたことを悟った。
俺が想ったのは千歳のことだった。
謙也じゃない。
今心にあるのは、千歳の藍色の瞳のことだけだった。
しかし俺はそれでもまだ千歳を好きになってはいけないと信じている。心変わりなんてしてはいけないのだ。俺は千歳を好きになってなんていない。昨日優しくされて嬉しかったのを、心が勘違いしているだけなのだろう。大丈夫。こんな感情、すぐ忘れる。だって謙也のことはずっと前から好きだったのだから。昨日好きだと感じただけの千歳では俺の気持ちは塗り替えられない。大丈夫、俺はまだ謙也のことが好きだ。
俺は真実から目を背け、遠くなる過去を追いかけた。
いつも通り登校し、普段通りの授業を受ける。しかし前の方の席に座る謙也を見ても、心が躍るような気持ちは湧いてこなかった。精彩を欠いたように、恋の楽しさは失われていた。それでも俺は謙也の背中に縋りつくような視線を送り続けた。
その日から、俺は自分の視線の先がすり変わっている事実に度々気付かされた。
謙也を追っていたはずの視線が、いつの間にか千歳を追う視線になっている。
気が付くたび謙也に視線を戻すのだけれど、それでもふと気が付けば、また千歳の姿を探している。どれだけ意識で押さえ込もうとしても、無自覚の力の方が大きかった。そんなことを何度も繰り返して、やっと俺は心が求める答えを認めた。
あの日と同じ中庭に、俺は千歳の姿を見つける。広い背中にゆっくりと近付いていけば、胸が甘くときめいた。謙也にはもう、こんな風に胸は鳴らない。それがとても寂しい気がして、でもこちらに気付いた千歳が俺を見て笑ってくれたらそんな感情さえ消えてなくなる。
「白石か。こげなとこに何の用ね?」
俺は千歳の横に腰を下ろして、「千歳と話がしたかってん」と呟いた。
「俺に話?」
「……諦めようかと思う」
何を、とは口にしなかったが、それだけで千歳は察してくれた。
「そう。……身を引けることも強さばい」
本当の俺は謙也や財前の為を思って身を引いたわけではない。だから、千歳からそんな風に言われると自分を偽っているようで心苦しかった。
俺はそない慈善的な人間やないんや。
そう言ってすぐ否定しなかったのは、千歳のフォローを無駄にしたくなかったからだろうか。それとも、偽りでも優しい自分を千歳に見せていたかったからだろうか。
俺が黙っているのを、胸を痛めているからだと思ったのか、千歳は重ねて俺を慰めた。
「……無理はしなすな。
そのうち時が解決してくれる。俺がそうだったように。徐々に忘れていけばよか」
千歳に優しい言葉を掛けられるほど、心苦しさが募った。耐えきれず、「ちゃうねん」と溢す。
「……何が?」
言ったら幻滅されるのではないか。
そう思うのに、俺の口は本音を告げる。
「俺、他の人好きになってしもたんや」
俺は本当の俺を許されたかった。
身を引くなんていう偽善で俺は三角関係を捨てたんじゃない。二人の幸せは確かに願っていたけれど、それで戦うことをやめてしまうほど俺は優しくなんかない。綺麗事は向いていない。俺はいつだって自分の幸せのために生きていて、他人の幸せのために生きているわけではない。それを自分勝手と呼ばれるなら、それで良かった。
無節操な奴と思われただろうか。
横顔にそっと視線を向ければ、千歳はぼんやりした表情で口を開いた。
「それもええんじゃなか?本気なら」
「千歳」
呼びたかった名前を口走る。
ああ、抑えていた蓋が消えた。
心が開いて、本音が口を衝く。
「……千歳のこと、好きになった」
俺の一言に千歳は固まって、「本気?」と問うた。
「本気かは、まだ分からん」
流れ出すのは嘘偽りのない、等身大の俺の言葉。
「それに、こんな風に三角関係を崩してええんかも分からん。
財前にも謙也にも、申し訳ない気がする」
口に出せば、気持ちが少しクリアになって見えた。
気になるのは、それだけ三角関係に心を囚われているからだ。千歳のことを好きになっても、あの正三角のことがまだ他人事にならず、俺の心に残り続けている。
こんなにも迷いのある状態で、自分の気持ちをぶつけてしまって良かったのだろうか。
千歳はグズグズしている俺に呆れているかもしれない。
千歳の顔を窺えば、彼は先程と何も変わらない表情のままでいた。
「白石。気持ちは嬉しいけど、一旦俺のことは忘れてほしいったい」
千歳が俺の方を向いて、そう言った。
「今はあん二人のことだけ考えて。
俺は待つけん。
けじめばつけたいなら告白してもいいし、せんのも白石ん自由ばい。
白石ん中で三角がキッパリ過去に変わるまで、俺は待っとくけん。
卒業までに謙也のことも財前のことも忘れられたら、俺と付き合おう」
この場合、俺と千歳のどちらが告白したことになるのだろう。
千歳の言葉は俺の胸を震わせて、よろこびで満たしてくれた。俺たちは両想いの確認をしあって、それでもまだ想いを遂げられない。
まだ、俺には片付けなければならない気持ちが残っている。
長い間、俺は三角形の一端だった。
輝かしい思い出を忘れ去るには、そこで過ごした時間以上の長い時間がかかるのだろう。
最後に謙也への気持ちにしがみついたのは、きっと最高の夏の記憶まで恋と一緒に失いたくなかったからだ。
煌めく太陽の下で、俺は財前の軽口に怒って、謙也は俺の隣で笑っていて。
そんなワンシーンを大切に収めていたアルバムを開く。二度とない夏が写るアルバムを見つめて、冬から春に変わる季節の中、俺は一人黙々と作業をした。
「正三角形」のページに貼り付けていた写真を、「チームメイト」のページに貼り替える。無かったことにするわけじゃない。完全に忘れるのともまた違う。俺なりに考えた、気持ちの整理の仕方だった。
財前に付けた名札を外す。
俺を好きになってくれてありがとう。
謙也に付けた名札を外す。
好きだったこと、ずっと忘れない。
俺に向けられた矢印も、俺が向けていた矢印もそっと優しく畳んで、俺は三角形の一端であることを終えた。
俺の手の上にたくさん載っていた宝物。
投げ捨てることは出来なかった。
だけど俺は新しい宝物を見つけた。
それを手にするためには、今ある宝物を手放さなければならない。
俺は悩んだ。
新しい宝物を掴むと決めてからも、俺はなかなか掌をひっくり返せなかった。
だから俺は、右手と左手の隙間から砂を溢すように、時間をかけて宝物を落としていった。
俺の掌から零れ落ちた恋という宝物は、滑り落ちながら記憶に変わって、俺のアルバムを埋めていく。
そして俺は今、空っぽになった掌で、新しい宝物を掬い上げようとする。
「……随分と待たせてしもたな」
あなたがゆっくりと笑う。
「……待っとったよ」
俺も微笑みを返す。
「千歳、俺と付き合ってください」
何もない掌を差し出せば、あなたの手が優しく俺の手に重ねられた。
「もちろん」
もう冬も終わる暖かい日の午後だった。
千歳の温かい掌が、俺の新しい宝物になった。落とさないよう握り締めれば、「痛いっちゃ」と千歳は小さく声を上げた。
宝物は変わってしまったけれど、他は何も変わらないまま、俺は学生生活を続けている。
今は謙也を見ても仲のいい友達にしか思えないし、財前のことは相変わらず生意気で苦手だけれど、それもまあ許したいと思っている。
財前と謙也は俺の影を追って、まだ俺の抜けた正三角形を保っているみたいだけれど、それもじきに崩れるだろう。
今、俺の隣には千歳がいて、残り僅かになった中学生活を一緒に楽しんでいる。
卒業まであと少しなのだから休むなと言っているのに、それでもサボる千歳と喧嘩することも楽しくて仕方ない。
そんな些細な幸せを感じるたび、俺の掌の上の宝物は増えていく。
戦わなかった狡い俺を認めてくれた。
強いあなただから、人の弱さを許すことが出来る。
そう思うから、俺は千歳が誇らしかった。
千歳を好きになって良かったと思うとき、俺は俺の選択まで誇らしかった。
CHOOSEΔ TOP