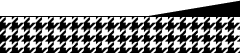帰宅してからも、赤い目を見られないよう閉じ籠った自分の部屋で、俺は何度も千歳の顔を思い浮かべていた。好きだと感じた気持ちをがむしゃらに追いかける。そうだ、あんな奴やめよう。謙也なんて嫌いだ。財前のことを好きな謙也は嫌いだ。俺の気持ちに気付かないあのアホなんか嫌いだ。それに比べて、千歳は優しい。俺はもう謙也のことなど嫌いになった。千歳のことを好きになったんだ。繰り返し繰り返しそう頭に叩き込みながら、俺は眠りに落ちていった。
翌朝、起きて鏡を見る。昨日あれだけ泣いたのに、俺の目は平常と変わらなかった。鏡に近付けば、目の際がいつもより赤い気もしたが、自分でも考えて分かるほどだから誰にも気付かれないだろう。
いつも通りの朝を過ごして、いつもの通学路を歩く。世界を呪おうと思ったあの帰り道のことは、もう思い返されない。俺はただ千歳が学校に来ているか、それだけを考えながら足早に学校へと急いだ。
しかし、その日千歳は欠席だった。
背の高い後ろ姿を廊下で見かけることも、昼休みに中庭の木の下に見かけることもなかった。
もしかして、昨日俺と長い間外で話し込んでいたから風邪を引いたのだろうか。想像するとどうにもそれが正解のように思えて落ち着かない。帰りに千歳の家へ寄ってみようか。そんなことを考えていれば、一日は飛ぶように過ぎた。
終業の号令がかかり、立ち上がってふと中庭に目を向けたその時、俺は藍色の頭を見つけた。
……千歳だ。
鞄も持たず、俺はとにかく駆け出した。
会いたい。
廊下は走るな!という警告ポスターも目に入らないスピードで俺は走る。階段前で滑るように方向転換すると、キュッと上履きが甲高い音で鳴った。早くしなければ千歳が行ってしまう。落ちるように階段を駆け下りると、俺はまた廊下をフルスピードで突っ切って、上履きのまま中庭に降り立った。
「千歳!」
自分で出したのかと疑うほど、馬鹿でかい声で叫んだ。
「千歳、おらんの!?」
俺は何故こんなにも取り乱しているのだろう。また昨日のように泣いてしまいそうだと思ったとき、木の影から千歳が姿を現した。
「なんね、白石。そぎゃん大声ば出してから」
千歳は呆れ笑いのようなものを浮かべ、ゆっくりと俺の方に近付いてきた。
「白石、靴ばどぎゃんしたと?」
俺の上履きを見て、千歳は首を傾げている。そうじゃない、今大事なのはそんなことじゃない。
「千歳、俺、
……千歳のこと好きになってしもた」
言ってしまってから、また驚いた。
千歳を見つけて反射的に追い掛けてきたけれど、走っている途中は千歳を捕まえることばかりで何を言うかなんて考えていなかったのに。
それがここに来て、千歳の前に立った瞬間、思い出したように口から滑り出た。
昨日の今日で、こんなことを言うべきではないはずだ。しかし、言ってしまった。もう何を考えても無駄だ。言ってしまったものは二度と口の中に戻せない。それなら、次に何を言うか考えよう。
千歳は俺の目をじっと見つめてきた。千歳の瞳には俺の本心を読んでいるような厳かさがあって、俺は思わず背筋を伸ばす。
「白石、」
千歳は問いかけた。
「……これでよかと?」
千歳の問いは俺の心に響かなかった。
どういうことだろう。俺は寝て起きて、確かに謙也を忘れていた。千歳を好きな気持ちが残った。それが答えだ。だから、これでいいに決まっている。
「白石、よう聞きなっせ。
今、白石が辛いんはよう分かったい。ばってん、その辛さは逃げても解決にはならん。それなのに白石はこれでいいんね?」
俺はまだ逃げているのだろうか。そんなはずはない。こんなにもキッパリと選んでいる。
「昨日まであぎゃん悩んで泣いとったんよ。一瞬で諦められる恋じゃなかはずよ」
俺はだんだんと千歳のことが分からなくなってきた。千歳は俺が嫌いで、だから好きになるなと言いたいのだろうか。
「今一瞬の気持ちで俺んこつ選んでいいんね?後悔せん?」
「一瞬」や「後悔」という言葉が選ばれる理由が分からない。俺は無意識にそれらの言葉をブロックしているのだろうか?千歳の口から飛び出た言葉は俺の表面を滑り落ちて、何も感じられない。
「白石は、まだ無理しとるごたる。『選びたい』って気持ちがいつの間にか義務になって、『選ばなきゃ』になっとうとじゃなか?」
強く見据えられて、俺は何も言えなかった。千歳の言うことには即座に反発を覚えたけれど、その実、千歳が言ったことはすべてその通りのような気がした。
「そぎゃん気持ちで選ばれても、俺は困る。それに、いつか白石も困ることんなるとよ」
優しく諭されて、だんだんと落ち着いてきた。千歳の言っている意味も、やっと頭に入ってき始める。
「昨日、白石は疲れとった。俺の接し方も悪かったかもしれんばい」
俺は楽をしようとしているのか?
選びたい気持ちが暴走して、手近に落ちていた簡単な答えを拾った。選んだつもりになって、よく考慮せずその答えを信じようとしている。
千歳には、そう見えている。千歳に見えているものは正しいのかもしれない。でも、俺が千歳を好きだと思ったのは本当だ。それだけは譲れない。
「千歳の言いたいことは分かった。せやけど、俺はホンマに千歳のこと好きになったんや」
「白石は何も分かってなか!俺はそん『好き』が怪しいっち言いよんよ」
語気を強めて言い返されて、身を竦めた。俺の好きが怪しい?どういうことだ?
「誰か他ん人を好きになってそれで辛いのを終わりにしようって、そぎゃん決め方で俺を選んだごたる。そいが好かん!」
「はあ?誰か他の人を好きになることもあるやろ。それがアカンの?
千歳、俺のこと嫌いならハッキリそう言いや!」
「違う、全然違う!」
珍しく大声を出して、千歳が打ち切った。
何が違うんや、と俺が零した言葉を千歳は丁寧に拾ってくれる。
「俺は逃げ道としての選択肢にはなりたくなか。白石が俺んこつ好いとる言うなら、ちゃんと俺んこつ考えて、選んで。ちゃんと俺に傷付けられる覚悟もしてから選んでほしか」
一転して穏やかな声で、千歳は言った。
俺はもう完全に冷静だ。千歳の言葉の意味もすんなりと理解出来る。
千歳の言うとおり、俺は逃げていただけだ。
昨日千歳の優しさに触れて、好きになれると思った。千歳なら許してくれると思った。可哀想な俺に優しくしてくれると思った。
だけど、それは好きとは言わない。利用だ。
好きなら、謙也や財前と同じように、千歳との恋愛の中で傷付く覚悟が必要だった。俺はなんとなく千歳ならすべて許してくれると思い、その優しさに甘えたかっただけなのだろう。
千歳は俺よりも俺をよく知っていて、俺が自分では気付かない気持ちまであっさりと見つけてしまう。隠し事も嘘も簡単に暴くし、俺の無理にだって、俺以上に敏感だ。
「それから、俺が白石んこつ嫌いっち言ったら、次は誰を逃げ道にするつもり?誰んことを好きになろうと頑張っても、白石ん心はたぶん、謙也に囚われ続けると思うたい」
そう言われて謙也の表情を思い浮かべた。好きかと問われれば、今でも好きと答える。けれどそれはもう心の明るくなるような恋ではなくて、執着や競争心の成れの果てだった。
「な、白石。好いとるっち言ってくれたんは嬉しか。ばってん、そいは気の迷いかもしれんばい。そうだったらお互い辛かけん、しっかり考えてからにしてほしか」
説き伏せて、千歳は俺の頭を撫でた。
その優しい手付きが好き。
そう思うのにそれを伝えることはもう許されないようで、俺は黙って俯いた。
あれから二週間。
いくらか時間が経って、盛り上がっていた気持ちは冷めた。この二週間、自分を冷静に見つめようと試み続けてきた。
俺は確かにあのとき、危うかった。
昨日まで好きだった人を一日で嫌いになれるわけなんてなかったのだ。好きな人の嫌いなところを無理矢理探していた。嫌いだと信じこむことを頑張るという、奇妙な努力をした。わざと嫌いになることなど不可能だったのに、俺はそれが出来ると思っていた。三角関係が辛かったから、謙也を好きなのをやめてしまいたかった。謙也のことを嫌いになれば、三角関係も終えられると思っていた。
だけど千歳はそんな俺の気持ちに気付いて、ちゃんと叱ってくれた。
自然の流れに身を任せたような生き方の中に、一本きちんと筋の通っている千歳だから言えた言葉だと思う。
俺は二週間、自分を見つめ続けた。
一番大切なのは「選ぶこと」じゃない。一番大切なのは「何を選ぶか」だ。
そのことに気付けたから、もう不自然に気持ちを捩じ曲げるような真似はしなかった。
自然な自分の気持ちを探そう。
そう心に決めて、ざわざわと波立つ心の表面を見つめていた。興奮が収まって、普段通りの生活がやってきた。泣くこともなく、澄んだ目も取り戻した。
揺れなくなった水面を見つめて、そこに映ったのは――。
「千歳」
千歳の後ろ姿を見つけたから、走って追い付いた。振り返る千歳、視線を合わせたのはあの日の中庭以来だ。
「……千歳、あの時はスマンかった」
千歳に見つめられても、俺の心は怯えなかった。ただ水面は沈黙している。
「悪いことしたなって思って、ずっと謝りたかった」
二週間、千歳は俺の前に姿を現さなかった。俺も無理に探すことはしなかった。
「ホンマ、ごめんな。でもあのとき千歳がちゃんと叱ってくれて良かった。感謝しとる」
千歳の深い色の目を見つめる。吸い込まれるように見つめる自分を客観的に見つけたら、心が少し波打った。
「俺、あれから二週間、自分の気持ちをじっと見つめとってん」
故意に考え、答えを出そうと足掻くのはやめた。ただ、答えが浮上してくるのを静かに待っていた。平静を取り戻した俺の心に、ぷかりと浮かんできた答え。
「俺、やっぱり千歳のこと好きになったみたい」
受け入れてもらえるだろうか。
自然体の俺が見つけた答え。
見つめあったかと思えば、千歳の目は柔らかく細められた。
「……そいだったらよかと思っとったたい」
千歳が笑っている。
言われた言葉を消化するのに時間がかかり、理解すればジワジワと身体中に嬉しさが広がった。
「え、ホンマに?」
「自分で断ったのに、こん二週間、ずっと白石んこつば気になっとったと」
タイムラグが埋まり始める。千歳の言葉が嬉しくて、鼻の奥がツンとした。
「白石の泣き顔ば思い出すたび苦しかったけん、顔合わせられんと思って学校サボっとった。
……でも流石に二週間はやり過ぎたったい。今センセに呼び出されて怒られてきたとこよ」
千歳が笑う。俺も笑う。
そのあと、「好き」と呟いたのが同時だったから、俺たちは顔を見合わせて照れあった。
もう一度言い直す「好き」のタイミングまでまた同じになって小さく噴き出せば、どちらからともなく声を上げて笑いあう。
「……中3の冬に二週間も休む奴がおるか」
「えー。白石のせいなのに」
「分かっとる!せやから、責任持って二週間分の勉強教えたる」
「とか言うとるけど、俺と一緒におりたいだけたいね?」
「……調子乗っとるとスパルタやぞ」
「ひえー。さっきまではほんなこつむぞらしかったんに!」
今、彼らは俺をどう思っているだろう。
三角形から飛び出して、勝手に幸せになってしまった俺を。
願わくばいつか許してほしいと思う。虫が良すぎるかもしれないけれど、いつか祝ってほしいと思う。
三角関係の中で確かに俺たちはライバルだった。
しかしそれでも俺たちは、綺麗な正三角を一緒に画いた、最高の仲間だったと思うから。
CHOOSEΔ TOP