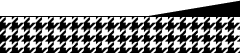汗が光る。確かに、少しスタミナが落ちているかもしれない。
向かいに立つ金ちゃんが見せてくれるのは自分自身だった。いつでも自分と戦うのは、自分自身。白熱していく試合、熱の上がる身体と反対に頭はどんどん冷えていった。冷静になれ。俺が勝てるのは、俺のテニスを極められた時だけだ。一切の無駄のない、聖書テニス。俺は俺のやり方で、この試合を制する。
金ちゃんの爆発的な一球も、テニスの球には変わりない。俺は基本に忠実にその球を拾い、コーナーを狙った。それが最後の一点となって、勝敗は決した。久々に、俺の勝ちだった。
「なんや〜、もう終わり?楽しい時間ってホンマあっという間やなあ」
あんな接戦のあとでも金ちゃんはケロリとして笑っている。汗だくになって息を吐いている俺とは大きな違いだ。
「今日の白石の球」
クールダウンとして軽く走りながら、金ちゃんが話しかけてきた。
「最初は球に迷いがあったけど、あとからどんどんビシッとしてきたなあ」
何を指されているか、すぐに分かった。
俺は金ちゃんに勝つために、迷いを捨てた。
悩むことをやめて、謙也に告白すると心を決めた。
そうさせてくれたのは、何もかも金ちゃんのおかげだ。
金ちゃんと向かい合って立つコートは、ひたすらに孤独だ。自分がこんなにも広いコートのすべてを守りきれるか、いつも不安でしょうがない。
実力が互角な金ちゃんと俺は、いつでも鏡と戦うような試合をした。自分の心ひとつで勝敗が変わることを何度も身をもって知っている。だから俺はいつも、金ちゃんと戦っていると言うよりは、自分の心と戦っていた。
巨大な敵と相対して、怯える心。それは今の俺の悩む姿そのものだった。自分の覚悟が決まらないから怖がって、いつまでも試合を始められないまま踞っている。
だけど今日、コートに立つ金ちゃんの姿を見た。彼はただテニスが楽しそうだった。勝っても負けても楽しくて堪らないという笑顔が、俺に決心させてくれたのだ。
コートに立ったなら、覚悟を持って勝負をしよう。勝っても負けても笑えたらいい。今しかない青春、今しか出来ない恋、全部楽しんだ方がいい。
恋をしてしまった。
それはとても困難な恋で、勝負の行方さえ見えない苦しい恋だった。
だけど、それさえきっと輝かしい記憶になる。
いつか「あの時は楽しかった」と心から思えるように、今、全力で勝負をしよう。
「金ちゃん、俺と試合してくれておおきに」
別れ際、金ちゃんにそう言えば、「こちらこそ、たこ焼きおおきに〜」と笑って返された。
「白石、最初よりイケメンに戻った気がするわ。良かったなあ」
「ホンマ?金ちゃんのおかげやわ」
「あい?なんでワイのおかげなん?」
まだ幼い金ちゃんは、自分の持つ力を知らない。それは怪力のことなんかではなくて、自分の生きざまやプレイが与える力のことだ。人に影響や感動を与えられる、それはほんの一握りのスーパースターだけが持ちうる特権。俺は確かに、金ちゃんとの試合の中でとても大切なことに気付かされた。
「金ちゃん見とると元気になんねん。せやから、おおきに」
金ちゃんは言われている意味もよく分からないようだったけれど、「そうなんや〜」と楽しそうに笑っていた。
「またなんか嫌なことあったらいつでも言うて!ワイの元気分けたるで!」
金ちゃんの笑顔に十分に力を貰って、俺は金ちゃんと別れた。
一人歩く帰り道、俺は今日までのことを思い出していた。
楽しいこと悲しいこと、色々あった。苦しかったけれどたくさんの感情を覚えて、俺はこの関係の中で成長したのかもしれない。
明日、俺は謙也に告白する。
今やっと試合開始の合図が鳴った。
常に2分の1で未来を選ぶ。
皆が当たり前にやっていることだ。
当たり前すぎて無感動に行われている。
でもあるときは胃の痛むまで悩んで選ぶ人間がいる。
選択肢の内容は気にしても、選択するという行為までは誰も気にも止めない。
だけど、選ぶことを選べなかった俺には分かる。選びたくなくて逃げ出そうとした俺には。
選択する、その行為自体がとても力強く未来ある行為だということ。
「逃げる」「選ばない」それもまた一つの選択だということ。
俺たちはこの世に生きている限り、選ぶことから逃げられない。
だからこそ、それは生きる努力といって差し支えない。
誰もが当たり前にやっていることだから、褒めてはくれないけれど俺は今、俺を褒めたい。
未来が削られる悲しみも、未来を決める楽しさも「選択」という行為の中にある。
だから俺はまた選ぶ。
明日、どうやって謙也を呼び出すか。
覚悟さえ決まれば、勝敗が見えなくても楽しめた。俺は選ぶことを純粋に楽しんで、スキップしたいほど逸る気持ちを抑えながら帰路を急いだ。
結局、俺は電話を選んだ。
帰宅して早々、制服のままベッドに腰掛けて謙也にコールする。
1コールで受話するのは謙也らしいと言えばらしかったが心臓に悪かった。まだ何を言うかも決まっていない。
「もしもし、白石?」
「あぁ、スマンな謙也。あんな、ちょっとお願いがあるんやけど」
「何?」
「大事な話があんねん。せやから、明日の放課後、屋上に来てくれん?」
今ここで気持ちを伝えてしまっても良かったけれど、せっかく心を決めたのだからきちんとした舞台で勝負をしたかった。
謙也には俺の覚悟が伝わっただろうか。妙な返事を貰いたくなくて「頼むわ」と念を押し、一方的に電話を切った。
「……はあ、心臓バクバク」
独り言を呟いて携帯を放り出し、仰向けに寝転んだ。まだ少し赤い目を撫でて、俺は明日を想う。
明日、最終決戦。
最後だけど、最後じゃない。
だってあの夏の日、俺たち四天宝寺中テニス部は最後の試合をしたけれど、それでも俺たちのテニスは終わりにならなかった。
終わっても、また始められる。
続いていく、生きている限り。
次の日の朝、鏡の前で自分の目をチェックした。目の下にまだ少し赤みが残っていたけれど、これくらいなら大丈夫だろう。きっと今日の俺なら金ちゃんにソックリさん認定はされないはずだ。
登校中、見慣れた景色がいつもより何倍も輝いて見えた。そういえばあの日の朝もこんな風に、世界のすべてが眩しく見えたっけ。もう半年も前になるあの日には、俺は既に謙也のことが好きだった。いつから好きだったのだろうか。始まりは思い出せないが、その気持ちは常に傍にあった気がした。
学校では特に何も変わらない一日を過ごした。クラスメイトと話をして、先生の授業を聞いて。謙也と話をしなかったことだけがいつもと少し違う点。不自然な今日のことはきっといつまでも記憶に残るだろう。意識して視線さえ交わさなかった、その甘酸っぱい気持ちが鮮烈な色となって、今日この日を残していく。
授業はいつの間にか最後の数学になっていた。数式の並ぶ教科書の隅に、俺は三角形を書いてみる。三辺がそれぞれ等しい、正三角。
取捨選択。
選び取る裏側にはいつも、選び捨てられる人がいる。
誰が選ばれて、誰が選ばれないのか分からない。もしかしたら俺が選んでも、俺は選ばれないかもしれない。
でも、誰が泣いても恨みっこなしだ。
選ばないまま泣くよりも、俺は選んで泣くことを選んだ。
選びたくない人にも、選ぶ人が選択を迫る。
選択は強い力で俺たちを引きずり込んで、生きている実感をくれる。
俺と謙也と財前、三人で正三角形を画いた日々は。
選ぶことの辛さ嬉しさを痛切に感じていた。
誰もが同じだけの勝率で、誰もが同じだけ負ける不安を抱いている。
皆同じ気持ちでいる、だからこそ考慮して選ぶことが難しかった。
誰もが幸せになりたかったし、誰もが好きな人に幸せになってほしかった。そして自分を好きになってくれた人には感謝があった。応えられないことが苦しかった。けして言うことは許されないけれど、好きになってくれた人の幸せをそっと願っていた。
「起立、礼!」
「「ありがとうございました」」
教科書の片隅に書いた三角形は消さなかった。一つの終わりの印として、残しておきたくなったから。
謙也はもう教室を出たようだ。相変わらず何でも素早い奴だと思い、そこも好きだと続ければ頬が緩んだ。
俺も急いで支度を終え、謙也を追いかける。廊下から走り出したいほどだったけれど、いつもの自分らしくゆっくりと歩いた。
自分のスタイルを崩さずに、自信を持って勝負をする。これも金ちゃんが試合を通して教えてくれたことだ。
階段を上りきり、屋上に出る。
重い扉が背後で閉まったけれど、屋上には誰の姿も見当たらなかった。
振り返り、扉の上を見たけれど、そんなところにいるわけでもなさそうだ。
もしかして謙也は帰ってしまったのだろうか?
嫌な予感がふと脳裡を掠めたが、俺は謙也を信じて待つことにした。
謙也が今どこで何をしているかは分からない。もし帰っていたとしても、呼び出したのは俺なのだから、とりあえずここに居られる限界の時刻まで待っていなければならないだろう。
俺はゆったりとフェンスに凭れ掛かり、長丁場も覚悟して座り込んだ。
それからどれくらい経ったのか。何度目かの「暇やな」を呟いて、一応は告白前だと言うのに昼寝してしまいそうなくらいリラックスして座っていた。
すると突然、ゴウン!という乱暴な音がして屋上の扉が全開になった。
現れたのは間違いなく俺が待ち望んでいた人物で、俺は立ち上がって姿勢を正す。
「……スマン、待たせて」
謙也は一体何をしていたのか、走ってきたように息を切らして俺の前に立った。
「ど、どないしたん?大丈夫?」
謙也は膝に手を突いて、ゼェハァと荒い息をついていた。俺に掌を見せるそのジェスチャーは、「大丈夫、気にせんでええ」の意だろうか。息を整え終わったのか、謙也がパッと顔を上げた。
謙也の異様な雰囲気に、告白のムードが出ない。
でも呼んだからには言ってしまわなければいけない。どうせ謙也にもこの呼び出しの意味は伝わっているのだろう。
ここまで来て怖気づくわけにはいかなかった。
「謙也、」
サッと風が吹いたから、今がチャンスだと思った。
「俺、謙也のことが好きや」
【Last Question】
→謙也ルート
→財前ルート
CHOOSEΔ TOP