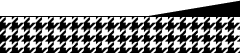弱気になるな、俺。今更立ち止まれるわけがない。
俺は財前を傷付けて、巡り巡って謙也まで傷付けた。
人を傷付けてまで何がしたいのか。
その問いに答えられなくなってしまったら、傷付けた過去にさえ無責任になる。
俺は幸せになりたいのだ。誰かを傷付けることは仕方ないことだったのだ。自己の正当化だとしても、この理屈でしか自分の思いを遂げられない。
俺は念じるように、「戦うんや」と唱えた。
昇降口を出たら辺りはすっかり夜の闇に包まれていた。僅かな電灯が朧気に足元を照らしてくれる。振り返っても屋上は見えなかった。俺の後に帰る財前のことが少し気にかかったが、俺はすぐにその心配を放り投げた。
校門の前、噴水の近くに来たとき、反対側で動く影を感じた。相手も同じだったのか、そいつはひょっこり噴水の影から顔を覗かせた。
「……千歳?」
「そん声は白石?」
千歳から俺の姿は見えなかったのか、千歳は近付いてきてやっと確信を得たようだった。
「こんな時間になるまでどないしたん?」
「それは白石も同じたい」
多く自分のことを語ろうとしないこの友人は、答えにくい質問があれば常に問い返してその場を切り抜けた。その癖を知っている俺は深く追及することをやめ、自分についても「ちょっとな」と誤魔化すだけに留めた。
「ちっと、ね。
……白石、泣いとったっちゃろ?」
「はあ?なんで?」
「誤魔化さんと話してみんね。千里眼の千歳さんには何でもお見通しなんよ」
たとえ目が赤かったり涙の跡が付いていたとして、この暗がりの中、ましてや千歳の視力でそこまで見つけられるとは思わなかった。だからきっと千歳は勘でそれを言い当てたのだろう。この男からは時々、常人にはない天賦の才を感じる。
「はぁ……、千歳には敵わんわ。千歳の言うとおりやけど、誰にでも言わんでな」
千歳は軽い様子で「言わんよ〜、言う相手もおらんっちゃ」と笑った。
「白石、今から帰るんね?」
今少し俺に近付いた千歳の足元からカランという音がした。この寒い時期に、千歳はまだ鉄下駄なんぞを履いているらしい。夏に聞けば涼を感じる良い音だが、今は剥き出しの足だけが想起されて寒々しかった。
「せや。すっかり遅うなったから早よ帰らな。千歳も早よ帰らなアカンで」
「うん、白石送ってから帰るばい」
千歳は躊躇いなくそう言った。
「え?俺男やで?」
「男だったら送っちゃダメなんね?」
「そう言うわけやないけどな。でも俺はホンマに一人で平気やから、千歳は早よ帰り?」
今は一人でいたい気がした。同じ部活で過ごしたとは言え、テニス以外の千歳のことはよく知らない。他人に気を遣いながら帰るだけの気力さえ、もう自分には残っていない気がした。強く断ろうとしたタイミングで、遮るように千歳が喋る。
「俺と白石はあんまり仲良くないけんね。ばってん、だからこそ喋ってしまえることもある。幸い、俺には白石ん秘密をバラす相手もおらんし」
驚いて千歳の顔を見たら、「友達おらんけんねえ、残念たい」と冗談をかまされた。
千歳のサボリ癖は部活だけでなく授業もで、そもそも学校に来ないのだからそうなるのも仕方ない。転校の時期も遅かったから親しい友達がいないことは想像に難くなかった。しかしこの男には遠い土地に親友と呼べる存在がいる。だから口で言うほど寂しくはないのかもしれなかった。
「……秘密を告白出来る相手って、それだけで信頼できる友達のような気がするんやけど」
俺がそう言ってやると、千歳は嬉しそうに笑った。確かに俺たちは僅か一夏を同じ目標に向かって進んだチームメイトに過ぎなかったけれど、それはかけがえのない絆だ。時に言葉を交わすより、一つのボールをやり取りすることで多くを語り合った。だから千歳が思慮深く慎みある人間だということを俺は心の底から知っている。
「とにかく!白石は美人さんばい、素直に送られときなっせ」
まだ口説くような演技を続ける千歳に小さく噴き出した。これも千歳なりの励まし方なのだろう。もしかしたら泣いていた俺を心配したのかもしれない。夜に響く冷たい下駄の音と共に、俺は歩き出した。
こうやって千歳と二人きりで歩いたのは初めてかもしれない。もう夜はすっかり始まっている。怖いわけではない、ただなんとなく心細い気がしてポケットの中に手を隠す。
「なぁ、千歳。叶わなくとも自分の好きを貫くのと、好きやないけど誰かの願いを叶えてやるの、どっちがええと思う?」
千歳は暫く黙っていたが、あまりにその時間は長かった。本当に聞いていなかったのではないかと俺が疑いかけたところで、千歳は唐突に声を発する。
「さぁねぇ」
悩みを聞くよ的なことを言っていたのにそれだけか、とツッコミかけたが、千歳がまだ何かを言おうとしていることに気が付いて口を噤んだ。
「……白石は、どっちを選ぶん?」
分からない、という思いが強かった。どちらを選べばいいか自信がないから訊いたのに、問い返されて答えられるはずがない。
そう言い返したい言葉は先手を打たれて砕かれた。
「俺に訊く前から、白石の気持ちはどちらかを選んどるはずよ」
白い息を吐き出しながら、千歳は言った。俺を見ることもなく、前を向いたまま。
俺は気付いていたのだろうか。
昨日も今日も、俺は分かっていた気もする。だけど、揺れていた。
俺は自分の気持ちを大切にしたい。
叶わなくてもいい。
迷わずに謙也を選びたい。
そんな自分を、いつも臆病な自分が邪魔した。
戦いたくない。
傷付きたくない。
このままでいたい。
自分の選択を、ネガティヴな意見が阻んでいた。
謙也は俺を選ばない。
俺のことを好きにならない。
財前のことを忘れない。
自信がないから核心を隠して、分からないフリをしていた。でも、そんな演技も千歳の前ではすべて無駄だった。
もう誤魔化せない。
立ち止まってしまった俺を振り返り、千歳はトドメを刺した。
「白石、覚悟を決めなっせ」
その言葉を聞いて、弾かれたようにまた涙が込み上げてくる。
「……好きでいたい、俺は、俺は、」
嗚咽交じりにそれだけ言うと、もう次の言葉は出てこなかった。
自分の好きを叶えたい。低い可能性でも、未来に賭けたい。言い訳のような「でも」や「だけど」に負けたくない。
もうすぐ家に着く。そう思っても涙は止まらなかった。次々溢れ出して洪水のようだ。
俺は、謙也を選ぶ。自分が愛することを選ぶ。自分の愛が届くことを祈る。財前の愛が俺に届かない事実を棚に上げて、自分の願いだけは叶うと信じる愚かさに打ちのめされながら。
「ちとせ、スマン、こない泣くつもりじゃ、」
手で目元を覆ったけれど、庇いきれない数の雫が流れ落ちた。
千歳がそっと抱き締めてくれる。しかしそれも恥ずかしさより安堵の方が大きかった。背中に回された手も優しかった。
「やっと正直になれた?」
ぽんぽんと叩かれるリズムに甘えて、俺は泣いた。千歳の肩を借りて絞り尽くすように泣けば、頭痛までぶり返して、その痛みにまた泣いた。子供のように泣き続ける俺に、千歳は「辛かったんね」「頑張ったんやね」と声をかけて宥めてくれる。
泣き止むタイミングは難しかった。もっと泣けそうな気もしたし、早く泣き止みたい気もしていた。
それでもだんだん照れ臭さの方が強くなっていたから、俺は鼻を啜り上げながら千歳と離れた。
「ごめ…んな、千歳」
鼻が詰まって喋りにくい。こんなにも泣いて、俺はどんな顔で家に帰ればいいのだろう。
「めっちゃ泣いてしもた。……恥ずかし」
「もう笑わんでええよ」
俺が無理して笑うことを、千歳は拒んだ。
千歳の長い腕に抱き寄せられて、俺はもう一度厚い胸板に顔を埋める。千歳は春のように暖かかった。
「千歳、俺もう泣かんから、」
「俺が寒いけん抱き締めとるだけたい」
優しくしないで、と言いたかった。弱っている心に千歳の優しさが沁みる。
「アカンって。こんなとき抱き締めるとか狡いわ」
「先に泣き出したんは白石ばい。俺は狡くなか」
千歳から離れようとしたけれど、千歳が思った以上に強く俺を抱き締めていたから抜け出せなかった。
「どうせ白石は、明日からまた無理して笑うんやろ。だから今だけは、休んでよかばい」
俺が始めた戦いで、俺は勝手に傷付いていた。自業自得と言えばそれまでなのに、千歳はそれを労ってくれる。俺の戦いを許されたような気がして嬉しかった。
「……ホンマ、おおきにな」
ゆっくりと千歳の肩を押して離れた。
俺は千歳に微笑んでみせる。
一度は拒まれた笑みを再び向けたのは、
→好きな人に見せるのにそれが一番相応しかったからだ。俺は目の前に現れた新しい選択肢を選んだ。
→俺はもう強がるしかなかったからだ。
心はもう笑えないから、せめて顔だけは笑っていたかった。目が笑えなければ、口だけでも笑っていたかった。
CHOOSEΔ TOP