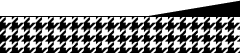俺の手首を掴んだ財前は、珍しい表情だった。滅多に見られない満面の笑みは不意に向けられると当惑してしまう。違和感が酷く、目の前にいるのは自分の知らない人間のように思われた。
「今日部活休みなんスわ。久々一緒に帰りましょうよ」
財前は甘えるような声を出す。財前にとって今は幸せなひとときなのだろう。好きな人に会えた嬉しさ、話が出来ている楽しさを感じているはずだ。財前の好きな人が俺でなければ、「良かったな」と言えたはずなのに、今はそういうわけにもいかない。明るい財前の隣で俺の気分はどんどん暗くなっていった。
「部長の仕事には慣れた?」
一緒に帰りましょう、と誘われた言葉には何も返さなかった。話題をすり替えたけれど、そもそも然程財前との会話を続けたかったわけではない。しかし俺たちは三角関係であることを除けば同じテニス部の仲間なのだ。俺と財前は新旧の部長という特別な関係でもあるし、私的な感情だけで邪険に扱うことは出来なかった。
「まあ。白石部長みたいに上手くまとめられるかは分からんですけど、自分なりになんとかやってますわ」
「そうか」
本当ならここで「財前なら上手くやれると思うわ」くらい言った方が良いのかもしれない。いつもの俺なら絶対に言うだろう。だが、好きでもない相手を褒めることは出来ない。俺に想いを寄せる財前が俺の一言で喜ぶことも分かってしまうから、余計に気を持たせるようなことは言えず、俺は冷たく感じられる程の態度を取ってしまう。
校門が近付いてきた。校門を出たところに目立つ金髪が見える。あのシルエットはたぶん謙也だろう。待つのが苦手なくせに俺を待ってくれている。そんな些細なことからいちいち優越感を得ようとしてしまう自分が浅ましくて嫌になるけれど、そう感じてしまうことは止められなかった。これ以上謙也を待たせたくなくて、走り出したい気持ちになったが同時に財前に話し掛けられた。
「センパイ、」
「スマン財前、今日もう他の奴と帰る約束しとってん」
財前の視線は俺が誤魔化した「他の奴」を見つけたようだ。謙也は校門の隅で携帯を弄っている。謙也の姿を見て、財前の機嫌が急激に悪くなったのが分かった。忌々しそうに謙也を睨んで、あからさまに拗ねている。そういう素直な感情表現が俺は苦手だ。自分を制することも出来ない子供のように見える。拗ねていたら俺が機嫌を取ってくれるとでも思っているのではないか。少し酷い考え方かもしれないが、俺は自分の思考の中の財前に苛ついた。
唐突に財前が俺の手首を掴んできた。驚いて財前の顔を振り返ると、同時に財前も含みのある笑顔を向けてくる。最初に掴まれた時より随分と強い力を加えられた。言葉はなかったが「逃がさない」と言われているように感じた。
「ちょっ、財前いきなり何」
「別に。センパイの手首の太さ測っとるんスわ」
もう謙也の表情まで見える距離に来ている。俺たちのこの状況は手を繋いでいるように見えないだろうか。謙也がいつ顔を上げるか分からないので気が気でない。放して、と小さく呟くと財前はしらばっくれて「え、何か言いました?」と笑った。財前の表情がまた屈託のない笑顔に戻っていて、その計算高さはゾッとするほど気味が悪い。
「お願い、早よ手放して」
こんなところを見られて謙也に勘違いされたら困る。もしそんなことになったら俺は絶対に財前を許せないし赦さないだろう。焦っても俺の手首は財前の手中にすっぽり収まっていて、財前は全然俺の願いに聞く耳を持たなかった。お願い、手を放して、それでちょっと離れて。聞き入れられない頼みを呟きながらだんだんと泣きたくなってくる。なぜ俺はこんな目に合っているのだろう。人の嫌がることをして、財前は好きな人に嫌われるなんてこれっぽっちも考えないのだろうか。
「財前、ほんま放してや。俺、謙也と帰る約束しとるんや」
俺が声を出した一瞬に謙也が振り向いて、楽しく話しているなどと勘違いされたらどうしよう。そう思うと怖くて、一言喋るだけでも勇気を必要とする。早口で言って俺は財前を見つめた。財前は至極冷たい声と表情で「あっそ」と言ってのけて、俺の手を放した瞬間に大声を上げた。
「謙也さーん、こっちですよー」
愛しい者に名を呼ばれ、謙也はパッと顔を上げた。それからすぐに花が咲くように笑って手を挙げてくれる。その行為すべて、向けられている位置が少しずつ俺からズレていて、分かっているつもりだった現実を突き付けられた。俺では謙也をあんな笑顔には出来ない。今謙也がとても楽しそうなのは、俺ではなく財前のおかげなのだ。
謙也が走って来て、財前に話し掛ける。俺の隣の財前に。約束していた俺ではなく、財前に。
「どうしたん、財前。デカイ声出すなんか珍しいやん」
「俺も一緒に帰ってええですか。たまには三人で帰りましょうよ」
財前のいきなりの提案に面食らった。俺にはそんなこと一言も訊かなかったくせに。漏れそうになった舌打ちは抑えられたが、引き攣る顔だけはどうすることも出来なかった。せっかく謙也と約束したのに、こんなことになっては約束なんて水の泡だ。俺に言えば断られるから、快諾するであろう謙也に訊いたのだろう。財前の読み通り謙也は「勿論ええで」と笑顔で答えていて、俺はもう何もかもが嫌になりそうだった。
たぶん財前は俺と謙也を二人きりにしたくなかったのだ。自分も恋をしているから、そうしたい財前の気持ちは分かる。邪魔をしては俺に嫌われるかもしれない。それでも俺と謙也が上手くいってしまうよりはいくらもいい。二人を自分の目の届くところに置いておかなければ。そう思ってこのやり方を選んだのだろう。されたことは腹立たしいが、財前の気持ちも痛いほど分かるから強く責められない。恨む気持ちはあるけれど非難に徹することが出来ないのは、同じ状況なら俺も同じことをしたかもしれないと思う心のあるせいだった。
そこまで財前の気持ちが分かるのに、愛されることに感謝も優越も感じられない。俺はただただ好きな人以外から向けられる好意が疎ましかった。
帰り道は苦行のようだった。三角関係になってからというもの、三人で集まることは意識して避けていた。だから久しぶりの「近すぎる距離」が不安で、一刻も早く帰りたくなる。俺の気持ちが伝わったのか、他の二人も同じことを思っていたのか、寄り道の提案もないまま三人は急ぎ足で帰路を歩いた。何かの弾みで正三角形が壊れてしまうのではないか。誰かが声を出せばそのたび気を尖らせて、そしてそれを悟らせないように極めて平穏な自分を装うのに必死だった。
一番家の近い財前は俺たち二人を残して帰宅することがとても嫌なようだったけれど、こればかりはごねても仕方ないのでおとなしく家に入っていった。
二人きりになった俺と謙也の間には会話が何もなくなった。それも不自然だと思って俺は何かを喋ったが、謙也の返事も冴えなかったので俺たちは結局また自然と無言になる。「俺、財前のこと好きやねん」そう言われたように思って俺は謙也を見たけれど、謙也は何も変わりなく前を向いて歩いていた。
「謙也、今なんか言うた?」
「ハァ?何も言うてへんで」
あぁ、そうと力なく笑った自分が随分みすぼらしい存在のように感じられる。不安感が強すぎて一番聴きたくない言葉が幻聴として聞こえたのか。
結局必死に誘って帰ってもこの状況が限界なのだ。俺にはここで告白する勇気があるわけでもなく、そして謙也に宣言される覚悟があるわけでもない。心の中で財前に「心配するようなことは何も起きてへんで」と伝えて自嘲した。
そのまま俺と謙也は曲がり角で別れて、それぞれ歩きだした。別れたあと俺は一度だけ振り返ったけれど、謙也は走って行ったのか、後ろ姿さえもう見えなかった。
ただ帰るだけなのに一試合以上に疲れて帰宅した。扉を開けるとリビングで姉妹が仲良く寛いでいる。
「おかえり、クーちゃん」
姉がこの時間から家にいるのは珍しいと思ったが、なんとなく日常会話が億劫で何も訊かなかった。二人の座るソファの横に鞄を立て掛けてから、洗面台で手を洗ってうがいをする。鏡に映った自分が疲れて見えて、目も当てられない気になったからすぐ目を逸らした。
リビングに戻って自分に似た二人の顔を見ると、話すことが億劫に感じられた気持ちは何処へ行ったのか、急に尋ねてみたくなった。
「なあ、二人は愛されるんと愛するんやったら、どっちがええ?」
笑ってしまうくらい唐突で、何でもないと誤魔化せる話の種でもない。
しかし二人は茶化しも囃し立てもせず、ただ笑って「なんや、クーちゃん、うちらと女子会したいん?」と聞き返した。
「クーちゃんの頼みとあらばしゃーないな。とりあえずアイス取ってきて。そしたら考えるわ」
ここぞとばかりに友香里に使いっぱしられたが、俺は文句一つ言わなかった。言う気力さえ残っていなかったともいえた。
スプーンとアイスをセットにして手渡すと、妹は「おおきに」と言ってすぐさま蓋を開け始める。
「それで、何やったっけ?愛するんと愛されるんとどっちがええかって?」
アイスを食べている姉妹の向かいで俺は頷いた。
「私は愛されとる方がええなあ。その方が楽やもん。好きな人とおったら好きで好きでめっちゃ苦しいし、浮気してへんかとか、嫉妬ばっかしてしもて自分がどんどんめんどくさい奴になるのが嫌なんよ。好かれとって、自分で好意をセーブできる方が、自分を乱されへん感じがして付き合いやすいわ」
スプーンを右手に持ったまま、友香里は一息に喋った。それだけ言うとまたアイスを食べる作業に戻っている。
「なんや、友香里は大人やなあ。でも私は反対やわ。私は愛しとる方がええな。だって愛されて付き合うやろ。それで浮気されてみ?なんかショックやない?自分には気持ちがいっこもないのに関係に縛られるようになんねんで。好きな人やったらまだ許すとか怒るとかしようがあるけど、自分が選んだわけでもない人に傷つけられるんはなんか許せへんねん」
「お姉ちゃん、前提がネガティブやわ」
「せやかてなー、好きでもない奴と付き合う気にはならんわ」
「いつまでも好きちゃうわけやあらへんよ。好きになれそうな人なら付き合って、そのうちちゃんと好きになんねん」
「ふーん。んで?クーちゃんはどうやねん」
急に話を振られて、俺はどう言ったものかと悩んだ。
「せや、うちらの意見言うたんやから、クーちゃんも教えてや」
「俺は……、」
どっちにするか、迷うとるんや。
正直にそう告げることは躊躇われて、「俺はまだよう分からへん。友達に聞かれて気になったから、訊いてみただけや」とはぐらかした。
「えー、何やそれ!」
姉妹からの非難を背中で受け止めながら、俺は一人の世界に潜っていった。
二人の言葉をぼんやりと反芻する。
愛すること、愛されること。
俺はどうしたらいいのだろう。
悩んでいるところに携帯のバイブが受信を報せた。メールは財前からだった。
「先輩らみたいに大人ちゃうんで、俺はこのまま知らんフリとか続けられません。ハッキリキッパリさせたいです。話がしたいんで明日の放課後、屋上に来てください」
学年は一つしか違わないのに、財前をとても若いと感じた。自分にない直球さが痛いくらい、青く眩しかった。
携帯を手に持ったまま、そこにある文字をぼんやり見つめる。俺は明日、財前の待つ屋上に
【Q2.】
→結局行ってしまうのだろう、と思った。
→たぶん行かないのだろう、と思った。
CHOOSEΔ TOP