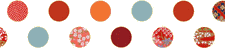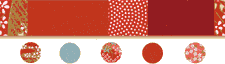
中学生の時、私は馬鹿だから勉強は出来なかったし、その上授業なんかつまらなくて、学校へ行くのは友達と会う為だけだった。それだけが楽しみで通い続けてた。無駄に駄弁るのが楽しくて、でもどんどん時間は過ぎてしまって、いつの間にか外が暗くなって友達が門限とか塾とかの理由でぽつぽつ帰り始める。そんな中私は、ただ帰りたくなくて、校庭へ出てボーッとしてたり。七時過ぎくらいになってとぼとぼ家に向かって帰り始めて。友達には直ぐにでも帰ろうと思える家があって、家族が居るのに、私にはそんな居場所無くて、迎えてくれる家族も居なくて。羨ましかったし、友達にあって私にはそれが無い、と言うのが恥ずかしかったし後ろめたかった。必死に話題を合わせて、その中で「理想の家族」を混ぜたりしてた。
私は家族って寄せ鍋みたいだなってずっと思ってた。其々の食材が互いの味を引き出し、それを旨味へと変える。言わば皆名脇役であり主人公なのだ。その味がまた暖かくて、身体に染み渡る。でも食材同士が合ってなければチグハグな味になってしまうし、そもそも火が付かずに冷めたままでは良い出汁を出す事すら出来ない。美味しい鍋が世間一般の家族なら、私の家は間違いなく後者の方だった。
「ただいま」
返事は無いし玄関は暗い。リビングの電気は消えていて、二階の寝室の方から父親のいびきが聞こえてくる。母親は居ない。何処か出掛けているのだろう。電気をつけて冷蔵庫から昨日作った残り物の肉じゃがを出す。電子レンジで温めて、ご飯と一緒に頂く。温めたのに、何か冷たくて、喉に通らなくて。咀嚼する度に味が失せて行く様で、自分で作っといてなんだけど、酷い味で。美味しくないの、全然。私は家族と机を囲んで揃ってご飯、なんてした事無かったし、そもそもご飯は自分で作って用意するものだった。その内なんだか口ん中が塩辛くて、今度はしょっぱくて食べてらんなかった。ボロボロ馬鹿みたいに泣きながら、残り物の肉じゃがを必死に食べて片付けた。
こんな家庭だったけど、私はずっと冷たい残り物とかじゃなくて、家族って暖かい物だって信じてた。
「先生、ただいまー」
今日のお夕飯の食材とついでに晩酌用のお酒を買って帰宅。明るい廊下を歩いてリビングへと顔を出すと先生が本を読んで待っていた。
「おう、お帰り。」
私の顔を見た先生は本を閉じて、すっと立ち上がってこっちに向かって来た。何やら机にはもうお猪口と一升瓶が置かれている。
「あれ、先生呑んでたの?珍しい一人酒?私も呑んで良い?」
「いや、これから呑むつもりだった。粂、勿論お前もな」
その答え方にちょっとドキッと来て目を逸らして苦笑いを浮かべてしまった。天然タラシなんだよねえ、この人。
「ちょっと何もう…あ、今日寒いしお鍋にしようと思って、私もお酒買ったから、軽いおつまみ作るね」
「ああそりゃ有難いな、鍋が出来次第、酒を呑み始めるとするか」
「うん、任せちゃって〜美味しいお鍋さんにするから!」
袖を捲りグッと拳を握ると先生は何やらくつくつと笑い始めた。それがちょっと照れ臭くて顔が熱くなり出す。鍋の食材は工夫をしてそんじょそこらのお鍋とは一味違う、格別美味しい物に仕上げるつもりだ。先生曰く、私の料理は「居酒屋の小料理」らしい。居酒屋通だし、私にとっちゃ光栄だった。火加減に気を張り、適度な大きさに切った食材を鍋の中へと入れぐつぐつと煮る。次第に灰汁が出始めて、辺りに良い匂いが立ち込める。先生が後ろで「今日の鍋は美味そうだなあ」と褒めてくれた。それに「期待しといて」と返事をし、灰汁を取り除いて調味料を入れて行く。
鍋つかみを付けて鍋を机へと運び、食器を並べる。箸を揃えて机へと起いて鍋の蓋を取る。
「はい、お待ちどうさま!頂きます」
「おいおい、待たんか粂」
何やらギョッとした様子で先生が止めに入って来た。
「ん?どうしたの?」
「先ずは乾杯だろう、こう言う時は。」
「え?今日何かあったっけ?」
「お前、それ本気で言っとるんか?」
本気で分からず首を傾げる私に酒を注いで差し出して来た先生。私がお猪口を受け取るとふふ、とはにかんで。
「お前さんの誕生日だろう、今日は。」
「………あぁー!!!」
言われて気が付いた。思わず大声を上げて驚くと先生が目を丸くする。どうやら私が誕生日を本気で忘れていたのかと驚愕しているらしい。いや、まあそりゃそうだわ。
「いっけない…年明けた時には1ヶ月後には誕生日だーなんて思ってたけど…」
「はっはっはっ道理で何か話が噛み合わんなと思った!まあ、ほら、呑め。」
「ぁ、あはは…うん、頂きます」
恥ずかしさでまだ呑んでないのに酔っ払いみたいに顔が赤くなって俯く。猪口に口をつけてくい、とお酒を飲み干した。
「すっごい美味しい…」
「そうか、お前さんの口に合うと思って用意したんだ。そりゃ良かった」
「……」
いくらしたんだろう…と顔が引き攣る。でも本当に美味しい。日本酒って渋くて辛くて強いのが多いんだけどその中でこれは果物みたいで甘口。凄い上品な味わいで喉越しが爽やか。一口で良い所のだって分かる。
「頂きます」
お酒に夢中になってると先生が手を合わせて鍋をつつき出した。ハッとして私ももう一度手を合わせて頂きます、と頭を下げる。先生がぱくり、と一口口に運ぶ。私もそれを追うように一口食べた。
「…美味いなあ、流石だな粂。」
「…ホントだ、美味しい」
私の反応に先生は呆気に取られた顔をした。でも意外で、ホントに鍋が美味しい。自分で作っといてなんだけど我ながら良い塩加減で、くどくないしだけど普通の鍋と違ってちょっとクセのある感じ。温かくて、今日みたいな冬の寒い日の主役とも言える。
「何だ、お前さんが作ったのに」
「いやあ、まさかここまで良く作れてるとは思って無くて!良かった〜美味しい物がご馳走出来たみたいで」
「全く…」
呆れた様な笑みを浮かべる先生、それに対して面目無いと困り眉になる。でも先生は怒るわけでも溜息を吐く訳でも無くて落ち着いた表情でまた静かに微笑んだ。そんな顔してゆっくりこっちを向くもんだから何事かと動けなくなる。
「謙虚で家事をこなし、その上勝気もあって女としての魅力も有る、儂は良い嫁を娶ったもんだ」
「………ぇ、ちょっ」
すっごい冷静にべた褒めされたから反応が遅れてしまった。一気にカーッと熱くなって慌てて冷たいお酒をぐいっと口に入れた。ごくりと喉に流し込んで、両頬をパンと叩いた。
「褒め、褒めすぎだし、そんな私…待って女としての魅力!!!?!?嫁!?!??」
「何だ今更」
「だってだって!!!そんな事言われた事無かったし!!まだ籍入れてないし!!!!」
「ゆくゆくは、の話だ。そもそも入籍と祝言の件はお前さん待ちだぞ?」
「う」
「急かすつもりは無い、老いぼれるまで待つさ。」
余裕ある態度で酒を仰ぎふう、と一息。先生には一生敵いそうにないや…。
「粂」
「はい…」
「誕生日おめでとう、いつも御苦労様、ありがとうな。」
「……いえ、此方こそ…どういたしまして、山頭火さん。」
「お、名前で呼んだな珍しい。どれもう一度呼んでみてくれないか」
「いやもう無理ぃ…恥ずかしい…」
家に帰ると迎えてくれて。そんでもって一緒にご飯も食べてくれて。美味しいと言ってくれれば流石なんて褒めてもくれて。おめでとうとか、ありがとうも言ってくれる人。私にとって彼は一番の家族だ。
素敵な旦那様のお陰で、今日の食卓も賑やかで明るくて、温かくて、何よりご飯が美味しい。お酒はもっと美味しい。御礼を言いたいのはこっちの方だった。ありがとう、先生。
………旦那様と言っても、未来のだけどね。