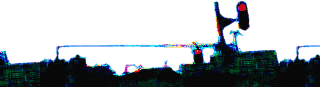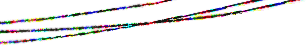
『君がいるから』 ハマイズ 頬に触れた温もりで眠りから覚めた。目を開けると泉と目が合う。どうやら温もりの原因は泉のキスだったみたいで、泉は少し困ったような顔をした。 「わりぃ、起こす気なかったんだけど…」 「いやいーよ…集合何時?」 ベッドの上に起き上がり、時計をちらりと見てからユニフォーム姿の泉に尋ねた。 「6時。軽く練習してから球場行く」 「そっか。後から応援行くから」 「おう、よろしくな」 「いっぱい打てよ」 「当たり前」 絶対勝つかんな、と泉がニカッと笑う。そっとキスをすると、はにかむような表情を浮かべて泉はパタパタと出て行った。 * * * * * 応援席から見るグラウンドはどこか現実味に欠け、すぐ間近で繰り広げられる熱戦は夢なんじゃないかとすら思ってしまうことがある。 野球を止めたのはもう2年も前なのに未練が残っているからだろうか。 …あの夏。グラウンドそのものから去ることと、マウンドから去ること。どちらかを選ばざるを得なくなって、オレが選んだのはグラウンドから去ることだった。 マウンドに自分以外の誰かが立ち、その後ろを守る自分、というものを受け入れることは出来そうもなかったのだし、選択が間違っていたとは思わない。 間違っていたとは思わない、けれど。 今だってマウンドを見れば、無意味な、だけれど、何度も何度も繰り返した仮定が頭を過ぎる。 “もし肘を痛めなければ” “もしもっと早く病院に行っていたら” そして結論はいつも変わることがない。 “そこに立っているのはオレだったかもしれない” 「…ま、おい、浜ってば」 「あ、ごめん、何?」 肩を叩かれて振り向けば、梅ちゃんが苦い顔をして立っていた。その様子からすると結構前から話掛けられていたんだろう。慌ててへらりと笑ってみせると、梅ちゃんははぁっと溜息をついた。 「何?じゃねーよ、そろそろグラ整終わんぞ」 「お、おう」 「しっかりしろよ、団長サン」 ばしん、と音がするくらい背中を叩かれて思わずむせる。しばらくゴホゴホとみっともなくむせた後、グラウンドを見ると泉がバッターボックスへと駆けて行くところだった。 朝の照れた可愛い様子とは打って変わって、泉は真剣な眼差しだ。野球をしている時の泉はすげーカッコイイ。片時も目が離せなくなって、未練も嫉妬も何もかも忘れそうになるくらい。 2年は長かった。だけれど、きっと泉がいなかったら球場に戻ってくるまでにもっと時間がかかっただろう。 だから、例え応援席から見るグラウンドがどこか現実味に欠けても、間近で繰り広げられる熱戦は夢なんじゃないかとすら思ってしまうことがあっても。 笑顔でガッツポーズをつくる泉の側で野球に触れていたいんだ。 「いずみぃー、ナイバッチー!!」 End ◎あとがき◎ フリリク第5弾です。リクエストが『試合中、自分がグランドにいないことに微妙な感覚を覚えつつ、泉を応援しているとそれを忘れてしまいそうになる浜田の話』でした。 お待たせしたにもかかわらず、素敵な感想をいただいたので掲載します。最近の遅筆っぷり本当に申し訳ありません!! 浜ちゃんの葛藤がちょっとでも伝わればいいなぁと思って書きました。 それではリクエスト本当にありがとうございました!! |