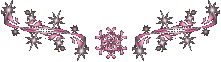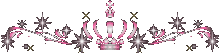
「そろそろ8時だぞ」
『…もう、そんな時間なのか…』
私に声をかけたのは愛する恋人、岡崎朋也。
私はいつも学校が終わったら夕飯の材料を買いにスーパーへ寄ってから朋也の部屋へ行く。
今もそうして仕事から帰ってきた朋也との時間を大切に過ごしていたのだが…。
高校を卒業し、社会人になった朋也と違い私はまだ学生だ。
そのため、遅くまで恋人の部屋に居座るのは良くないだろう、と8時には帰ることになっている。
それは他の誰が決めた訳でもなく、私と朋也の二人で決めたことだった。
自制心を持って、乗り越えていこう。
そう言った時の朋也の顔は大人の男の顔だった。
『それじゃあ私は帰るが、明日も早いんだから夜更かしするなよ』
「ああ、大丈夫だ。それより、本当に送っていかなくていいのか?」
『うん。明るい道を通っているし危ない所もないからな、平気だ。』
お前はゆっくり休んでくれ、と言ってドアを出ようとすると。
「智代」腕を掴まれ呼び止められたので振り返ると。
口に温かいものが触れ目の前には朋也の顔があった。
『ほんっとーに、お前はキス魔だなっ』
そう言うと朋也はニヤリと口元を吊り上げて
「おやすみ」
と少年のように笑った。
ああ、この笑顔が好きなんだ。
ふいにそう再確認した。
『うん、おやすみ』
だから私も微笑み返してキスをすると朋也の部屋を出て家へと帰った。
昔は帰ることが苦痛でしかなかった家。
帰る時に何を思っていたのかさえ、今は思い出せない。
いや、多分激しい怒りや憎しみで我を忘れていただけかもしれない。
それが、今は。
『……ふふっ』
朋也との幸せな時間を思い出して思わず笑みがこぼれてしまう。
また明日が待ち遠しい。
そうやって過ごしていけたら、これ程幸せなことはきっとないだろう。
家に着くと、家族全員が揃っていた。
みんながおかえり、と声を揃えて言ってくれた。
父さんは新聞を読んだまま、母さんは食器を洗いながら、鷹文はテレビにかじり付きながら。
それでも、こんな当たり前のことを嬉しいと感じるのは私くらいなのだろうか。
『私は一足先に部屋に戻る。復習しておきたいところがあるのでな』
「そう、頑張ってね」
『おやすみ』
「おやすみ」
お風呂に入って、少しニュースをみた後私は部屋に戻った。
これでも、と言うのは変な感じがするが私は町一番の進学校の三年生だ。
もう受験勉強に取りかからねばならない。
つい最近まで生徒会長を努めていたため、自分の受験のことなど考える余裕も無かったが。
正直、進学したいとは思っていない。
本音はこのまま就職して朋也と一緒に暮らしたい。
でも、朋也はそれをよしとしなかった。
[お前は進学するべきだ、と俺は思う。
学校の威信のためとかじゃなくて、お前自身のために必要なことだと思うからだ。]
真っ直ぐな目でそんなことを言われては私も反論できなかった。
――朋也は、私と一緒にいたくないのか?
そんな言葉が喉元まででかかったのを必死でこらえて、分かったと頷いた。
だから、妥協は許されない。
進学すると約束したのだから、それに全力を尽くすまでだ。
受験勉強のために朋也との時間を割いたこともあった。
会えない時間がどんどん増えている。
それでも、やらなきゃいけないんだ。
必死で物事に取り組むと、時間がすごく早く感じてしまう。
22時頃に始めた勉強も気づけば翌日の3時になっていて。
睡眠時間が3時間を切ってしまうことにため息を出さずにはいられなかった。
――もう寝なければ。
そうして1日1日が過ぎていく。