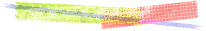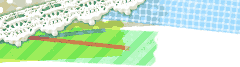
気持ちの良い昼下がりだった。
特に宛があるわけでもなく、ただただ暇を持て余し廊下を歩いていると、庭先でパパの姿を見つけた。
「………」
周りに人はいない。
ついでに、小さいわたしもいない。
今なら、いいかな―――。
「ん?」
わたしはなにも言わず、パパの隣に座った。
「どうしたの?」
別に。
どうもしないよ。
と、声には出さずに心の中で呟く。
心地よい風が、肩をすり抜け髪を撫でた。
一緒に揺れるパパの髪が肌にあたり、少しくすぐったい。
わたしが喋らないからか、パパも何も言わなくなった。
穏やか。
とても、穏やかな時間。
わたしが、ずっと欲しかった時間――。
「――」
パパの肩にそっと頭を預ける。
嫌がるような素振りひとつ見せず、わたしを受け入れてくれる。
少し前のパパだったら、考えられなかったことだ。
またこんな時間が、過ごせるなんて。
また、こんな風に、甘えられるなんて――。
無造作に膝の上に置いていた手に、パパの大きな掌が重ねられる。
指先から伝わる体温が、ひどく心地好い。
愛しい温度。
感じて思い出す。
パパのことは覚えているつもりだったのに、長い別離で、想像以上に色々なものが零れてしまっていたようだ。
「泣かないで」
目元を拭うように、パパの指先が添えられる。
わたし、泣いてたの?
でも、悲しくて泣いてるんじゃないから。
どうしようもなく嬉しくて、それをどう表現していいかわからなくて。
泣いてしまうの。子供みたいに。
「いい子だから、泣かないで。君に泣かれたら、どうしていいかわからなくなるんだ」
わたしを宥めるパパの声が、耳のすぐ横で聴こえた。
気付けば、パパの腕の中にいる。
伝わる体温が気持ちよくて、触れた部分から麻痺していくような感覚だった。
手を伸ばせば触れる距離
(致死量に満たない毒に侵されている、ような)