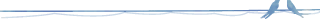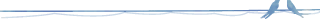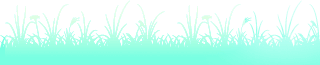幸村×佐助♀
幸村×佐助♀
2013.10.02 Wed 02:47
・現代パロ
・幸村×♀佐助
・幸村視点
・さすけが年上、幼馴染
・長いです
・細かな設定については脳内補完をお願いします
以上のことにご理解頂けましたら、本文へとお進み下さい。
『初恋の相手』
小さな頃から一緒だった。
年は向こうの方がひとつ上。
そのせいか、俺はいつも弟扱い。
さすけが高校に上がる頃、クラスの女子が「同学年の男子は子供っぽい」などと話しているのが耳に入った。その後も、「やっぱり年上がいいよね」「憧れるよね」と、恋愛話に花が咲いている。
…やはり、さすけもそのように考えているのだろうか?
一抹の不安が胸を過ぎる。
いつからか抱いていた気持ちは、自分でも『恋』なのだとハッキリ自覚していた。きっと、物心付いた頃にはもう好きだった。
世に言う、初恋というものを、俺は今までずっと続けている。
それなのに、いつまでたっても抜け出せない『弟』というポジション。
勇気を出して、行動を起こしたこともある。けれど、抱きつけば甘えているだけだと取られるし、好きだといえば「俺さまもー。」なんて軽い返事で返される。
たった一つの年の差が、俺は本気で恨めしい。
もし俺がさすけよりも年上だったら。幼馴染というこの関係は、少しは違っていたのだろうか?
もんもんとした思考に区切りが付けられたのは、翌週の日曜日のことだった。
その日はお館様の道場で鍛錬を積む日で、俺はいつも通りにさすけの家へと立ち寄った。幼い頃からずっと、二人で通ってきたのだ。
「ごめん!」
…だというのに、ヤツは顔をあわせるなり開口一番そう言った。なんでも、どうしても外せない用事が出来てしまった、ということらしい。
「もっと早く連絡を寄越せば良いものを…。」
「ほんっとごめん!俺さま、うっかりしてて…」
連絡云々が問題なのではなく、一緒に行けないのが問題なのだが、流石に正直に話す訳にはいかない。
不満に口をとがらせると、さすけは顔の前で両手を合わせ、この通りだと、深く頭を下げた。こちらの様子をうかがうように、時折ちらりと視線が上向くのがたまらない。
「つ、次からは気をつけるのだぞ!」
「! うん!」
パァッと、笑みが広がる。
常々弟扱いされてはいるが、俺は、こんな可愛いヤツを姉のようだと思ったことは一度も無い。
いつだって、一人の女の子として見て来たのだ。
「ありがと、旦那。だから旦那って大好き!」
…なのに何故、伝わらないのだろう。
さすけの家を出て、数十メートル。
聞きなれないやかましいエンジン音に振り返ると、先ほど自分が入って行った家の前に、一台の大きなバイクが止まっていた。跨っているのは、見知らぬ男だ。
おそらく、(俺はもちろん)さすけよりも一つ二つは年上だろう。
気になって様子をうかがっていると、男はバイクを降りて呼び鈴を鳴らし、インターホンへ声を投げかけた。玄関の扉はすぐに開き、さすけがひょっこりと顔を出す。
彼女は少し怒ったような素振りを見せた後、楽しそうに破顔した。
そして男の差し出したヘルメットをなんの抵抗もなく被ると、そのままバイクの後に跨った。遅れてシートに座った男の腰に、細い手が回される。寄り添うように、背中にぴったりと体が密着された。
俺の頭の中は真っ白で、ただ淡々と目の前の状況の記録だけを行っていた。
なんの感情も浮かんでこない。指先一つ、動かせない。
バイクが走り去る瞬間。俺の視線に気が付いたのか、さすけがこちらを振り返った。
笑顔でひらひらと手を振るその姿が、何故だか脳裏に強く焼きついた。
やっぱり、年上の男が良いのだろうか?
いつまでたっても、俺は弟のような存在でしか成り得ないのだろうか?
『初恋は叶わない』なんて、誰が言ったとも知らぬ言葉が頭を駆け巡る。
昔から通ってきたお館様の道場を休んでまで、あの男といることを選んださすけ。バイクの後ろに乗って、笑顔で手を振る姿は、まるでサヨナラを告げているかのようにも見えた。
きっと、もう、諦めるしかないのだろう。
道場で槍をふるいながら、俺はいよいよ覚悟を決めた。長い、長い片思いを終わらせる覚悟だ。
今夜。
今夜、さすけに告白をしよう。
思いを告げずに立ち去るなど、そんなスマートな真似が自分に出来るとは思わない。見苦しくとも、長年の思いをぶつけて、返事を貰わなくては、この先前に進めそうもない。
せめて、好きだという気持ちだけは知っておいて貰いたい。
『きっぱりと告白をして、きっぱりとフラれる。』
それで全てを終わらせるのだと決意して、二槍を強く握り締めた。いつも以上に、力も気持ちも高ぶっている。
あの男の顔がちらちらと脳裏に浮かび、その度に奥歯がギリッと音を立てた。嫉妬とも敵対心ともわからない闘志が、胸に熱く燃え滾る。
ちくしょう。年齢の差が、羨ましい。
夜。道場からの帰り道、さすけの家の前で足を止めた。見上げれば、彼女の部屋には明かりが灯っている。どうやら、もう帰ってきているらしい。
ちらりと覗いたガレージは空っぽで、彼女の両親の車も、昼間見たバイクも見当たらない。
今この家にいるのは、さすけただ一人のようだった。
「…。」
深呼吸をして、携帯電話の発信ボタンを押す。表示されている名前は勿論、『猿飛さすけ』。
『はいはーい。』
数回のコール音の後、いつも通りの軽い口調が聞こえてきた。
対して、俺は自分でも信じられないくらいに緊張していた。渇いたのどを咳払いでごまかして、今、家の前にいるのだと告げる。
出てこれるか、と尋ねるよりも先に、バタバタと忙しない音がして、玄関の扉が開かれた。
顔を覗かせたさすけに招かれるままに玄関へ入り、ドアをきっちりと閉じる。部屋に行かないか、という誘いは、流石に断った。
「上がって行かないの?」
「うむ。すぐ済む話だ、ここで良い。」
「そう?…ま、いっか。」
不思議そうに首を傾げたさすけだったが、すぐに気持ちを切り替えると、こちらを向いて話を聞く態勢を整えた。
…どう切り出そうか。
「あ、もしかして今日道場休んだこと?ほんとゴメンね、お詫びに今度…」
わずかばかり逡巡していると、さすけが先に口を開いた。お前は少しの沈黙も耐えられないのかと、少しばかり呆れてしまう。そうではないとピシャリと告げて、いったん会話を終わらせる。
流石のさすけもいつもと違う空気に気が付いたのか、大人しく口をつぐんだ。
正面からしっかりとさすけを見据えると、彼女は少しだけ居心地悪そうにして、わずかに顔をうつむかせた。
瞳には、不安とも、心配ともつかない色が滲んでいる。
「…どうしたの?」
一つ、大きく深呼吸をする。
気持ちはもう、落ち着いていた。
「好きだ。」
とてもシンプルな告白に、目の前の小さな肩が揺れる。
流石に、いつものように茶化されることは無かった。
目元に朱をさしたさすけは、動揺と困惑を明らかに、じっとこちらを見据えている。
「…そ、それって、どういう意味の?」
「そのままだ。ずっと昔から、好きだった。」
異性として。幼馴染なんかじゃなく、恋仲になりたいと、ずっと思っていた。
初恋だ、と最後に付け足して、これでもう以前のような関係には戻れないのだと覚悟した。
しばらくはこの思いを引きずることになるだろうが、言いたいことは全て伝えてある。胸には、悲しさよりも、思いを正しく告げられたという充足感の方が満ちていた。
さすけの前で女々しい姿は見せないし、あの男との仲だって、…今は無理でも、いずれは応援してみせる。
これでいいんだ、と心の中で大きく頷いて、さぁ一思いにフッてくれと胸を張った。
いよいよ顔を真っ赤にさせたさすけは、言葉を失くしてうつむいた。
困らせているのだと解ってはいたが、だからといって引く訳には行かない。
「答えを聞かせてはくれぬか?」
「…好き…。」
聞こえた言葉に体を硬直させる。いや、そんな訳がない。しっかりしろ、俺の耳、俺の頭!現実逃避をするにはまだ早い!
反応のない俺に、さすけは顔を上げて先程よりも大きな声で繰り返した。
「俺さまも、旦那が好き。」
好き。さすけが、俺を。俺と、同じ意味で。
…聞き間違いではなかったのか。
胸に飛び込んで来たさすけを受け止めて、細い背中に手を回す。嫌がらないことを確認して、抱きしめる腕に力を込めた。
予想外の出来事に、頭の処理が追い付かない。
とにかく『嬉しい』と、それだけは間違いない。
けれど、…だとしたら、昼間のあの男は一体何なんだ?
ありがとう、嬉しい、と繰り返すさすけを落ち着かせ、一度体を離す。改めて対面し、マジマジと彼女を眺めた。
紅潮した頬、輝く瞳、絶えず笑みをたたえた口元、…とても嘘を言っているようには思えない。
「よ、良いのか?さすけ。」
「なにその反応。良いに決まってんじゃん!」
不満気に膨れた頬が可愛らしい…とか、今はそんなことを考えている場合ではない。あのバイクの男のことだと、率直に問いかけた。
「バイクって、昼間の?白い髪で眼帯つけた、ちょっと恐そうなお兄さん?」
やはり年上だったのか、と、変なところで胸がざわつく。頷けば、盛大に笑い飛ばされた。
「チカちゃんは同じ委員会の先輩だよ。」
その先輩が何故さすけの家に来るのか…と問うよりも早く、さすけは上機嫌で説明を始めた。
「委員会ってのは文化祭実行委員でね、俺さまがお金の管理してんの。で、チカちゃんが備品を作るのに必要な道具があるとかで、俺さまに連絡が来たって訳。面倒だから明日にしろって言ったんだけど、それじゃ間に合わないだの今すぐ作りたいだのうるさいから、じゃあ迎えに来いって、…」
相変わらずよく回る口だ。一通り喋り終えたさすけは、「ほら、これが証拠。」と文化祭の計画表を取り出した。
文化祭本部スタッフの欄には、各学年の実行委員と、生徒会役員の名前が連なって書き記されている。
その中の妙に長ったらしい漢字ばかりの名前を示し、これが「チカちゃん」だと教えられた。
「明日お礼言っておかなっきゃ。」
「…何故だ?」
「だって、おかげで旦那に告白されたから。」
そう。色々なことがあって実感を持てずにいたが、俺はさすけに玉砕覚悟の告白をし、予想外の色よい返事を貰ったのだ。
再び抱きつかれて、かぁっと頬が熱くなる。
さすけは嬉しそうに笑い、真っ赤になっているであろう俺の頬に手をそえた。
「旦那、前も好きだって言ってくれたことあるでしょ?あの時は、ごまかしてゴメンね。」
覚えていたのか。さらりと流されたものだから、てっきり記憶にも残っていないのだと思っていた。
理由を問えば、さすけは眉を八の字にさせた。
「旦那の『好き』が、俺さまの『好き』と同じ意味なのか解んなかったんだもん。…ほら、旦那はまだ小学生だったでしょ?」
くらりと眩暈がした。やはり年齢だ。あの時も、たった一つの年の差が俺の邪魔をしていたのだ。
そのせいで三年間も悩み、足踏みをしていたのだと思うと、なんともやりきれない思いが沸き起こる。
「ほんと、ゴメン。」
溜息に何か勘違いをしたのか、さすけが謝罪を重ねる。
その申し訳なさそうな顔を見て、衝動的に細い体を抱きしめた。ついでに、添えられた手に強く頬を押し当てる。
我ながら甘えた動作だとは思うが、そうしたかったのだから仕方がない。
「…これから、よろしくね。」
「うむ。こちらこそ、よろしく頼む。」
こうして、俺の葛藤ばかりの日々にピリオドが打たれた。
「ねぇ、旦那。」
「うん?」
「部屋、本当に行かなくていーの?」
「!? は、破廉恥だぞ!さすけぇっ!!」
そうして、また新たな葛藤の日々が始まる。
END
[*前へ]
[#次へ]
戻る
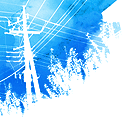
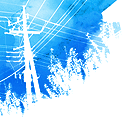
 幸村×佐助♀
幸村×佐助♀