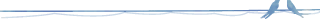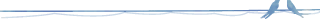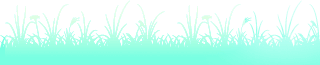政宗×佐助♀
政宗×佐助♀
2016.02.14 Sun 05:33
・2016年バレンタインネタ
・ですがVD当日ではありません
・伊達×佐助♀
・明確な女体化要素ほとんどなし
・既に恋人同士の二人
・少々変態くさいところあり
・チューあり
以上のことにご理解いただけましたら、本文へとお進み下さい。
『chocolate factory』
彼氏の分を差し置いて、真田の野郎のためのチョコを作るとは一体どういう了見だ。
上機嫌でキッチンに立つ猿飛の後ろ姿を見ながら、伊達は不満を隠さずに舌打ちをした。
去年はガトーショコラだ、その前はザッハトルテだ、更に言えば初めて作ったのはチョコクッキーだ、…。一体何が悲しくて、恋人が他の奴に送ったチョコレートの歴史を聞かされなければならないのか。
真田と猿飛の関係が家族みたいなもので、恋愛感情を抱いていないことは知っている。(真田に関しては、正直そうとも言い切れないのでは、と疑っているが。)
それでも、妬けるんだから仕方ない。
「政宗にもちゃんと作ってあげてるでしょ?」
なかったら流石に泣いている。
全身から発する不機嫌なオーラもなんのその。猿飛は鼻歌さえ歌いながら、丸めたチョコレートをココアパウダーの上で転がしている。
今年のバレンタインデーは、小さなチョコを何種類もたくさん作って、詰合せにして贈るらしい。
去年のガトーショコラよりも随分手軽じゃないかと密かに喜んだが、どうも事情があるようだった。
曰く、簡単に持ち運べて、手を汚さずに、どこでも気軽に食べられることが重要だとか。
「ほら、今年の十四日って日曜日じゃん?旦那、他校で部活の練習試合があるんだって。」
あぁ、そういうこと…
がっくりと肩を落とす伊達を気にも留めず(むしろ少し楽しそうでもある)、猿飛は一口サイズのチョコを作り続けている。
いい加減本気で面白くなくなってきた伊達は、小さな体に背後からのしかかり、作業の妨害を試みた。あわよくば、そのまま恋人同士らしい空気に持ち込もうという魂胆である。
しかし、例えお菓子作りだといっても、料理中の恋人は真剣そのもの。邪魔、と一声かけられたきり、こちらを振り向く気配もない。
いよいよもってつまらない。
だが、あまりしつこくして猿飛の堪忍袋の緒が切れることだけは避けたかった。なんせ、まだ自分の分のチョコレートは作られていないのだ。
彼女が丹精込めて作るバレンタインチョコレート。しかも、味は絶対の保証付き。
それを欲しくない男など、この世の中にいるものか。
「ねぇ、邪魔だってば。それに重い!」
「Ah〜…OK、邪魔をする気はねぇよ。」
本当は、あったのだけれど。
名残惜しくも体を離し、それでも折角一緒にいるのだからと、邪魔にならぬよう隣に立つ。
目の前には、チョコレートを作るための材料が、所狭しと並んでいた。
ひと口大だというチョコレートを、一体いくつ作るつもりなのか…。それが途方もない数であろうことは想像に難くないが、漏れる溜息を禁じ得ない。
湯煎にかけられたチョコレートだけでも、見ていて胸やけを起こしそうな量だ。
「…こんだけあったら、chocolate playも出来そうだな。」
小さな呟きの後には、静寂だけが返って来た。彼女の耳に入らなかった訳ではないことは、見上げて来た顔の、眉間に寄せられた深いしわが語っていた。
「なんでそんなバカなこと思いつくの」と、呆れているのと、憐れんでいるのとがごちゃ混ぜになったような、そんな顔だ。
もっとも、生憎と変な趣味は持っていないので、憐憫の眼で見られても興奮しないし、嬉しくもない。
ふん、と鼻を鳴らしてそっぽを向くと、どう解釈したのか、猿飛は大きなため息を吐いた。
白く細い指が、溶けた茶色の中につぷんと沈む。
ややあって静かに引き抜かれると、第二関節の辺りまで、チョコレートでコーティングされていた。
それが、すっと、伊達の口元に差し出される。
不思議なことに、部屋に満ちたチョコレートの匂いよりも、もっと、ずっと甘い香りが鼻孔をくすぐった。
「はい。これで我慢してよ。」
たれるから、早く。
促されて、今一度指を見つめて。実際にたれ始めたチョコレートをすくうように、根元から舌で舐め上げた。
先端までたどり着くと、次いで、ぱくりと口内に包み込む。爪の隙間に舌を這わせ、軽く吸うと、猿飛の体は小さくピクリと跳ねた。
「…っはい、おしまい!」
言うが早いか、指を引き抜いた猿飛は、素早く水道の蛇口をひねった。勢いよく流れる水の中に手を差し入れ、いくらか乱暴な仕草で手を洗っている。
後ろから覗く耳が真っ赤に染まっていることを、みすみす見逃す伊達ではない。
ココアパウダーの中に放置されたチョコの一つをつまみ上げると、口にくわえ、素早く猿飛の口に当てがった。
勿論、逃げられないように後頭部に手を添えることも忘れない。
驚きに目を白黒させている猿飛の顔は想像通りに赤くって、自然と口角が吊り上がる。少し力を込めて更に押し当てると、水に濡れた手とがっちり固定された頭では抵抗もままならないと悟ったか、実に悔しそうに、唇がゆっくりと開かれた。
待ってましたとばかりにチョコを押し込めば、必然、二人の唇は重なった。
角度を変え、唇をはみ、舌を絡め…。チョコを味わっているだけだ、なんて言い訳を胸中に呟きながら、執拗なほどに口内を蹂躙する。
時折口の端から逃れる熱っぽい吐息が、より一層気分を盛り立てて、行為を大胆にさせた。
頭に添えていた手も、いつしか、細い腰を抱いていた。
「っ、は…。」
ようやく唇が解放された頃には、息はすっかりあがり、乱れていた。瞳にはうっすらと水の膜が張っている。
くてん、と寄りかかって来る身体の愛しさに、伊達は上機嫌で己の唇を舐めとった。
「どうせなら、これくらいserviceしてくれよ。」
リップ音を立てて目元に唇を落とせば、力なく「ふざけんな」と暴言が返ってきた。
まったくもって可愛くない物言いなのに、可愛い、と思ってしまう自分はどこかおかしいのかもしれない。
「chocolate、少し甘すぎねぇか?」
「…だって、旦那は甘い方が好きだもん。」
あぁ、なるほど。確かにあいつはドがつく甘党だ。
再び首をもたげ始めた嫉妬の炎は、しかし、燃え上がる前に鎮火した。
「政宗の分だけだよ、甘さ控えめにしたの。…だって、ほら。彼氏に、一番喜んで貰いたいじゃん…?」
らしくないことを言っている、という照れが出て来たのか、最後の方は、消え入りそうな声だった。
それでもしっかりと全文を聞き取って、伊達は猿飛を強く抱きしめた。
今日日、ホワイトデーは三倍返しと聞く。
これは、随分と高くつきそうだ。
END
[*前へ]
[#次へ]
戻る
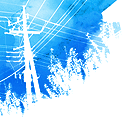
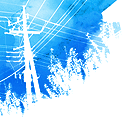
 政宗×佐助♀
政宗×佐助♀