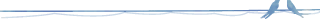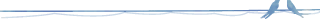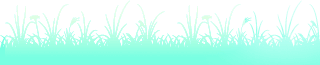元親×佐助♀
元親×佐助♀
2016.01.15 Fri 01:49
『気まぐれフリリク』にて頂いたリクエスト『元親×佐助♀』の消化作品です。
リクエストして下さった本人様のみ、お持ち帰り可能です。
(その際には、一言ご連絡をお願い致します。)
以下、注意事項
・元親×佐助♀
・名前は変わらず「さすけ」
・現代学生パロ
・苦学生佐助
・クリスマスネタ
・長くなりました…(反省)
以上のことにご理解いただけましたら、本文へとお進み下さい。
『ding-dong』
「おいおい、クリスマスもバイトなのか?」
それは恋人への非難ではなく、純粋な驚きをもった声だった。
振り向くと、元親が月の変わったばかりのカレンダーを指差している。自分からちゃんと伝えなくちゃ、と思っていたのに、言うより先に見つけられてしまった。
「うん、そう。ケーキ屋さんの臨時アルバイト。」
この時期が一番の繁忙期だと、ほとんどのケーキ屋が口を揃えて言う。とんでもない数の注文が入って、猫の手も借りたいほどの忙しさだというのに、(様々な理由から)人員の確保が難しいのだ。
商店街にあるその店でも、毎年クリスマスイブと当日の二日間、臨時のアルバイトを募集していた。時給は高め、更にケーキのおまけつきとなれば、さすけが飛びつかない訳がない。
けれども、今年は少々事情が違う。
それこそまさに、目の前の人物…恋人、と呼ばれる相手の存在だった。
付き合いこそ長いものの、それがいわゆる『恋人同士』と呼ばれる関係のものになったのは、今年の春のことだった。
恋人と一緒に迎える、初めてのクリスマス。
おおよその人が特別視するであろうその日に、相手に一言の断りもなく予定を入れてしまったのだ。大きく肩を落とす元親の背中を見れば、どうしたって罪悪感が込み上げる。
「ごめん、そもそもちゃんと相談するべきだった。」
「…ま、仕方ねぇさ。残念だけどよ。」
苦く笑った顔は、落胆を隠せていない。それでも、苦学生であるさすけの生活事情を知っている彼は、咎めも、怒りもしなかった。文句の一つも漏らさずに、さすけの頭を優しく撫でている。
立派な体躯に銀髪隻眼、と、一見誤解されやすい見た目をしているが、実は良識的で、人のことを思いやることが出来る優しいヤツなのだ。
「その代わり、初詣は一緒に行こうな。」
バイト、頑張って来いよ。
そんな言葉と共に額に唇を落とされては、頷くより他にない。
好きになったのが彼でよかった。
そんな照れ臭いことを思って、さすけは密かに頬を染めるのだった。
そして今一度、その気持ちを噛み締めることとなる。
十二月二十四日。アルバイトを終えて店を出ると、時刻は夜の九時を回っていた。雪こそ降っていないが、冷え込みは厳しく、店内との温度差にぶるりと体が震えた。
さっさと家で温まりたい。そんな一心から、表通りを目指して店の横の通路を足早に進む。本来は裏口に面した路地から帰った方が近いのだが、なにかと物騒だから人通りの多い表通りを使うようにと、元親から口をすっぱくして言われていた。
少し過保護じゃないかと呆れもしたが、「彼女の心配をして悪ぃかよ」と拗ねる横顔に、けして悪い気はしなかったのを覚えている。
(彼氏の言いつけをきちんと守るなんて、俺様ってばほんと健気なオンナノコ。)
短い通路を抜けて表通りに出ると、ふと、視界の端で何かが動くのを捉えた。不思議に思って視線を巡らせると、暗闇の中に、店の前で佇む人影を見つけた。
閉店時間はとっくに過ぎ去り、シャッターも閉まっているというのに、その人影は時折時計に目を落としながら、店の方をしきりに気にしている。
(ケーキを買いそびれて、途方に暮れている…ってとこかな?)
しかし、残念ながら店の営業時間は終わっているし、今日用意していたケーキは完売済みだ。ケーキが欲しいのならば、ここでじっとしているより、コンビニを渡り歩いた方がよっぽど現実的だろう。それだって、急いだ方がいいに決まっている。
アルバイトとはいえ、今日一日さすけは店の従業員として働いている。一言声をかけるべきかと判断して近寄ると、足音に気が付いたのか、人影はこちらを振り返った。そして、暗がりから街灯の明かりの下へと出てきたのは…
「元親!?」
自分の、恋人だった。
「よお。遅かったな。」
左手を上げて朗らかに笑う彼は、寒さのせいか鼻先が赤くなっている。一体いつからここで待っていたのかと気を取られている内に、下ろされた左手がさすけの右手を握りしめた。
お互いに手袋しているのがちょっと残念…なんて、らしくないことを考えた頭を勢いよく左右に振る。
そんなことよりも、だ。
「なんでいるの?」
落ち合う約束をしていた訳ではないし、迎えに来るとも、待っているとも聞いていない。
「折角のクリスマスだし、やっぱ一緒にいてぇじゃねぇか。家まで送らせてくれや。」
そういうと、元親は返事も聞かずに手を引いて歩き出した。さすけも慌てて足を動かすも、中々隣に並べない。
いつもより歩調が速いからだと気が付いたのは、すぐのことだった。見上げた先にある顔はそっぽを向いていて、こちらを見ようとしない。
(元親、照れてる…?)
耳が赤いのも、きっと寒さのせいだけではないだろう。
「…かーわいい。」
小さく漏れた笑い声に、彼の耳は赤さを増した。
「そういや、ケーキは持ってねぇのか?」
「ケーキ?」
他愛無い会話が途切れた時、不意に疑問を投げかけられた。そういえば、先日『ケーキがもらえるから一緒に食べよう』と約束を交わしたことを思い出す。
けれど、今さすけが持っている荷物は背負ったカバン一つのみ。勿論、そんな不安定なところにケーキが入っている訳もない。
「ケーキが貰えるのは、二十五日の夜だよ。」
二日間きっちりと働いて、最終日にご褒美とバイト代を貰うことになっている。
元親は「そうか」とだけ呟くと、視線を空に移した。珍しく満月の浮かんだクリスマスイブは、それだけでやけにロマンチックに映る。
しかし、空を見上げられると、さすけの身長では彼の顔が見えなくなってしまう。それが少しだけ不満で、さすけは肩で元親の体を押した。
(こっち見てよ。)
願いながらも、それを悟られるのは恥ずかしく、すぐに軽口を重ねる。
「もしかして、今日のお迎えってケーキ目当てだった?無くてがっかり?」
からかいの言葉に、思惑通り元親の視線が戻って来る。もし今の言葉が図星であったならば、きっと、さぞかし面白い表情が見られることだろう。
さてどうかと顔を覗き込めば、予想と反して、彼は楽しそうに笑っていた。
至近距離で不意に見せられた笑顔に、心臓が大きく跳ねあがる。
「がっかりなんざしてねぇさ。明日、迎えにいく理由が出来たからな。」
…ちくしょう、元親のくせに。
(かっこよくって、むかつく。)
熱くなった顔をうつむかせるも、隠すのが少し遅かったらしい。繋いでいた手を強く引っ張られ、気付いた時には元親の腕の中にすっぽりとおさまっていた。
体格も腕力も、到底適わない相手だ。大きな体でぎゅうぎゅうと抱きしめられては、抵抗一つ出来やしない。突っ張ってどうにか距離を開けようと試みた両腕も、少しも伸ばすことが出来ず、手のひらを相手の胸に添えるだけに終わった。
「ちょっと、恥ずかしいでしょ!」
唯一自由になる口で訴えると、腕の拘束は僅かに緩み、手は背中から腰へと移動した。
密着した状態から解放され、ほっと息をついたのも束の間。腰に回った腕に再び力が込められて、さすけの踵が少しだけ浮き上がった。
この態勢には、覚えがある。
顔を上げると、隻眼と視線がぶつかった。
緩く弧を描いた唇が、ゆっくりと近付いて…。
「や、やだってば!」
咄嗟に突きだした右手は、偶然にも元親の顎を的確に捉えていた。下降していた首を強引に上向かせられて、ぐえ、と、潰れたカエルのような声が漏れる。
その隙を見逃さずに、さすけはするりと腕の中かから抜け出した。
打たれた顎をさする元親は、痛みのせいか、予期せぬ乱暴な『おあずけ』のせいか、目に涙を浮かべている。
「〜どこも似たような奴らでいっぱいだしよォ。ちょっとぐらい良いじゃねぇか。」
どうせ誰も気にしちゃいねぇ、と言われても、当の本人が気になるのだから仕方ない。それでも嫌だときっぱり告げると、元親は肩をすくめて白い息を吐き出した。
あっさりと、諦めてくれたらしい。
「悪かったよ。…ほら、行くぞ。」
差し出された手に己の手のひらを重ね、「うん」と上機嫌に笑ってみせる。
本気で嫌がることは、けして無理強いしない男だと知っていた。
知っていて、さすけはそれに甘えている。
だからこそ、彼女もまた相手を甘やかしたくなるのだった。
「どうせくっつくなら、家に帰ってからにしない?」
控えめな上目遣いは、相手から自分がどう見えるかを、ちょっとだけ意識した。
イタズラっぽく笑って見せた顔に、元親は一瞬目を丸くさせ、しかしすぐにニヤリと口角を吊り上げた。
「言ったな?」
手を引いて走り出した元親に、さすけも遅れず走り出す。
楽しいのと嬉しいのがごっちゃになったような高揚感に、口元は自然と笑みを作っていた。
道すがら。家にクリスマスのご馳走が何もないことを思い出す。
コンビニでも寄って行く?と問いかけたら、お前がいればいいと返された。
END
[*前へ]
[#次へ]
戻る
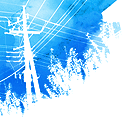
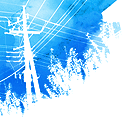
 元親×佐助♀
元親×佐助♀