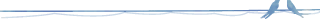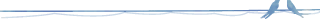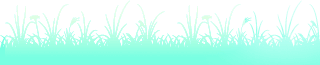☆妖怪パロ(織田夫妻)
☆妖怪パロ(織田夫妻)
2021.07.26 Mon 14:31
妖怪好きだし、夏だし、ホラー書きたい…との思いから生まれたSS。
・妖怪パロ
・ホラーもどき
・織田軍が人外
・モブ(男)視点
・出番配分は、濃姫がっつり、信長ちょっと、蘭丸匂わせ程度
詳細の設定は練っていませんので、説明の足りない個所は各々脳内補完をお願いいたします。
以上のことにご理解いただけましたら、本文へとお進みください。
『夜の蜘蛛は』
静かな山間部。日はとっくに落ちて、聞こえてくるのは近くの田畑にいる虫や牛蛙の鳴き声のみ。街灯も少ない道ではあるが、空にはぽっかりと穴の空いたような満月が浮かんでおり、幸い、十分な月明かりが落ちていた。
けれども、夏も近いこの季節。樹木は青々と葉を茂らせている。道幅が狭まれば、道の両脇で生い茂った木々が、その枝葉で空を覆い隠した。
月光が遮られただけだというのに、途端に、辺りは暗闇に包まれる。細道は八十メートルほども続いており、帰宅するべき家は、その更に先。幼い頃に何度も通った道ではあるが、進学を機に地元を離れて以来久しく、それも夜半ともなれば郷愁よりも多少の薄気味悪さ…正直に言えば、暗闇に対する純粋な恐怖が胸に去来する。
せめて少しでも明かりを、とスマホを取り出すも、充電が少ないことに気が付いてライトの点灯は断念した。(もし家人が玄関を施錠して寝ていたら、電話をかけて起こさなければならないからだ。)
グゥ、グゥと鳴く牛蛙の声が、自分の足音が近付くとしんとなり、しばらく歩くと、背後でまた聞こえ出す。こんな田舎なのに、しっかりと人を警戒しているのがなんだか意外で滑稽に思えた。
暗い道をしばらく進むと、ちょうど木漏れ日のように月光が葉の隙間から差し込んでいる場所があった。微かとはいえ、明かりがあるとホッとする。気が緩んだその瞬間、奥に続く暗闇の中を見て息を飲んだ。
人影だ。
誰かが道端にしゃがみ込んでいる。大きな道路から外れ、街灯もない、周りに家屋も少ない小さな細道で、こんな夜半に。
息を詰め、じっと暗闇に目を凝らす。
幽霊は怖い。が、生きている人間…酔っ払いや変質者だったら、もっと怖い。
視線に気が付いたのか、人影がこちらを振り向いた。すらりと立ち上がる動作を見るに、少なくとも泥酔はしていなさそうだ。
闇に浮かぶシルエットは、明らかに女性のもの。着物を着ており、二本の足もある。
不思議と、相手が女性というだけで警戒心はいくらか薄くなった。幽霊でなければ尚更だ。
彼女は暗闇の中から歩き出て、月光の下へと姿をさらした。
「ごめんなさい。道に迷ってしまったのだけど…。」
グゥ、グゥと蛙の声がうるさい中で、鈴を転がしたような声は際立って聞こえた。
見た目も良けりゃ、声も良い。低俗だが、率直な、素直な感想はそれだった。都会でもなかなかお目にかかれないレベルの、とんでもなく綺麗な人だ。少しきつめな美人顔。紅いアイメイクがよく似合っており、結い上げた日本髪の、うなじの白さが目に眩しい。
(なんでこんな綺麗な人がこんなド田舎に…?嫁いできたのか?)
興味も疑問も尽きないけれど、口はすべてを飲み込んで、「大丈夫、ご案内しますよ。」などと、紳士ぶって笑みさえ浮かべて見せたのだった。
彼女は、自身を『帰蝶』と名乗った。着物の柄も相まって、蝶のように華麗で美しい彼女には似合いの名だ。
もっとも、変わった響きのそれが本名かどうかは甚だ疑問である。もしかしたら有名人で、芸名かもしれない、と、後でググろうと秘かに心にとめた。
「へぇ、ご両親がこちらへ引っ越しを?」
「えぇ。田舎暮らしに憧れて、この春に。今回初めて訪ねたのだけど、この有様よ。」
確かに、昨今はスローライフだなんだと田舎暮らしが注目されつつある。この土地の出身者としては、高齢者や都会に慣れた若者が暮らすには不便すぎやしないかと思うのだが、それもまた魅力となるらしい。つくづく、世の中何がウケるか分からない。
(あっ)
並んで歩く白魚のような手が、己の手に触れる。何度目かのそれは、去り際にするりと手の甲を撫でて離れていった。
触れる回数の多さに、偶然ではなく故意ではないかと疑ってはいたが、これはもう決定的だ。
ちらりと視線を向ければ、こちらを見上げる瞳と、大きく開いた胸元が目に入る。無意識にごくりとつばを飲み込んで、喉の渇きを自覚した。その間も、無防備にさらされたなだらかな二つの曲線の、豊満な胸の谷間から目が離せないでいる。
彼女は露骨な視線を嫌がる素振りもなく、蠱惑な笑みを浮かべてみせた。紅い舌の先が、唇の端からちらりと覗いている。
これは、据え膳だ。誘われているに違いない。
距離を詰め、手を腰へ回そうとした。
その時、ふと。
虫の声が聞こえないことに気が付いた。
些細なことである。けれども、ここで生まれ育った者としては、大きな大きな違和感だった。虫の声はしないのに、牛蛙の声は絶えず聞こえ続けているのも、違和感の一因だ。
思い返せば、先ほど帰蝶が暗がりから出てきた時も、蛙はずっと鳴いていた。
彼女の歩みに合わせて、鳴くのを止めた蛙は一匹もいなかったのだ。
一瞬にして、ぞわりと肌が粟立った。
昔、亡くなった祖母から牛鬼という人食い妖怪の伝承を聞いたことがある。牛鬼は美しい女と行動を共にしており、その女の色香に誘われてのこのこやってきた男どもを、頭からバリバリと食い尽くすのだと言う。
今、目の前にいる彼女は、本当に人間なのだろうか?触れられるから、幽霊ではないだろう。では、なんだ。化け物か。この美しさは、人を惑わし、騙すための撒き餌なのか。
「どうかしたの?坊や。」
優しい声。色香もある。
それが、今はただただ恐ろしい。
身を引こうとすると、するりと腕をからめとられた。逃がさない、と言われた気がした。彼女を華麗な蝶だと例えた己の認識を、今は改めざるを得ない。
蝶ではない。蜘蛛だ。毒々しいほどに色鮮やかな、女郎蜘蛛。
…同名の妖怪が、昔見たアニメに出てきた。あれもやはり、若く綺麗な女の姿をしていた。妖怪退治をしてくれる妖怪が主人公の物語だったので、最後は襲われている人間を主人公が助けに来てくれてハッピーエンド。
でも、結局アニメの話である。今、自分を助けに来てくれる主人公はどこにもいない。
(俺は、どうなる?)
緊張と恐怖で喉が渇く。
生憎と飲み物は持っていない。せめて、ガムか飴でも持ち合わせていなかっただろうか。もしくは、今、この状況を切り抜けられる何かがあったりはしないだろうか。
化け物は煙草の煙が苦手、というのが定番だが、生憎と自分自身が嫌煙家である。藁にもすがる思いでポケットを探れば、指先に覚えのないビニールの感触が触れた。何かと取り出したそれは、色とりどりの…
「金平糖…。」
「金平糖?」
「えっ、あ、はい、金平糖…そう、友人がくれて…っ」
しどろもどろな口調の代わりに、ブンブンと必死に首を縦に振って肯定する。
酔っ払った友人が、何故かカバンから取り出した金平糖を投げてよこしてきたのだ。何一つ道理も理由もわからぬ行動であったが、酔っていたのはお互い様。笑って受け取って、そのままポケットに突っ込んだことを思い出す。
こんなもの、何の助けにもなりゃしない…と肩を落としたのも束の間。横から注がれる視線は、ずっと金平糖に向けられていた。
そのあまりの熱心さに、一抹の望みをかけてみようという気になった。駄目で元々、他に策も何もない。
「い…いります、か…?」
「あら…いいの?」
「は、はい。」
どうぞ、と恐る恐る差し出すと、腕に絡んでいた手がほどかれた。彼女は両手で包むようにそっと金平糖を受け取ると、口元を優しくほころばせた。きつく見えた涼しげな目元も、今は柔らかく形を変えている。
ふふっと笑う姿の華やかさに、恐怖も忘れて目を奪われた。
「ありがとう。あの子、喜ぶわ。」
慈母のような笑みにぼうっと見惚れているうちに、「ここでいいわ。ありがとうね、ぼうや。」と、彼女は足取り軽く闇へと消えていった。
呆然と、どれだけの時を立ち尽くしていたか。いつからか、辺りから虫の声が聞こえていることに気が付いた。
「ッ、は〜…!」
大きな、大きなため息を吐き出した。恐怖と緊張から解放された、安堵のため息だ。
まさかあんな小さな金平糖が、お助けアイテムになるとは思わなかった。世の中、本当に何が起こるか分からない。
「綺麗な人だったな…。」
結果論、とでも言うのか。無事だったからこその心境なのだろうが、空気が緩むと、とたんに気が大きくなる。
妖怪だの化け物だのは、酔いと恐怖が作り出した自分の馬鹿な妄想で、彼女は本当にただの人だったのではないか。そんな考えが首をもたげて、ともすれば、「惜しいことをした」などと悔やむ卑しさも顔を出す。
熱い視線でこちらを見上げ、腕まで絡めてきた彼女は乗り気だったに違いない。一夜限りの楽しい火遊びが出来たはずなのに、自ら棒に振ってしまったのだ。
イイ女だったのに、勿体ないことをしてしまった。顔も、声も、身体も一級品。抱いたらどんな具合だっただろうか。
ニヤニヤと妄想に浸っていたせいで、虫の音が再び止んでいることに気が付けなかった。
そして、
『グルワァ』と。
すぐ近くで、ひと際大きな蛙の鳴き声がした。
いや、近くどころではない。耳の、すぐ、後ろだ。
思わず後ろを振り返る。けれど、そこには何の姿も見えない。姿どころか、虫の声も、蛙の声さえも止んでいた。
どっと、全身から汗が噴き出した。
耳に残る異様な声音。あれはもはや牛蛙というよりも、牛そのもの…いや、牛より、もっと大きな生き物のような鳴き声だった。
地の底から響いてくるような、獣の、唸り声。
『是非もなし…消えろォ…』
次いで聞こえたくぐもった声に、たまらず全力で駆け出した。
家は、もう視認できる距離にある。すぐそこだ。
そう、すぐそこなのだ。
家の、こんな近くに、得体のしれない何かがいるのだ。
『消えろォ』、と、先ほどの声が何度も何度も頭の中で繰り返される。
苛立ちを孕んだ、呪詛めいた声。圧倒的な強者の声。
安全な屋内に逃げ込める安心感と、扉一枚隔てた屋外に危険がある恐怖。せめぎ合う感情に、せめて戸締りをしっかりすること、そして、年老いた両親を都会に呼ぶことを心に決めた。
二度目の邂逅など御免被りたいが。もし、そんなことがあったとして。
その時、また見逃してもらえるとは限らないのだから。
END
[*前へ]
[#次へ]
戻る
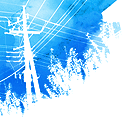
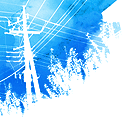
 ☆妖怪パロ(織田夫妻)
☆妖怪パロ(織田夫妻)