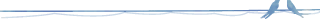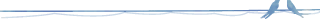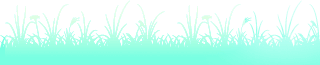天変地異(幸佐)
天変地異(幸佐)
2019.11.09 Sat 11:57
・幸村×佐助
・現代パロ
・風邪ネタ
・武田軍三人一つ屋根の下で暮らしています
・真田主従は高校生、佐助が一つ年上くらいのイメージ
・CP要素は薄め
以上のことにご理解いただけましたら、本文へとお進
み下さい。
「天変地異」
季節の変わり目ってのは、天候が不安定で体調を崩しやすいものだ。
突然の雨。冷たい風。夕飯の買い出しの帰り道に見舞われた不運に、幸村は雨宿りではなく走って帰ることを選択した。
手に下げたビニール袋の中には、商店街の精肉店で買った肉の塊が入っている。家では佐助が夕食の準備を進めていることだろう。早いところこれを調理してもらいたかった。
持ち合わせた調理の知識は決して豊富ではないが、長く煮込めば美味しくなることを知っている。
少しでも煮込む時間を長く!少しでも肉を美味しく!そんな気持ちからの判断だった。
かくして、それは凶と出た。
風呂には、同じく帰宅途中に雨に打たれたという信玄が既に入って体を温めていた。聞こえ漏れてくる上機嫌な鼻歌に、ずいぶんとリラックスしていることが知れる。
邪魔をする訳にはいかない、と、幸村はそっと廊下へ引き返した。
タオルで雨の水分をふき取り、…けれども着替えることはせず、信玄が風呂から上がってくるのを静かに待った。
信玄は幸村が濡れて帰ってきたことを知らなかったし、佐助は幸村が信玄と一緒に風呂に入っているものだと思っていた。
そうして、幸村は風邪をひいたのだ。
「あーもーお馬鹿さん。ほんっとお馬鹿さん!」
風呂から上がった信玄の驚愕の雄叫びで、濡れネズミは発見された。すぐさま風呂場へと押し込まれ充分に体を温めたが、湯上り直後から寒気を感じていた。明らかな風邪の前兆である。
しかし、普段風邪など無縁である幸村は、その違和感を無視してしまった。何かがおかしいと思うものの、経験値の少なさから風邪とは気が付かなかったのだ。なんだか寒い。雨に濡れたからだろうか。身体を動かせば温まるだろう、と、寝る前に汗をかくという愚行さえ犯した。
そして、翌朝。佐助が叫んだ言葉が先ほどのそれである。
ズビ、と鼻をすする音がその言葉尻に重なる。
「不覚…っ!」
「いや不覚じゃなくって…。」
呆れた声は、途中から何もかもを諦めた重い溜息に変わった。手元へ帰ってきた電子体温計は、三十九度という数字を示している。平熱そのものが高そうではあるが、それにしたって高熱だ。
今日が学校が休みで良かったと、佐助は秘かに胸をなでおろす。幸村が皆勤賞狙いであることは誰もが知っている。これが平日であったなら、学校を休むよう説得せねばならなかっただろう。しかも、信玄は仕事で朝早くから家を出ている。自分一人で説得するだなんて骨の折れる作業、想像するだけでげんなりしてしまう。
「…で、どう?ご飯は食べれそう?」
問いかけに、幸村は腹を抑えて首を傾げた。そういえば空腹を感じていない。なんとも慣れない感覚だ。…が、食べれないという訳でもないだろう。
もっとも、初めから彼の中で答えは一択であった。食べる、と告げるために顔を上げるも、勢いが良すぎたのかグラリと視界が揺れた。慌てて腕が伸びてきて、再び布団へ戻される。
「あーもー危ないから急に動かない!ほら、ちゃんと寝てて。…ご飯、たまご粥でいいね?」
言わずとも悟るとは、流石は佐助だ。満足げに頷けば、額にぺちんと冷却シートを張り付けられた。わざと、ちょっと痛くされた気がする。
「すぐ用意するから、寝ちゃわないでね?でも、くれぐれも布団からは出ないこと!」
きっちりと念を押して、佐助はキッチンへと消えていった。
(風邪、か…。)
滅多にひかないから、そうそうありつけないたまご粥が楽しみだ。不謹慎ながら、ふふ、と小さな笑いが漏れた。
「…」
目玉が、熱い。
熱があるせいだろうか。ぼんやりとした頭で考えるも、その思考すらよくまとまらない。朝起きた時はもう少し余裕があったのだが、時間が経つごとにどうも体がだるくなってきている。
慣れぬ熱に、体が参りだしたのだろうか。はたまた熱が上がっているのか。そもそも風邪と言うものの症状が正しくこれなのか…。最後に風邪をひいた時の記憶は、もはや脳の片隅にも残っていない。
「はいは〜い、お待たせ〜」
いつも通りの間延びした声が聞こえ、お盆を持った佐助が戻ってきた。盆の上では、湯気の立ったお粥と、水、市販の風邪薬が乗っている。ふわりと優しい香りが漂った。
佐助は幸村に目を向けると、先刻よりも不調が明らかな姿にぎゅっと眉間にしわを寄せた。
「…本当に食べれる?」
薬を飲むのに、少しでも口に入れた方がいいんだけど…と、問いかける声は遠慮がちだ。幸村の慣れぬ風邪に戸惑っていたのは、本人だけではなかったらしい。
不安と心配をないまぜにした表情に、幸村は慌てて体を起こした。再び揺れた視界には、気付かないふりをして気力で無視を決め込む。
「もちろん!」
さあ寄越せ!とばかりに両手を伸ばせば、長い溜息が返ってきた。それでも、少しだけ雰囲気は明るくなったような気がする。無理しないでね、という言葉と共にお盆ごとお粥が渡された。
思えば、寝具の中で飲食をするのも初めてだ。風邪をひくと随分と特別があるのだな、と、しみじみ思う。
手を合わせ、いただきます、と頭を下げる。
…余談ではあるが、「あーん」をして貰おうと言う考えは微塵も存在していない。幼い頃から一緒に育ち、普段から二人の距離が近いこと、互いに甘え上手と甘えさせ上手であること。そんな事情から、「あーん」は、彼らにとって最早日常の一部だった。
勿論、幸村が望めば佐助は応じてくれるだろうが、「風邪を移してはいけない」という思いが強い。はなからその気はないのである。
そんな訳で、自分の手でレンゲを取り、掬った一口分を軽く冷ましてから口に運んだ。食べやすい、優しい味だ。ふわりと鼻に抜ける香りが、躊躇わず二口目を掬いあげさせる。それがどのようにして作られたかなど、幸村には想像にも及ばないが、色々と気を使って技巧を凝らしてくれたのだろうと知れた。
料理は愛情、とはうまいことを言うものだ。まさにその通りだと、一口一口を噛み締める。
「凄く美味い。それに食べやすい。礼を言うぞ、佐助。」
ありがとう、と笑う幸村に、佐助もようやく心からの笑みを見せたのだった。
ついたため息は、苦しみではなく充足感からもたらされたものだった。胃の辺りがほのかに温かく、腹八分目の満腹感に満たされている。
薬を水で流し込み、一息つけば、自然と大きなあくびが飛び出した。
幼い頃に「食べてすぐ寝たら牛になる」などと、からかわれながら注意されたことを思い出す。必死に眠気に抗っていると、察したらしい佐助から「風邪の時は寝てもいいんだよ」と笑われる。
「むしろ、寝てしっかりと体を休ませないと。」
「む…そういうものか?」
「そーいうもの。」
言い終わるや否や、背に手を添えられて布団に寝かされた。顎の下まで布団を引き上げられて、と、至れり尽くせりである。まるで幼子への対応だと気恥ずかしくもあったが、…やはり慣れぬ風邪で弱気になっているのか、甘んじて受け入れた。
ぽん、ぽん、と布団の上から一定のリズムで叩かれて、ますます瞼が重くなる。
「必要そうなものはここに置いてくね。あと、ちょこちょこ様子見に来るから。」
言いながら、体温計、スポーツ飲料、額に貼る冷却シートなどが幸村の手の届く範囲に陳列される。換気していた窓を閉め、少し考えてから、窓の半面だけをカーテンで隠した。ほのかに差し込む日光は温かく、けれども眠気を邪魔するほどに眩しくはない。
まどろむ幸村の意識は、ずるずると眠りに引っ張られていく。
「あと、何か欲しいものがあったら言ってね。」
食器を乗せた盆を持って立ち上がると、幸村の瞳が開き、その姿を追いかけた。視線に気付いて動きを止めた佐助に、眠たげな声がかけられる。
「佐助…」
「あらら、早速?はいはい、何が入用ですか?」
幸村のことだから、「甘いものが欲しい」などとねだられるだろうか。そう当たりをつけ、あとで備蓄の桃缶でも開けてやろうと考える。体調次第ではバニラアイスを添えてもいいだろう。
「佐助。」
「はいはーい。聞こえてますよ。」
答えるも、返ってくる言葉はない。早くも寝ぼけているのだろうか、と疑問に思ってベッドに近付くも、両目はしっかりと佐助を見つめていた。ただ、熱のせいか、眠気のせいか、その目にいつもの覇気は感じられない。
念のために己の額と幸村の頬(額には冷却シートが貼ってあるためだ)に手を当てて体温を比べてみたが、先ほどよりも熱が上がっているという訳でもなさそうだった。
「佐助。」と、またもや名前を呼ばれたので、頭を撫でてやりながら返事を繰り返す。すると、布団の中から力なく手が伸ばされた。
「…お主が、必要だと言っている…。」
驚きに丸まった双眸の先で、幸村の手がちょいちょいと小さく手招きをしている。佐助は、え、え、と小さく戸惑いの声をあげながら、幸村の顔と手を交互に見やった。
彼の眼差しは真剣で、手はずっと同じ動作を続けている。
(手を握れば、いい…の、かな?)
お盆を脇に置き、伸ばされた手をおずおずと両手で包み込めば、幸村は安心した子供のようにふにゃりと笑った。
そして、そのまま目が閉じられる。
幾度も名前を呼ばれたのは、用件を伝えるためではなく、呼んだその名こそが、まさに「必要なもの」そのものだったのである。
しばらくそのまま見守っていると、やがて小さな寝息が聞こえてきた。寝顔は、変わらず穏やかなままだ。
「…えっ。えぇ…っ!」
遅れて動揺がやって来る。
(なんだこれ、なんだこれ!なんだこの可愛いの!嘘だろ、俺様この手どうしたらいいんだよ!!)
しかし、眠る幸村のそばで騒ぎ立てる訳にはいかない。もはや彼の性分とでもいうべきか。パニックは表に出ることなく、佐助の心の内でだけ爆発している。
落ち着くために長く深い深呼吸をしてみるも、高鳴った胸の鼓動はそう簡単には静まりそうもない。まいったな、と小さく独り言ちる。
こんな甘え方をされたら、照れてしまう。
もっと甘やかしたくなってしまう。
もっと、好きになってしまう。
情けなく崩れた表情を隠すように、空いた片手で己の顔を覆った。
触れた頬のあまりの熱さに、ますます恥ずかしさは募るのだった。
END
[*前へ]
[#次へ]
戻る
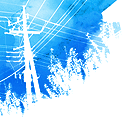
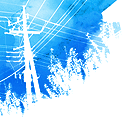
 天変地異(幸佐)
天変地異(幸佐)