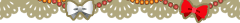
一護の言葉とルキアの思考が、重なった。
顔を隠すことも忘れて、ルキアはまじまじと一護を見上げた。
彼の顔が、自分と同じか、―――それ以上に紅くなっている事に、この時初めて気が付いた。
何か見てはならないモノを見てしまった様な気分になり、ガバッと俯き視線を外す。
思わず息を止めていた事もあって、息が上がる。
理由がそれだけではないとも分かっているが、脈だって異常に早い。
心の臓が破裂しそうだと、思う。
だが―――目の前の一護の心臓も、同じくらいの速さで動いていた。
―――どれくらいそうしていただろうか。
不意に、ルキアの後頭部を押さえていた一護の右手が離れ、ルキアの左腕を掴んだ、と思ったら。
ひょいっと軽々とルキアの身体が宙に浮き、くるっと反転しながら着地した。
一護の左手はずっとルキアの右肩を掴んだままだったので、ルキアは一護の腕の中で、左手一本で拘束されている。
護挺の副隊長としてはあるイミ屈辱的な体勢であったが、―――それどころでは無かった。
いきなり目の前に広がった光景に、気を取られ、動けなかった。
今のルキアの眼前に現れたそれは。
『黒崎家之墓』
の墓石だった。
……つまりは、一護の母親たる真咲の墓前で、あの恥ずかしいやりとりを交わしていた訳で。
その事をルキアはすっかり失念していた。
わなわなと口元を震わせるルキアの背後から、一護はゆっくりと声を発した。
「ん。とりあえず、今日は帰るよ、おふくろ。また、こいつつれて、今度はゆっくり、来るから、さ」
そしてそのまま、水桶を右手に、左手でルキアの右手をしっかりと握った一護はさっさとその場を後にした。
「……一護!?」
「……何だよ?」
色々と言いたいことは在るのだが、最優先はまずこれだった。
「もうちょっと、ゆっくり歩くか、手を放してくれぬか?」
まず二人の歩幅からして違うのだから、ルキアには競歩どころか小走りになっている。
ルキアの訴えに、あっさりペースが落ちる。
が、その手が離されることは無い。
「まったく、貴様は!!さっきから勝手な事ばかり言いおって!」
「……?そうか?」
「そうだ!さ、さ、さっきだって!!」
「さっき?」
「ま、また私を真咲殿の所に連れて行くとか!」
「…来てくれないのか?」
「い、いや、そういう訳では、無いが。……そ、その前の、ぷ、ぷ、ぷろぽおずとやらみたいな事だって…っ!」
「ああ、あれ」
何でも無い様な事の様に言われて、ルキアの怒りは頂点へと駈け上る。
「問題ないだろ?お前、あんだけ待っても否定も断る事もしなかったんだし……」
「……へ?」
あの沈黙は、返事を待っていたのか?と、破裂寸前だった怒りの風船がぷしゅうと萎む。
一護が足を止め、ルキアもそれに倣う。
水桶を地面に置いて、ルキアと向かい合うと、きょろきょろと辺りを見回し、他の人の気配がない事を確認して、一護はルキアの左手を取って両手にぎゅっと力を込めた。
「俺、お前がいいんだ。お前が好きだ。―――ずっと、本当は好きだったんだ、な」
ルキアは、この一言で思考を放棄した。
「だから、きっとあんなにあっさり言葉が出てきたんだって思うんだよ」
そういって、また水桶を手に、一護は歩き出した。
ニカッと笑って振り向いたその表情は、……ルキアが知らなかった笑顔だった。
―――彼は今日成人式とやらで、大人になったはずだったのに。
今まで見た中で、一番幼い―――でも一番嬉しそうな顔だった。
その笑顔に、ルキアの頭は真っ白になったのだから。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
ふと気づけば、一護の右手には借りていた水桶はとうに無く、辺りの景色も見覚え有る物に変わっており、ルキアは慌てた。
「い、一護……?」
「ん?もうすぐだぞ?」
「へ?すぐとは、何処へだ?」
「取り敢えずは、浦原商店。偽骸が無いとこっちで生活できないだろ?」
ルキアが半ば意識を飛ばしていた間に、一護の中では何やら予定が組まれてしまったらしい。
「ちょ、ちょっと待て一護!!」
「待たない」
「一護!!」
「―――待てない」
「!!」
あまりに正直な言葉に、絶句する間にも、店に一歩ずつ近づいていく。
声をかけても、その足取りは止まらない。
何を言えば一護が止まってくれるのかと、未だ混乱の最中に居るルキアは、―――咄嗟に叫んだ。
「き、貴様、さっき『二十六になったら』って言ったではないか!!」
その言葉に、一護はピタッと止まって、ルキアを振り返った。
―――つい今の今まで、ルキアは一護の(無意識の)求婚に、返事をしていなかった。
しかし今の発言は、裏を返せば、『二十六になったら』という条件を返したのと同義である。
後頭部に手をやり、一護は何やら考え始める。
ルキアはと言えば、ひとまず一護が止まってくれた事にホッとして、膝に手を当て大きく息を吐き出した。
自分の発言には、気づいていない。
「ん、よしっ!」
「!っ、な、何だ?!」
ルキアの警戒レベルは既に最大値を振り切っている。
しかし、それをあっさりと崩して乗り越えてしまうのが、この男。
黒崎一護である。
「わかった、今日の所は、今すぐってのは諦める」
「っ!本当か一護?」
二人の未来をあきらめるとは一言も言ってないのに、ルキアはホッと息を吐いた。
その油断した一瞬に、今日最大の爆弾は連続投下される。
「本当は、このまま惚れた女を返すのは癪なんだけど、我慢するさ。また今度そっち行くから、根回ししとけよ?」
「――――――は?え?ほ、ほ、ほ、ほっ?惚れっ?え?ね、根回し?」
どもり倒しているルキアだったが、一番分からなかったのはその根回しで。
「決まってんだろ?せっかくお前がプロポーズ受けてくれたのに、そっちの上に話通さなきゃ二十六になってもこっち来れないだろ?」
お前がしないんなら、俺今から即刻乗り込んでくけど、それでも良いぞ?
――――――恐ろしいセリフに、ルキアはぶんぶんと首を振って拒否した。
それでも、ちゃんとしとけよ、と三度念押しされた。
最期にギュッと抱きしめられて、離れる間際に自分を見つめる一護と目が合った。
その眼差しからは、ルキアへと向ける愛情が恋情がタダ漏れで。
呆けた頭で、目は口ほどにってこういう事を言うのかと考えた。
黒崎一護は、やっぱり『あの』黒崎一心の息子なんだなと、妙な実感も伴って。
じゃあ、またなと浦原商店への分かれ道で、一護は背を向け帰宅していった。
―――その背が見えなくなって、暫くしてから。
ルキアはぺたんとその場にへたり込んだ。
怒涛の展開に着いていけずに腰を抜かしたのだった。
そのまま、一護の言っていた事を物凄い羞恥心と戦いながら思い返せば、反論出来なくなっていた。
確かに、ルキアの中に拒否や断るという考えは、浮かんではこなかった。
そんな行動に移る筈も無かった。
そんな自分に気付いて、まず途方にくれた。
そして、暫く会わずにいる内に、一護の発言はパワーアップしていた。
昔なら、初めて会った頃は、照れが勝っていたというのに。
その後は何度かルキアの心臓に悪い発言も多々していたが。
何が心臓に悪いかといえば、内容もだが、それが無意識に漏れ出る一護の本音だという点だった。
しかしこれほどでは無かったはずなのに。
「もしかして、―――自覚したから、タガが外れた、のか?」
それとも、こうして自分の気持ちを素直に出せる様になった事が、―――大人になったという事だろうかとルキアは真っ赤な顔のまま、何かに震える身体を抱き締めて、―――天を仰いだ。
未だ途方に暮れるルキアは気づかない。
帰宅途中の一護が、今月がルキアの誕生月だと思いだし、虫よけ変わりの意味も込めて何かを用意しようと考えている事も。
そのルキアを、塀の上から通りかかった黒猫が訝しげに見詰めている事にも。
波乱はまだまだ続きそうだった。
―――――――――――――――
橙紫黒白のすみしょん様に捧げます。
相互リンク記念という事で、お互いリクエストしあいました。
『無自覚天然激鈍一護の自覚編』
……自覚と同時にエライ事もしでかしてますけどね(汗)。
まさかまたプロポーズになるなんか、予定に無かったのですが。
たつき・織姫に厳しくなってしまいました。
いや、たつきは可哀想か(汗)。
すみしょん様のみ、お持ち帰り下さい。
相互リンク、ありがとうございます。
これからよろしくお願いします。

