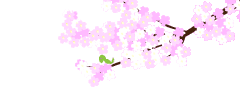
授業が終わると同時に鳴った、代行証と伝令神機。
揃って屋上まで駆け上がり、死神化した。
場所は意外と近く、一高の裏山の―――学校から見て―――向こう側だった。
出てきた3体の虚を2人で瞬殺。
駐在の車谷の伝令神機が虚を確認した直後に反応は消えた。
「よっし、完了」
「うむ、大したこと無くて良かった」
揃って息を吐いたら、ルキアが目を閉じて、クンクンと鼻を蠢かせた。
「……ルキア?」
「―――何やら良い薫りがするのだが」
特別用事も無かった二人は、そのまま薫りに誘われる様に、山へ足を進めた。
二人並んで歩く事数分。
匂いの元へと辿り着いていた。
「うわっ」
「へー」
「……見事だなぁ」
「ああ」
二人の眼前には固まって並ぶ樹が、真っ白い花を咲かせていた。
あまり背は高くなく、周りの木々の枝が外からは見えにくくしていたらしい。
「白梅だ……久しぶりに見た」
「あれ?白哉ん家の庭にねーのか?」
一護の何気ない質問に、ルキアは戸惑った様な表情をする。
「……ルキア?」
「在るにはあるのだが……私の部屋近くには無い」
「あー、広いもんなー」
「……紅梅は十三番隊にもあるから観るのだが、な」
……その紅梅が実は盆栽の迷手・浮竹の手をくぐり抜けて来た強者である事は、古参の者達だけが知る事実だったりする。
「確かに広さもあるのだが……梅は兄様と姉様のお部屋近くにあるのだ」
「なんで?」
「……多分、兄様が姉様の為に整えられたのだと思う。姉様は椿と梅と桜がお好きだったのだと、聞いたから」
「へー、あの白哉が」
「あの庭は、兄様と姉様の庭だ。通される者も多くは無いし……如何に妹と呼ばれようと易々と近付けぬよ」
遠くをみる様な視線の先に、ルキアが何を見ているのか、一護には分からない。
しかし、以前見せてもらった緋真の写真は、ルキアとよく似ていた。
亡き妻の面影を濃く残す妹が、思い出の庭を歩くなら、白哉はそこに緋真を視るのだろうか?
「ふーん、……桜は?」
「ああ、桜はどの庭にも在るぞ?」
「……椿に梅に桜、ねぇ」
なにやら考え始めた一護にルキアが首を傾げた。
椿は六番隊の隊花だし、梅については白哉と初めて向き合い、姉の事を聞いた時に話に出てきた。
一護もその場に居たはずだ。
……桜は白哉の斬魄刀の名にあるし、貴族の庭には大抵植えられる。
何も考える必要など無いはずだ。
「あぁ!……もしかしてそーゆー事なのか?」
「一護?」
「あ、いや、緋真さんがなんで椿と梅と桜が好きだったのか、分かった気がして」
「何だと?」
思いがけない事を言われて、ルキアは思わず一護の死霸装の袖をギュッと握った。
「……」
無言でじっと見上げて、教えろと訴える。
一護は、その必死さに内心狼狽えたが、思わず口にした自分が悪いと、腹を括った。
まぁ、違ってるかもしんないけど、と前置きをするのは忘れなかったが。
「……だから、椿って何色が咲くんだっけ?」
「は?……赤と白では無いか?」
「さっき話した梅の種類は?」
「紅梅と……白梅」
「白哉達の名前の字ってこう書くんだろ」
すらすらと空中に書かれた字に、ルキアは頷く。
「『白』哉と『緋』真。『緋』って、赤の事だろ?」
「……まさか」
「……そーゆー可能性も、あるって事じゃねー?」
姉は、夫と自分の名と同じ色を咲かせる、同種の花が好きだったのか?
兄は、そんな花を邸の庭に植える事で、自分達が朽木の主であり、姉は自分の対だと無言のままで示そうとしたのかもしれない。
「……」
黙りこんだルキアに、一護は軽く言い放った。
「何なら、聞いてみたら良いじゃねーか、今度尸魂界に行った時に」
「……それは」
「今なら、大丈夫だろ」
「そう、だろうか?」
「まぁ、恥ずかしがるか惚気るかは……俺には想像つかねーな」
カラカラと笑いながら、一護は近くの白梅に手を伸ばす。
その背中を眺めながら、ルキアは自分の胸の内が暖かくなった気がした。
「……そういえば俺、紅梅って直接見た事ねーなぁ」
ぽろりと零れた呟きに、ルキアが駆け寄る。
「なんだ、現世には紅梅は無いのか?」
「いや、この近くには植えられて無いだけだ。テレビや図鑑なら俺もある」
白梅はあちこちあるのにと、その薫りを目を閉じて吸い込んでみる。
「やっぱ、匂いとか違うのか?」
「……そうだな、あくまでも私の印象だが、紅梅はもっと華やかな感じだな」
「へー」
「華やかで艶やか、甘さが強い」
直接匂いを比べた事は無いから、見た目のイメージが強く残っているかもしれないな、とルキアは目の前の白梅を見上げた。
「……緋真さんの花、か」
「うむ。白梅は、華やかさより気高さ、凛とした誇り高い花、だな」
「……まさしく「じゃあ、紅梅が緋真さんなら、ルキアは白梅だな」
『兄様の花にふさわしい』
そう続く筈だったルキアの言葉は、一護の思いがけない言葉に掻き消された。
「……何故、そう思う?」
驚き、半ば固まったまま尋ねたルキアに一護の答えはあっさりと返された。
「ん?俺の勝手なイメージ?」
反応に困ってしまったルキアを、一護はグッと背中を反らしてから、振り返った。
「ま、そろそろ帰ろうぜ?遅くなっちまうし」
何せ身体はまだ学校の屋上だ。
「……ああ、そうだな」
少しの名残惜しさを振り切って、前を向けば、一護が端にあった白梅に手を伸ばしていた。
「ああ、でも……」
「?」
「俺は、紅梅より好きだぞ―――白梅(こっち)の方が」
手を伸ばし、枝を引き寄せる。
花と蕾が並ぶその枝先はしなやかに折れず、一護の顔の前に来る。
はてさて、その薫りを楽しんでいるのか、はたまたその花に唇寄せたのか、―――ルキアからは見えなかった。
「さ、帰ろうぜ」
優しく枝を戻した一護は、少しだけルキアを振り返って、こともなく笑い掛けて先にスタスタと歩いて行った。
その背が遠くなってから、ルキアはじわじわと自分の顔が熱を持った事を自覚した。
見られなくて、本当に良かった。
「い、今のはどういう意味だと―――」
本人には決して面と向かっては聞けない事を、ルキアは呟く。
ルキアを白梅と例えたその口で、その白梅が好きだと言う。
極め付けは、最後の行動だ。
「……このタラシめが」
そんな事を誰彼構わずしていれば、いずれ手痛い目にあうに違いない。
茹った様な自分の頬に手を当て、後ろから女に刺されてしまえと悪態をつきながら、この事も兄様に報告してやると、―――一護の身に危険が迫ると自覚の無いまま―――ルキアは心に決めた。
この先でルキアの事を待っている少年が、無自覚のままとはいえ、タラシ込むのが自分だけであるとは知らぬまま、ルキアはその背を追って飛び乗った。
了
↓(オマケ)
「あぶねーな!」
「良いから乗せろ!」
「……へいへい」
「一護!また観にこよう」
「……そん時は、生身で弁当持ってくるか」
「おおっ!それも良いな」
「……お前の手作り?」
「不満か?」
「いーえ、―――適量でよろしく」
―――――――――――――――――――――
周りに梅が満開に近づいてきたので、書いてみました。
私が『椿』(隊花)と『梅』(庭にあるのは確認済み)と『桜』で連想した事を、まんま一護に指摘させちゃいました。
合ってるのかな(笑)?
この一護さんは天然タラシです。
ルキアさん限定ですが(苦笑)。
無自覚に意味深な台詞を吐くので、その度にルキアはオタオタ。
でも、本人も自分が本能的に口にした台詞を吟味したら、恥ずかしさに悶えますねきっと(笑)。

