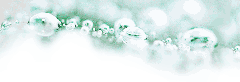
「何で?」
「え?」
「何でお前を責めなきゃなんないわけ?」
全く解らんと一護は目を細めた。
「だって、……私が、あの時力を渡したからではないか!!全ての切っ掛けは、やはり私で、あれが無ければ、貴様は!!」
死神にはなっていなかったではないか!!
そう続けるはずの言葉は、皆まで口には出来ず遮られた。
握っていた襟を外され、グイッと力強く引かれて、ルキアは何かにぶつかり強かに鼻と額を打った。
後頭部には一護の手が添えられ、ピクリとも動けない。
目の前に広がるのは、一護の真新しいスーツのジャケットと、着ているコートの黒だった。
「ルキア、―――そりゃ違うだろ」
もし―――あのまま普通の人間として暮らしていたのなら?
待っていたのは藍染の手による王鍵創世の材料の末路で、ルキアは別の形で殺されていた。
だが一護は何より否定して欲しくはなかった。
「お前は、俺に力と一緒にその意味を教えて、与えてくれたんだ」
……持て余していた、自分の力。
そして無力に打ちひしがれていた自分に、……その力に。
「お前に力を貰って、俺は初めて自分の力に誇りが持てたんだ」
それを、無かったことにしないでくれ。
よりによって、俺を導いてくれたお前が。
上から降ってくる言葉に、ルキアはクスンと鼻を鳴らした。
「お前がその事を後悔して、自分を責める事は、―――俺の誇りを汚す事だと覚えとけ」
きっぱりと言われて、ルキアは目の前のコートをグッと掴んだ。
「そもそも、これは親父からの遺伝だから、お前の責任じゃねぇの!!……解りましたか、朽木さん」
「……分かった」
よしっと頷く一護の声が、とても優しく響いた。
「……だが」
「…まだ何かあんの?」
「……寂しくは、無いか?」
「……何が?」
「生涯、一人なのだぞ?小父様だって、いずれは人としての生を終え此方に来るだろうし、実家には妹が居るとはいえ、遊子は嫁に行く」
しかし、貴様は一人になってしまうではないか。
「ルキア、俺は単に臆病なんだよ。現世で家族を持たないのは」
きっと自分には、―――親父が俺にしてくれたみたいに『見守る』だけなんて、出来ないから。
だから、この点においては、一護は父にはかなわないと素直に思えた。
本当に強いなら、嫁も子も全部巻き込んでも護ると、覚悟を持って進めただろうに。
この二束の草鞋状態では、そんな事を自信を持って言えないのだ。
―――それさえも、自分が選んだ道だった。
「そういう意味じゃ、俺は―――弱いんだよ」
そういって、ルキアを腕に抱いたまま、一護は目を伏せた。
「ま、コンは連れてくから、十分騒がしいだろ」
「アレが子供代わりか?」
「そうだな。まぁ良いんだよ。別にホントにこの先ずっと妻や子が持てないって訳でもねぇし?」
「……は?」
一護の矛盾したような言葉に、ルキアは眉間に皺を寄せる。
「『は?』って、そりゃー現世で人間との子は、あれだけど。そっちでなら、俺も大丈夫だろ?」
「…『そっち』って」
「まぁ、元死神代行だの、人間とのハーフだのって奴に嫁に来てくれるかは、流石にわかんねぇけど?」
予想外のセリフに、ルキアの頭は少々混乱したが、そんな納得の仕方をしてたのかと、開いた口がふさがらない。
……どっかの誰かと似たような事を言った一護はケロッとしている。
何をどう突っ込むべきか、……流石のルキアも悩んだ。
「…一護、人としての生の終わりと死神としての生を、同じ延長線上に置いて考えるな。人としての生の終わりは、紛れもなく『死』なのだから」
「肉体の生が終わっても、俺の魂は俺のままだ。…あれ?俺、そっち行ったら記憶―――消されるのか?」
「!……否、それは」
―――恐らく、無い。
尸魂界の上層部・四十六室も一護の力は身に染みて知っている。
妙な事をして敵に回すより、そのまま味方に引き込もうとする筈だ。
同じ理由で、浦原達の復帰は行なわれていない。
「なら、人の俺も、死神になった俺も、何も変わらないんだよ。俺は俺だ」
それに、人としての生を軽んじたりするかよ。
「本当か?」
「当たり前だ。さっき聞いてたんだろうが?」
母の墓前への、新たなる誓い。
「うむ」
「おふくろが、お前が―――護ってくれた生命だ。そんなことしたら罰あたる。っつーかお前がすっ飛んできてとび蹴りでもされそうだし?」
「それは当然だ」
そこはきっぱりと即答。
言い切ったルキアに一護は思わず笑った。
「まぁ、そっちに行ってもよろしくなって事でいいじゃん」
そん時は、正式な死神として生まれ変わるって事だなと一人頷く。
「尸魂界が貴様の来世と聞こえるな」
「似たようなもんだって」
本当にケロッと言い放つ様子に、半ば言い包められながらも、ルキアは渋面を作る。
「何やら貴様が本当に理解して言ってるのか不安でならんのだが」
大きく吐き出される溜息が、少々重い。
「……じゃあ、お前がこっち来れば良いんじゃね?」
「・・・は?」
「お前が言うには、俺はお前が見張って無いとすぐにヘタレるみたいだし?」
「そ、それはっ」
「―――そうだよ。俺の監視兼サポート、制御の為には隊長格が望ましい!とか言って来いよ」
研修医としての間は、無理だが、二十六の年には実家に移るのだと一護は言う。
「その頃は俺も一人暮らしだから、お前一人増えたって、仕事持ち込んだって平気だぞ?」
勝手に出された提案にルキアは一護の胃に頭突きでもしてやろうと考える。
「……そしたら、コンも喜ぶし。俺が寂しくもならない事確実だぞ」
「!!」
寂しくないかと問うたのは、ルキアだ。
「朝起きたら、お前が居て、コンが居て、一緒に飯食って」
お前はソコで仕事して、と一護が語るのは、まるで現実味が無くとも、夢のような未来。
「夕方帰ったら、家に灯りが点いてて、―――今の家みたいにお帰りって返事が返って来るんだよ」
そう、それは空想のままごとの様で。
「何だ、夕飯は私の担当なのか?」
「じゃあ、朝は作ってやるよ」
ルキアもちょっと悪乗りした。
「私は貴様に養われるのか」
「代わりに疲れて帰る事確実な俺を、癒してくれたら問題なしだろ?」
「貴様は同居人を養うのか、アホだろう」
だから、すっかり油断していた。
「んー……それってすっかり家族だな。それとも――――――いっそ、本当に嫁に来るか?」
それはもう、ピシリと動けなくなった。
「そうだよなー、お前とだったら尸魂界いっても、そのままやっていける……よ、……な、るき、あ…?」
腕の中でルキアが身体を強張らせたことに、支える掌から感じ取り、一護の軽かった口調も段々尻すぼみになって行った。
そっとルキアを見下ろせば、一護を凝視していた顔が、見る見る内に真っ赤に染まっていった。
え?
あれ?
……何?
俺、今―――何、言ったっけ?
ルキアは勿論だが、言った一護の方もプチパニックだった。
その間も、一護は自分の顔に熱が昇っていくのを自覚した。
この一月の寒空の下だ。
はっきりと分かる。
「キ、貴様……そういうセリフは、ちゃんと、恋人である女性に言わぬか…っ」
「い、いや、だから、俺は、現世の女性を妻にする気はねぇんだから、他に言う予定なんかねぇ、ぞ?」
現世の女性で無い自分なら良いのか?!とか言いたいことはあるのに、言葉になってくれない。
それはまるで、『お前以外には言わない』とも聞こえて、知らず目が潤んでいく。
―――今までだって散々一護の無自覚な言葉に、ルキアは振り回されてきたが、―――これが無意識だなんてありえない。
無意識だったら、これは、一護の本音になってしまう。
――――――だって、これは……。
「……なんか、プロポーズ、みてぇ、だ、…な……?」

