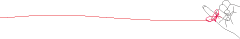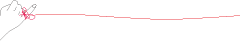
 少年rに手紙を2
少年rに手紙を22014.01.11
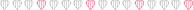
なんて言ってごまかしてみたり。
佐久間光には気にしている人がいる。
同級生の黒髪の可愛らしい少女だ。
彼女の名前は加賀美月さん。とても優しい子で、人を後ろで支えるのが上手な子だ。
趣味はおかし作りということでいつも甘い香りを漂わせているふわふわしている子だ。
だけど、僕はこの子を気にしている。これは恋なんてもんじゃない。僕は見てしまったのだ。
彼女のある行動を。
夏。放課後。
教室で友人を待っていたのだが、窓を開けても暑いもんだ。自動販売機に行ってコーラを買いに僕は黒澄んだ百円玉と数十円を持って外に出た。
教室を出た。
出たのだ。ドアを閉めず。中が見えるぐらいあけっぱで。
「………」
外に出て、コーラを買って、また来た道を戻って教室についた僕が見たのは。
ピンクな。思春期な彼女だった。
「大好きなの。とってもとっても大好きなの。大好き」
甘い声。甘い匂い。甘いムード。
この声は、この匂いは、このムードは。
加賀美月だ。
あれはなんだったのか。あれは夏が僕に見せてきた白昼夢だったのだろうか。今の僕でもわからない。
ただただ彼女の存在は変わった。ふわふわからどろどろへ。愛くるしいから…。
ワイシャツの襟首のボタンを外し、真っ赤なネクタイを緩める放課後。汗ばんだワイシャツがしっとりと皮膚に絡みつく。風はない。
夕日が教室を染める。
そして、彼女が現れる。
僕の右手にはショットガン
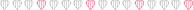
戻る