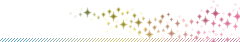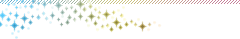
生路・7
静寂が支配する闇の中、重い目蓋を上げる楼那。
意識の覚醒と共に腹部の痛みが甦り、わずかにその眉根を寄せた。
白馬寺の仏堂と庭、至る所に黄巾賊に害された領民達の骸が無残に横たわる。
美しかった蓮池も今は黒い血に濁る。
寺院に押し入った賊はあらゆる物を略奪し、抗う者を情け容赦なく斬り捨てた。楼那もやはり槍で脇腹を突かれ、流れる血潮に次第に意識を遠のかす。
(……)
間近に迫る最期の時。
が、刹那、不可思議な兆しにその魂が呼応した。
体に残る力のすべてを振り絞り、よろめきながらも立ち上がる。朦朧とする意識の中、一歩一歩踏みしめるように寺院の回廊を進む。
手摺を伝い、石畳を踏んだ。
頭上の星図を高く仰ぐ。
「!」
と、楼那はふいに近くに降りた“大いなる星”の気配にその目を見開いた。
暗闇の中、星の光が次第に人の形を成す。
それはやがて白馬を引いた一人の青年へ変わった。
「おぉ…」
今や楼那の霞む意識は完全に覚醒を果たし、尽きかけた魂の火は最後の熱を彼の四肢へと駆け巡らせた。
「貴方は、」
そう呼びかけた楼那の眼前、青年がハッとしたように立ち竦む。
「これは…!」
青年―――劉備は急ぎ楼那に駆け寄った。
冷たく凍えた世界の中で生者と巡り会えたこと、それは思いもよらぬ驚き、そして喜びであっただろう。
「なんたること、よもや生きている人がいようとは…御坊、私は琢の劉備と申します」
「劉…?……いや失礼…私は楼那、この寺の行者にございます。しかし、貴公、何ゆえにここへ参られた?」
「人を探しているのです。御坊、我が叔父劉元起がこちらに来てはおりませぬか」
「…いえ、心当たりはございません」
楼那の応えに劉備は落胆の息をつく。
が、彼はすぐさまその双眸に強い決意の光を湛え、楼那に向けて言うのだった。
「それでは共に参りましょう。このまま居ては再び賊に襲われぬとも限りません。さ、どうぞ、私がお連れ致します」
楼那が負った深手を劉備は知る由もない。避難を促す青年を前に、異国の僧は静かな笑みを浮かべて小さく頭を振る。
と、ふいにキィンと鋭い音が夜のしじまを切り裂いた。
劉備の腰に佩かれた靖王の剣が再び刀身を鳴らす。
「劉備殿…その剣は一体?」
「これは我が家に先祖代々伝わってきたものなのです」
劉備の手から靖王を受け取り、その幽かにまばゆい刃の光に深く見入る。
楼那の面に驚嘆が、次いで安堵の色が浮かぶ。
「これはまさしく王者の剣。魔を払い、暗黒の世に光をもたらす王の証となる剣だ」
靖王を押し戴いて劉備に深い礼を捧げる楼那僧。
彼の心は深い喜びに満ちていた。この世で果たす最後の務め、今それに確かな希望をもって己は臨んでいけるのだ。
「劉備殿、貴方には大いなる星の導きと加護がありましょう」
「大いなる星…?」
「志をお持ちなさい。貴方の相は天下を統べる王者のそれであるのだから」
「御坊…」
宿房の一画。
隠し扉の向こうに「姫」と楼那は呼びかけた。
「芙蓉姫、私です、安心して出ていらっしゃい」
漆喰の壁がギィときしんだ音を立て、一人の少女が中から姿を現した。
「…御坊様」
「大丈夫、賊はもうここを去りました。さ、おいでなさい、貴女に会わせる人がいる」
芙蓉を伴い回廊を抜け、寺院の正門へ向かう。
「……」
門前に射す月の光。
少女の瞳は白馬とその傍らに立つ青年の姿を映し出していた。
「劉備殿」
楼那の声に青年が此方を顧みる。
瞬間、重なり合う視線。
劉備は思わず息を呑む。
(なんと美しい人だ!)
眼前の佳人、月の雫を集めたような清く麗しい姿に、劉備の魂は震えた。
それはまったく思いもよらぬ出来事だった。
青年は未知の情動に惑い、次いで湧き起る甘い疼きに胸の鼓動を早くする。
澱み荒んだ世界の只中にあって、この少女の存在はいっそ奇跡にも思えた。
「こちらは芙蓉姫、先頃賊との戦いでお亡くなりになった領主、鴻淵様のご令嬢です。劉備殿、この方を貴方にお預けしたい、どうか安全な所へ送り届けて下さらんか」
「私がこの方を…」
「この通り、どうかお頼み申します」
「…わかりました。この劉備、一命を賭してお守り致す所存です」
「おぉ!…良かった、良かった、これで気がかりな事は何も無くなった」
楼那は芙蓉の背を押して劉備のもとへ向かわせる。
「御坊様もご一緒に」と振り返る芙蓉に彼は穏やかな笑みを向け、言った。
「私はここに残ります。死んだ者達、善男善女を弔い供養しなくては」
瞬間、すべてを悟った芙蓉の頬をひとすじの涙が伝う。
「姫をお頼みしましたぞ」
深くうなずき、華奢な芙蓉の身を抱え馬鞍に乗せてやる劉備。青年は楼那に一礼し、自身も鞍上の人となる。
別れの時。若い二人の目の前で、楼那の指が遥かな北の空を指す。
「ご覧なさい。あの北斗星、あの星に向かいただまっすぐに駆けなさい」
「御坊様」
「御坊…」
「劉備殿、芙蓉姫、星のさだめを信じて強く生きるのです。どうか幸多からんことを」
白馬は夜の底を駆ける。
深く沈んだ暗い森。耳元を、頬を、凍えた風がかすめていく。
手綱を手繰る劉備の瞳に宙を舞う透明な涙の粒が映り込む。胸の中、芙蓉のけぶる睫毛にからむその雫。
儚く柔いその肢体。小さな胸の奥底に秘めたその悲しみを思うだに、劉備の胸は締めつけられそうになった。
ふとした瞬間、劉備の眼がひとしずく、芙蓉の頬にかすかな熱を落としていた。
少女の両の目蓋が上がり、花のかんばせがおもむろに青年を見上げる。
二十二歳の劉玄徳と十四歳の鴻芙蓉。
互いの瞳の奥を見る。まぶしい煌めきが宿る。
やがて風に舞う涙の粒は天に上って銀河に溶けた。
二人は星の鼓動を聞く。
北斗七星の光が若い魂を導き、真白い月の輝きは世界を隅々まで照らす。
続く
戻る