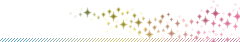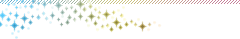
生路・6
黄巾賊の侵攻により戦場と化した琢郡南部。
方々の集落に火の手が上がり、目を覆わんばかりの惨状が引き起こされていく。家を、親を、子を失って、人々は黒い大地に呪詛を吐く。
劉備の旅団は北上するに従ってその隊列を長くする。行く先々で救いを求める難民に遭遇し、とても見捨ててはおけぬと手を差し伸べた結果だ。
進行速度が落ち郷里への帰還が間遠になったのは事実であるが、しかし、劉備の面に迷いの色は見られない。
(人の器ってものはこういう時にはっきり見えてくるもんだ)
簡雍は思う。
幼なじみの劉玄徳。甘えん坊で泣き虫で、いつまでも“弟分の可愛い阿備”でいるのだろうと心のどこかで思っていた。いや、そうであって欲しいと願っていたのかもしれない。
小さかった弟はいつしか大人へと変わった。自己の信念に従い、苦難に抗い戦う道を選び取った。
そんな劉備の内なる炎を簡雍は知る。知り、理解し、共にしたいと願っている。
(玄徳、俺もお前もとんでもなく生きづらい世に生まれちまったもんだよな。出来ることなら真っ当に生きていきたいと思うが、この俺みたいな俗物はひとたび道を誤ったならただもう転がり落ちるばかりで二度とは這い上がれんだろう)
必要なのは灯だった。
道を誤らぬ為に、暗い世界を前に進んでいく為に、消えぬ灯火こそが欲しい。
(俺の灯はお前だよ)
劉玄徳の炎とは大いなる仁のそれである。
彼の心を揺さぶり行動させるのは人の涙と願いであるということを、簡雍は今、確信する。
「あれ…」
遥か前方、原野の彼方に目をこらしていた田豫が小さく呟いた。
「もしかして、」
少年はよく遠目が効く。二、三度まばたき、そうしてパッと笑顔になった。馬の脇腹を軽く蹴り、前を行く劉備へと駆け寄る。
「玄徳さん、州軍の旗が見えますよ!」
その呼びかけに両目を見開いた劉備。
「ほら見て!」
「おぉ…あれは、」
強い北風に青い軍旗が翻る。
なびく錦に縫い付けられた「幽州」、そして「鄒」の文字。
これこそまさに州都・薊より賊の討伐に赴いた幽州軍の先兵隊であったのだ。
「みんな見ろ、助けが来たぞ!」
蘇双の声に難民達がワッと歓声を上げる。
傷つき疲れた彼らの面に希望の色が戻っていた。
劉備は簡雍を伴い、幽州軍の指揮官に面会の申し入れをした。果たせるかな、軍を率いる校尉・鄒靖は劉備の師である盧植に面識のある人物で、両者はわずかの間に親しく語らい心を通わすに至る。
安堵の息をついたのも束の間―――蜂の如くに起こる賊徒の報を受け、幽州軍は出撃体勢に入る。
「憲和兄さん、蘇双さん、お二人は叔父上と民とを連れて急ぎ村までお戻りを。私はもう一度中山の境へ向かいます」
「そんな…玄徳お前、」
「元起叔父上を見つけてきっと戻ります。兄さん、道中くれぐれも気をつけて」
引き留めかける簡雍と蘇双に劉備は小さく頭を下げる。
彼は胡庸と田豫、旅団の半数を連れて、再び南へ馬を駆った。
南下の途上、黄巾賊との遭遇と戦闘を幾たびか繰り返す内、やがて旅団は散り散りになる。
いつしか劉備は漆黒の闇を単騎で駆けていたのだった。
無情なる雲にさえぎられ月光は地に届かない。鬱蒼とした森の中へと迷い込み、ただただ惑うばかりである。
心細さを振り払い、強くあれ、勇者であれと何度も自己に言い聞かせた。靖王の剣を鞘から抜いて頭上に高くかざしてみれば、白刃はまるで天上の星のきらめきを束ねたように煌々として輝き出す。
その輝きは暗闇に在って劉備を導く灯火だ。青年は剣に宿った祖先の御魂、血脈の加護を強く烈しく自覚する。
茂みをかき分け、林道に出る。
風も無い中、靖王の刀身がキィンとかすかに鳴る音を劉備は確かに聞いていた。
「……」
ふと、彼は“予感”にかられ前方の闇に目をこらす。
「…!」
靖王の煌めきと響く音とがひときわ強いものになり、そうしてふとした瞬間にすべてが静止し、無になった。
無音の世界。
次第に晴れていく雲間。
降り注ぐ月の光が劉備の瞳に白い伽藍を映し出す。
(これは…)
ややあって劉備の四肢の強張りは解け、一陣の夜風と共に世界に音が戻ってきた。
眼前に出現した五重造りのその仏塔。
月光に照らし出された門の扁額に「白馬寺」の三文字が刻み込まれていた。
続く
戻る