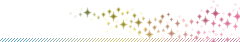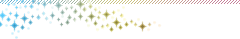
生路・3
◆簡雍(156年生)
靖王の剣。
代々劉家の親から子へ、子からまたその子へ長きに渡り受け継がれてきた王者の剣だ。
その白刃の煌めきが若き劉備に血脈の重みを知らしめる。
剣を携え、蘇双の伯父・張世平のもとへと単身向かう劉備。
豪商の眼前で拱手し深く頭を垂れ、「馬と兵とをお貸し頂けますまいか」と至極簡潔に告げた。
青年の意図するところを瞬時に悟る張世平―――わずかに、しかし驚いたように両の眼を見開いた。
「中山へ出向くおつもりなのですか」
「はい」
「元起殿と子敬殿の件、私も気にはしておりました。ご一族の皆様もおつらいことであるのでしょう。が、しかし、玄徳殿…それはあまりに無謀な賭けではありませんか」
「……」
「今国境で何が起こっているのかは貴方もご承知のはずだ。賊はその数、千とも万ともつかぬという…州軍の到着まで今しばらくお待ちになられてはいかが」
張世平のその言に劉備は黙し、瞑目する。
ややあって彼はその目蓋を開き、深緑の双眸に強い光を湛えて言った。
「張大人、私の父は私が七つの年の冬、胸を患い亡くなりました。今でもよく覚えています、あの夜の吹雪の強い音を」
「……」
「家には母と私のたった二人になりました。禄は絶え家人は去り、生計を得るため母は靴を縫い私は藁を綯いました。母が、苦労を知らずに育った若い身空の母親が、己の晴れ着を裁ち切って、靴を…」
言葉をつまらせる劉備。
その目尻にはかすかに光るものがある。
「ある日、二人の叔父が母を訪ねてこう言いました。備を連れ越していらっしゃいと…我ら両名、幼少の頃より亡き兄上にはひとかたならぬ恩愛を受けてきた、今その恩を義姉上と備に返していきたいのです、と」
「……」
「元起叔父上と子敬叔父上は玄徳を我が子も同様、深く慈しんで下さった。衣食だけでなく学問の機会をもこの身に与えて下さった。盧植先生、書に、剣に、一体どれほど多くの世界を私は知ったことでしょう。張大人、私は幸福であったのです。叔父達は私にすべてを与えてくれていた」
劉備の頬を流れるひとすじの涙。
今、彼の胸中に青春の日々の記憶が波のごとくに押し寄せる。
「この身は若輩者なれど忠孝の道理はわきまえているつもりです。無謀な賭け、確かにそうなのかもしれない。でも、それでも私は賭けてみたい、ほんのわずかの希望があるならそれにすべてを賭けてみたいと思うのです」
「賭ける……いいえ玄徳殿、それは間違っていますよ」
「……」
「賭けるではなく、信じる、でしょう?」
「!」
「信じたい、そう、信ずる心はすべてのことの動機と成り得ますからね」
「張大人、」
「よろしい。劉玄徳、当家の兵を貴方にお預け致しましょう。私も貴方を信じます、商人は何より信義を貴ぶもの……さ、そうと決まれば急いで支度しなくては」
「大人、」
「出立は明朝、ぐずぐずしてはいられませんぞ!」
「…感謝致します、大人!」
睫毛に絡む涙を払い、劉備は深く拝礼する。
そんな青年の肩を張世平は期待と励ましを込めてぐっと力強く抱いた。
伯父と劉備のそのやり取りを衝立の向こうで聞く蘇双。
その胸中にあの日の劉備の言葉が幾度も甦る。
本当に正しいもの、尊いものは、それは…
翌早朝。
張世平の邸の庭に集った三十人の手練れの士。
彼らはみな不測の戦闘に備えて種々の兵器を身につけ駿馬の手綱を締め直す。
(……)
ひんやりとした空気の中、劉備は帯の左右に下げた長剣の柄を握り締めた。
キン、と鋭い音を立て、鞘から白刃が抜かれる。
右手に靖王。
そして左に張世平より守り刀として贈られた呉の細剣。
重ねた切先。昇る朝日の気高い輝きが宿る。
劉備は思い返していた。
恩師・盧植の眼差しを、遠いあの日の空の色を。
その日、学び舎の空はどこまでも高く澄んでいた。
八尺二寸の師の巨躯が繰り出す剣先の鋭さ。右に左に、どこから来るか予想もつかぬ動きを前に、十六歳の劉備の息は荒くなる。
柔く優しく生まれついている少年の手に鋼の剣はひどく重い。
一撃、二撃、三撃と、盧植の剣を受ける度、痛い位の衝撃が剣柄を通して劉備の全身に響いた。
「どうした玄徳、こちらに踏み込んできなさい」
盧植は事もなげに言う。
泣き出したいのをグッとこらえ、劉備は剣を握り直して地を蹴った。
自身が人より腕力に劣る事実を痛い位に自覚していた少年は、その非力を補って余りある程の剣技を会得しようとした。幸いにも天分に恵まれ、師の教えのもと劉備は日々めざましい上達を遂げていく。
武を極め兵を巧みに用いる盧子幹はしかし、劉備の剣を鍛えつつ、繰り返し繰り返しこう言い聞かせるのだった。
「剣と戦はあくまで手段に過ぎんのだ。どこまでいっても武は物事の本質、理由とは成り得ぬ。玄徳よ、いつかそなたが困難に遭いその道行きに迷う時、そなたは剣を握るだろう。だが、だがな玄徳、決して見失うでないぞ。最後に人を救うのは、人と己を生かすのは…」
伝え、受け継ぐ。
盧植の言葉は劉備の内で“信念”という強い鋼の剣になる。
真に正しく尊いもの。最後に人を生かすもの。
心の底に在る光。
己を突き動かす情動。
(信じること、そう、私は信じられてきた。多くの人に信じる事を教えられた。今が応えるその時だ)
繰り返す。
言い聞かす。
誰に?―――己自身にだ。
(……)
わずかにその身を震わせて、劉備はきつく目を閉じる。
朝日が白い頬に射す。
拭いきれない恐れと不安を呑み込んだ。
「…?」
ふと、劉備は背後に人の気配を感じて彼方を顧みる。
まぶしさの中、その人影に目をこらす。
「…あっ」
憲和兄さん!―――わずかに跳ねる劉備の声。
眼前に幼なじみの青年・簡雍憲和の姿を見止め、大きな両目を更に大きく見開いた。
「兄さん、」
「おう、おはよう玄徳」
「え……あの、その姿は?」
「その姿はって…おいおい、今から叔父上達を探しに行くって話だろう? それにふさわしい姿をするのは当たり前さ」
劉備の唇が震える。
決意に強張る顔と肩から力が抜け、元々幼い造りの面が一気に子供のそれになった。
「…私と一緒に行って下さるのですか?」
「いけないかい?」
「いえ、いいえ……兄さん、私は、玄徳は、」
剣を握った両手が小刻みに揺れる。
「決めたんです。叔父上達を見つけてきっと一緒に帰るって。まだ生きていると信じてる、でも…」
「でも?」
「怖いんです。もし違ったら? 会えずに終わるかもしれない、賊と出くわすかもしれない、私は人を、」
人を斬るのかもしれない。
血族の為、生きる為、己の剣は人を殺めるかもしれない。
「怖い。怖くて怖くてたまらない。私に果たせるのでしょうか。死にたくない、叔父達に生きていて欲しい、一体私はどうしたら…」
か細い声。
うつむく面は逡巡を帯びて暗くなる。
「……」
しばしの沈黙を経て、簡雍はおもむろに劉備に歩み寄り、白い両手を引き寄せ剣柄ごと握った。
「玄徳、俺もやっぱり怖いんだよ。昨日は随分迷ったね。張の旦那の家にお前が向かったと聞いて、大方の予想はついたがしかし、いざ自分もと思うと足が震えてね」
「……」
「ごろつき共との喧嘩とは訳が違うしな。賊を相手に切り合いにでもなったなら…ああ、考えただけでゾッとする。どう考えても俺の性分じゃあないし、いっそこのまま見て見ぬふりを決め込もうかと思ったが…」
簡雍は言う。
劉備に伝えようとする。
「でもね、自分に嘘はつけないよ。なぁ玄徳、俺はお前をこんな小さな赤子の頃から知っている。ずっと一緒にここまで来た。お前は俺を兄貴と思ってくれている、俺もお前を可愛い弟と思う」
「……」
「その弟が、たった一人の弟が、命を張って成そうとしてる事がある。知らんふりなど出来ないよ。そう、俺はお前と共に居たい、お前と一緒に生きたいんだ」
「兄さん…」
「玄徳、昔お前と唱えたね。塾から帰ったお前はいつでも俺にあの言葉を語り聞かせてくれていた。さあ玄徳、もう一度俺に聞かせてくれ、俺のこの背を押してくれ」
重なる手。
心と心とが繋がる。
同じ風、同じ景色の中で育った二人が今、朝日の向こうへ手を携えて踏み出すのだ。
「知者は惑わず」
劉備は言う。
「知者は惑わず」―――煌めきを宿したふたつの緑を見つめて簡雍がそれを繰り返す。
「仁者は憂えず」
「仁者は憂えず」
「勇者は懼れず」
「勇者は懼れず…そう、そうだ玄徳、懼れるな。自分を信じろ、お前にはきっとそれが出来る」
「信じます、兄さん。私は貴方を、己自身を信じます。勇者となりたい。きっとなります、絶対に」
最後に人を救うものは、真に正しく尊いものは、信じる愛であると知る。
白馬に跨った劉備。
朝日の中、彼を先頭に馬蹄の音を響かせ村を発つ旅団。
村境にさしかかる頃、劉備はふと切ない予感にかられて辺りを見渡した。
数瞬ののち、村名を刻んだ石碑の横に立つ宋淑玲を見止めて(あっ)と息を呑む。
子を送り出す母の瞳は濡れていた。
信じていると、生きて帰ってきておくれと、苦しい程に願う心に満ちている。
(母上、私は必ず戻ります。元起叔父上、子敬叔父上、皆と共にきっと帰ってまいります)
信念が彼を導き嵐の中へと向かわせる。
激しい風は青年のその歩を阻み大きな試練を課すだろう。
(懼れない。母上、叔父上、憲和兄さん、張大人、私は勇者になってみせる)
亡き父が、祖父が、数多の祖先が身に帯び伝えた靖王の剣、その煌めき。
愛し、愛され、守られてきた記憶の結晶であるのだ。
劉備に宿る金色は昇る朝日のそれにも似る。
村境から南に十里ほど進んだところで、劉備はふと、遠くから己の名を呼ぶ男の声を耳にした。
手綱を引き、隊列を停めて後方に馬首を向けてみる。玄徳、玄徳と繰り返し呼ぶ声には聞き覚えがあった。
やがて此方に向け駆けてくる一騎を見て取り「あっ」と驚いて叫んだ。
「蘇双さん!」
追ってきたのは蘇双だった。
目を丸くする劉備の横、簡雍も同じく驚いたように目を見開き、次いで小さく吹き出した。
一行に追いついてきた蘇双はどこか気恥ずかしげな様子で頬を掻いている。
「蘇双さん…力を貸して下さるのですか?」
劉備の問いに「まぁな」とわざとぶっきらぼうに返してくる。
「その、なんだ…人手は多いに越したことないだろ」
精一杯の照れ隠し。
劉備の目尻ににじむ涙はすぐに笑顔へと変わった。
「らしくないね、蘇双さん」と簡雍が蘇双をからかえば、三十人の旅団の士もみな朗らかに笑い出す。
「なんだい皆、そんなに笑うことないだろ、俺だってここ一番の男気は心得ているつもりだぜ」
困ったように言う青年に明るく笑いかける劉備。
「ありがとう、本当にありがとう蘇双さん。感謝しています、心から」
「…水くさいよ玄徳、俺と君との仲だろう」
若者達の行く手には新たな時代の嵐がある。
信じる心と勇気とがその道行きを照らしていく。
続く
戻る