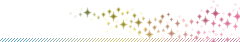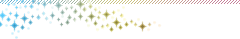
暁光・17
章武二年正月。
夷陵の陣屋に音も無く雪が降り積もる。
弔いの香がたゆたう祭壇の前、白の布帛に包まれ黄忠は眠る。
老将の遺骸に寄り添い鎮魂の祈りを捧げるのは、王平。
黄漢升。
その死に顔に苦しみの色は見られない。
静寂が支配する真白い空間の中で、彼女は独り亡き人を想い、また悼む。
(江東においては弓腰姫と称えられる奥方様の弓の技、ひとつこの老骨に見せては頂けますまいか)
公安城のあのひと時から十二年もの月日が経っていたのだった。
王平は思う。七十五年の生涯は嵐のそれであったろう。出会い、喜び、泣き、笑い―――そして今、遥かに高い天へと魂は還る。
その旅路がどうか安らかであるように。
黄忠の胸に守りの小弓を手向けた。
赤い。
何もかもすべて血に染まる。
血の赤はやがて炎のそれと化していく。
馬鞍山の四方から呉軍の火矢が降り注ぐ。
炎に包まれた夷陵。
視界がすべて火の海だ。
業火の中をかいくぐり、王平は単騎、劉備の姿を探し求めて死地を駆ける。
「……」
―――ふと、何かの予感にとらわれ手綱を引く王平。
燃え盛る木立の向こうに目をこらす。
一騎の影を見止めていた。
味方か、それとも呉の兵か。
「…!!」
次の瞬間、ああ、と我知らず驚嘆の息をついていた。
「興覇!」
舞い散る火の粉の向こう側、その人もまた此方を見遣り目を見開く。
「おお…貴女は、」
甘寧は見る。
別れの丘より六年の歳月を経た邂逅だった。
「姫」
王平―――孫尚香の双眸が熱い奔流を溢れさす。
彼女は甘寧の胸に突き立っている黄金の矢を悲痛な眼差しで見つめた。
そう、あれは味方の、西胡の雄・沙摩柯の矢に他ならない。
朱に染まった甘寧の胸。一目で深手だとわかる。おそらくはもう助かるまい。
「興覇…」
滂沱の涙が頬を濡らす。
彼と過ごした日々の記憶が波濤のごとく胸に迫る。
並び見た空。
長江の青い水しぶき。
親にはぐれた子烏と、あの日の風と、語らいと―――すべては思い出の彼方だ。
「姫、願いは、」
「叶えたよ、私は願いを叶えたのだ。望んだものにすべてなれた」
尚香のその応えに、甘寧は苦しい息の中、安堵の笑みを浮かべていた。
良かった、何よりのことですと、つぶやくように言い、笑う。
尚香も師に向け笑う。
努めて笑みを向けようと…だが、やはり涙はその頬を流れて止むことはなかった。
「お志を果たされんことを祈ります。姫、重々ご自愛のほどを……これにてお別れ致します」
「ありがとう、興覇、会えて良かった、会えて…」
尚香と甘寧。
二人の眼前、燃え朽ちた木々が轟音と共に横倒しになり、互いの影を炎の渦に溶かしていく。
炎の谷を抜け出た甘寧は富池口へと至る。
岸辺に桑の大木を見、瀕死の体を引きずるようにその木の下へ行き着いた。
座り込み、幹にもたれて細く小さく、息をする。
彼方の紅蓮。
黒煙に覆われた天を仰ぎ見た。
「…おぉ、」
ふと、傍らに懐かしい羽ばたきの音を聞く。
「お前……そうか、俺を迎えに来てくれたのか」
肩の上、いつかのようにあの子烏がカァカァ甘え鳴いていた。
「また会えたな。やはりお前は金烏の化身であったのだ。姫の仰られた通り……さあ、頼むぞ、日輪のもとまで俺を導いていってくれ」
すべてが金色に溶けゆく。
日輪の使い、神鴉の導きによって、甘寧の魂は遥かな蒼穹へ昇った。
建興三年。
この年の三月、大渡河の以南において南蛮王・孟獲を筆頭とした南中豪族勢が蜀漢に反旗を翻す。
丞相・諸葛亮は五十万の兵を率いて直々にこれの鎮圧に赴いた。
随行するは趙雲、魏延、馬岱、王平、馬謖、関索、張嶷、張翼、馬忠、董厥、樊建。
半年に渡る南蛮征伐の幕開けだった。
岷江を南に下り、金沙江の流れを渡る。
孟獲の支配する昆明は果たして蛮都、未知なる地だ。
獰猛な獣達。
疫病を運ぶ数多の虫。
毒河、毒泉、毒気を吹き出す死の岩場。
困難の中、諸葛亮の命を受けた王平は五百の手勢を率いて敵地探索に赴いた。
捕らえた蛮兵を懐柔し、また叟族と交渉して、慎重かつ迅速に地理を図面に落とし込む。
王平の切り開いた進行経路は日々後方の本陣、諸葛亮の元へと早馬で届いた。
ひと月ぶりに本陣へと帰還した王平は、諸葛亮の幕舎で彼と向かい合った。
過酷な任務を全うしてきた王平を言葉少なに、しかし真摯な声音でもって労う諸葛亮。
二人はしばしこの戦役の先行きについて語り合う。
なぜ反乱が起きるのか、
憎悪と対立の根源に何があったのか、
どうすれば分かり合えるのか。
「叟の民には我らの同胞であるといった意識は微塵も無いのではないかと…華夏の民、悪しき者よと、私や部下を憎み恐れて止まぬのです。その、正直どうしたらよいのか…」
厳しい行軍の道中、土着の民から向けられた不信に満ちたあの眼差し。
やりきれなさに歯切れの悪くなる王平と、その眼前で思考し黙す諸葛亮。
ややあって、彼はその口を開いた。
「…王化を、」
「え」
「王化を施し従えようと、そのように思い来ましたが、誤っていたやもしれません」
「?……丞相、彼らに漢の大義を示して従えることが誤りであると仰せですか」
「いえ、理念としては必ずしも誤りでない。ただ、そこには多分に我ら自身の思い上がりと彼らに対する蔑みの念とが篭っているのではないかと、そのように思えてならぬのです」
「蔑み…そんな、私は決して南中の民にそのような、」
「わかりますよ王平殿、貴女の思いは充分に。しかしこれはあまりに根深い問題だ。我ら漢人、華夏の民が抱えた業にまで及ぶ…」
古の商の代より続いてきた華夏人と夷人の血濡れた抗争の歴史に、諸葛亮と王平はその眉を曇らせる。
この戦いに果たして光はあるだろうか?
殺し尽くせば終わるのか、
力でねじ伏せることが真に正しい行いか?
重き逡巡。
惑い、悩んで、そうしてふとした瞬間に、二人はかの人を思う。
「先帝は、」
そう言いかけた王平に、諸葛亮がハッとしたように白い面を上げていた。
「先帝は常日頃仰せになっておられました。語らうのだと、相対したならただひたすらに言葉を交わし語らえと」
「語らう…」
「丞相、語らうこととは斬り合うよりもよほど容易く、そして成し難いことですね」
「……ええ、本当に」
しかしそれこそまことの道であるのでしょう―――己が心に刻みつけんとするかのように、決意を込めて彼は言う。
劉玄徳。
とわに忘れじの面影。
今は遠くのかの人に、この道行きを照らしてくれるよう願う。
二人の眼差しの先にいつでも彼は在り続ける。
と、諸葛亮の幕舎を辞して一歩外へと出た王平のその耳に、ギャンギャンがなる馬岱の声が飛び込んだ。
何事かと声のする方を向いて、次の瞬間、ポカンと口を開けていた。
「ああもう、酷い目に遭った! 趙雲殿、二度とこんなのは御免だぞ!」
馬岱が纏う草色の匈服は何かの爪で裂かれたようにボロボロだ。革帽も飾りの房を失ってずいぶんみすぼらしく見える。
カッカする彼のその後ろでは、やはり古裂と化した戦袍を纏う趙雲が「すまんすまん」と笑っていた。彼のとなり、同じくボロボロの魏延が「あの豹、今度会ったらきっと毛皮にしてやるぞ」と息巻く。
なんだアレはと言わんばかりな王平に、関索があきれたような口調でもって告げてきた。
「趙雲殿が祝融の挑発にまんまと乗って獣の群れに突っ込んでいったそうですよ」
「なにっ、そうか、お三方のあの身なり…そういう事か」
反省したのか、していないのか…今では総白髪となった趙雲子龍は呵々大笑して「そう怒るなよ」と馬岱の背中をバンバン叩く。
ただでさえ暑さに弱く南中を厭う馬岱―――彼はついにその鬱憤を爆発させた。
振り返り、趙雲に向け、叫んでしまう。
「このっ…老害!!」
趙雲の傍ら、魏延が「うっ」と低く呻く。
続けざま、慌てたように叫ぶ関索。
「まずい! 馬岱殿、ご老体にそれを言ってはなりません!」
畳みかけるようにして、王平。
「そうだ、老将軍に老害などと失敬だ!」
・・・・・・・・・
「老害? 老将? ご老体?」
真顔で聞き返す趙雲。
馬岱、関索、王平は、三人同時に「あ、しまった」と口元を手で押さえていた。
両手の指をボキボキ鳴らし始めた趙雲の横で、頭を抱えた魏延が「うわー」と悲鳴する。
うっかり発動させてしまったその禁句。
王平と関索と馬岱、三人揃って踵を返し、脱兎のごとくその場から逃げ出した。
そんな彼らを拳を握って追いかけ回す趙雲の後ろ、「落ち着いてくれ」と必死になって魏延が追いすがっていく。
ワァワァと果てない追いかけっこを続ける諸将。
幕舎より出で、その喧騒を遠くに見やる諸葛亮―――手にした羽扇で顔を覆い、やれやれと大きなため息をついた。
続く
戻る