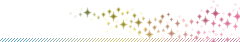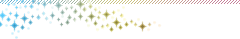
暁光・16
王廟の別院―――その一室で孫尚香と諸葛亮とは向かい合う。
「……」
諸葛亮はうっすら胸を痛めていた。
呉国の姫はその全身が泥と砂とに煤けている。かつて錦の戦袍を纏った麗しの姿も、今はうらぶれ惨めなほどの有り様だ。
彼は憔悴しきった様子の尚香に対し、慎重に言葉を選び、問いかけた。
「苦労なされたようですな」
尚香の視線は下に落ちたまま動かない。
やつれた頬に乱れた結い髪が落ちる。
「江東よりの旅路はさぞ険しかったことでしょう。お一人でよくぞここまで…」
「……」
「間者より知らせを受けています。呉国においては孫尚香はすでに亡き人であると」
「……」
「呉公にはお別れを?」
「ええ」
諸葛亮の胸中に哀愁と葛藤が渦を巻く。
今、彼は尚香への同情と共に、今後激化の一途を辿るであろう孫呉との駆け引きに思いを巡らせているのだ。
荊州の攻防。
目前に迫る漢中攻略。
孫権の思惑、尚香の節…
「…あえて聞きます」
何故ここへ?―――諸葛亮のその問いに、混濁しかけた意識がふいに覚醒した。
弾かれたようにその面を上げる尚香。
「皇叔の正室にはすでに呉夫人がおありだ。半月前に双子の御子もお生まれです」
「存じております、道すがら耳に致しました」
諸葛亮の眉尻がわずかに動く。
彼にとって孫尚香のその応えは意外なものであったようだ。
「知りながらもなお此処へ来たと?……わからない、わかりませんね呉妹様、貴女のお心、」
言いかけ、そして奇妙に感慨深げな面持ちで、青い瞳を見遣る“月”。
「呉妹様…いえ、孫尚香は死んだのでした。今の貴女は名を持たぬ者」
月の引力が尚香の内に既視感を呼び起こす。
彼女の内側、音も無く満ちゆく青白い気。
「再びかの人の妻に…そのように望みここへ来た?」
“否”と頭を振る尚香。
「貴女は何者であるのです」
「……私は、」
「望みは? 願いは? 何が貴女をこの地に至らしめたのか、私は知りたいと思う」
月亮の言霊が尚香の“願い”に確かな輪郭をもたらす。
劉玄徳。
すべてさだめであったのだ。
かの人、金色の太陽こそが我が掟。
「私は士です」
尚香は言う。
己の内で長きに渡り相反し、克し続けた陰陽の気がついに太極へと至る。
「皇叔の士であり剣であるのです。願いは大漢の復興、劉皇叔の志こそこの身がここに在る理由……軍師よ、どうか、」
この身を生かし給えと告げ、諸葛亮の足下に膝突き深く頭を垂れていた。
臣下の礼。
劉備の理想を支え導くその人に、忠誠を捧げ、誓うのだ。
諸葛亮がその長身を屈めて尚香の手を取る。
静かに引き、立ち上がらせて、自身も深く返礼した。
建安二十一年三月某日。
成都の王宮に春の嵐が吹きつける。
黒く輝く大理の石が敷き詰められた宗廟に、風に運ばれ舞い落ちていく白い花弁。
「……」
独り廟内に佇み、風に舞う花弁を目で追う劉備。
過ぎゆく風の声を聞く。
強く、時に儚い音。
やがて雲間に明るい陽の光が溢れ、嵐は遠くなっていく。
宗廟を出、光溢れる庭へと降りた。
そしてから彼はまぶしい光のその先に二つの人影を見て取る。
長身の人影は己が股肱、諸葛亮へと変わりゆく。
「…!」
彼の傍ら―――黄金の髪、青の瞳。
左将軍府直属の武官の袍を身に纏い、彼女はそこに在ったのだ。
交わす眼差し。
思いのすべてが映し見える。
伝わる。
再び出会い、心と心とを寄せて、魂までも近くなる。
劉備は眼前で深々と臣下の礼を捧げる彼女に歩み寄り、自身もその場に膝を突く。
日射しの中、どこかまぶしげに劉備を見上げてくる彼女。
青と緑が重なる刹那、二人の胸に遥かに遠い日々の記憶が甦った。
江山の頂で見たあの暁光。
長江の蒼。
秋牡丹。
思い出は今なお金色であるのだ。決して色褪せはしない。
そして今、激情が、焦がれるような恋の炎が、静かに強い愛の光へ昇華する。
「玄徳様、否、我が君。お会いし、そしてお伝えしとうございました。私は新たに名を得ました。その名に従い士と成りてこの志を果たしていきたく思います」
「志…」
「志とは劉玄徳、貴方をおいて他にない。再び漢室を興し、太平と仁の世を築かんことを誓います」
「共に歩んでくれますか」
「どこまでも…我が君」
見つめ合う二人の頬をひとすじ、涙が伝っていた。
柔らかな風に乾いていく。
日輪と月は二度と離れることはない。
建安二十四年三月。
定軍山の戦いを経て、劉備・曹操両軍の攻防はいっそう苛烈さを増した。
漢水を挟んで対峙した両陣営の先鋒隊、趙雲と徐晃の軍。
相対してより三日目の晩、漢水の東岸に敷かれた徐晃の陣から突如として火の手が上がる。
瞬く間に四方八方から燃え上がり、風にあおられ業火となって魏の将兵を大混乱に陥れた。
「おぉっ…これは、」
剣を手に幕舎を飛び出した徐晃。
信じられぬといった様子で燃え盛る自陣を見渡し歯噛みする。
「なんたる事だ!」
ひときわ強い火柱を上げる糧秣庫。
兵糧も兵器も武具もすべて炎に呑まれていく。
やがて剣戟の音と矢羽の音とが闇に響き、恐慌状態の兵達が陣を棄て逃走を始めた。
「!!」
と、徐晃の眼前、どこからか飛んできた矢に胸を射抜かれ一人の兵卒が倒れた。
ハッとして彼方に目をこらす。
四方を囲む炎の赤に照らし出されたその黄金。
青い瞳がまっすぐ徐晃を捉えている。
「お、お前…!」
弓をかまえて立つその姿―――漢水進軍の直前に配下となった胡人の郷導使ではないか。
徐晃は瞬時に逆上し、対峙する金髪碧眼の将に向かって怒号を放つ。
「裏切り者め、この火はお前の仕業だな!」
「裏切る? すべては計略の内だ、はなからこうするつもりでお前の元に来たのだから」
「おのれ、貴様…何者だ!?」
「漢の王平」
名乗りを上げ、おもむろに手にした弓に矢をつがえる。
息を呑み、わずかに後ずさる徐晃。
降り落ちる火の粉―――視界がすべて赤になる。
「!!」
瞬間、キィンと高い音を立て、手にした剣が飛んできた矢に弾かれ宙を舞っていた。
衝撃に痺れた右手をかばう徐晃の目の前で、王平がフッと小さな笑みを見せる。数瞬ののち、身をひるがえして紅蓮の闇に溶けていった。
漢水の西岸。
燃え盛る対岸―――巨大な火柱となった徐晃の陣を無言で見据え佇んでいるのは、趙雲。
彼は漢水の流れに目をこらす。
今か、今かと、かの者の帰還を待つ。
「……」
と、突如、闇の向こうにボゥッと灯る赤を見た。
松明だ。
こちらに向かい近づいてくる船の上、火の灯された松明が大きく円を描いている。
「!」
戻ってきたぞ、やった、周囲の兵が次々歓声を上げる。
無事西岸に漕ぎ着く船。
魏兵に偽装し徐晃の軍に潜入していた味方の兵が戻ったのだ。
「趙雲殿!」
船から岸に降り立った王平が、趙雲に向け、手を振る。
「おお…王平殿!」
駆け寄り、互いに礼を交わす。
二人はその肩を並べ、赤々と燃える敵陣を彼方に見遣り、笑い合った。
「いやはや、なんとも威勢の良い燃え方だ」
「そうでしょう。油と火薬を嫌というほど馳走してやりました」
王平―――かつて孫尚香という名を生きたその将は、対魏の戦線において大功を成し遂げた。
その昔、彼女と趙雲の間にあった苦渋の日々も、今は無い。
理解し、受け入れ、認め合った。
理想を分かつ同志となっていったのだ。
二人の魂は共に劉備の夢を見る。
愛する人の剣となり、混迷の世を切り開き、光を手にしたいと願う。
曹操の益州侵攻―――それを見越した諸葛亮から命を受け、王平は一年あまりの時を費やし巴西と漢水流域の地理を徹底的に探索した。
土着の羌族に誠実をもって接し、協力を仰いだ上で此度の計略に臨んだ。巴の民として魏軍に雇い入れられて、目論見通り道案内の役に就く。
そして今、敵陣偵察と先鋒撃破の大任を同時に成して、王平は無事帰陣した。
趙雲に連れられ一年ぶりの帰還を果たした王平を、劉備はその目に涙を浮かべて出迎える。
「我が君、ただ今戻りました」
「王平、よく無事で帰った、まこと大儀であったこと…」
言葉に詰まり、袂で目頭を押さえる。
劉備のそんな姿を前に、誇らしげな、それでいてどこか照れくさそうな表情を浮かべる王平。
やがて涙を拭いつつ劉備が柔らかく笑えば、彼女もまた嬉しげに笑った。
「そなたの働き、その功は何にも勝る。王平よ、今日この時よりそなたを牙門将に任ず。この身を扶け天下の大義に尽くしてくれ」
主の言葉に拱手し「是」と応える王平。
青い瞳が希望の光に満ち、輝く。
願うものにはすべてなれる。
母と、師と、己を信じ励まして、その背を押してくれたのだ。
愛の形はひとつでないと、
絆はその形を変えてなお強くなることを知った。
新たな世界に愛する人と共に在る。
巡り合わせのすべてに感謝し、祈った。
続く
戻る