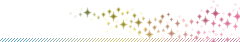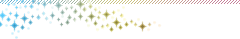
暁光・14
尚香は孫権を、孫権は尚香を沈黙の内に見つめ、そして多くのことを思う。
覚えておこう。
その眼差しも、耳も、口も、手も、すべて。
心に刻みつけておこう。
すぐそこ、二人の目の前に、今生の別れが迫っている。
兄と妹。
この瞬間、残されたわずかな時間が彼らにとってすべてなのだ。
「お前にはつらい思いをさせてきた」
孫権は言う。
悔いのにじんだその声で途切れ途切れに紡いでいく。
「国の為、民の為よと、そのように思いこれまで来た。だが俺はどこかで思い違えていた。焦りか、驕りか……わからん、今となってはこの俺自身にもわからぬ」
兄の言葉はか細く儚い糸ではあったが、しかし、尚香はその糸を確かに胸に手繰り寄せる。
「妹よ、公瑾を恨まんでやってくれ。苦しんでいたのだ、長いことずっと…」
「……」
「恨むか。俺を、公瑾を、憎いと思っているか、尚香」
尚香の唇が穏やかに深い笑みを刷く。
どこか安らぎさえはらむ。
「恨みはしません。無論憎いとも思いません。兄上、貴方は私に多くを与えて下さった」
多くの、本当に数多の世界を、景色を。
「私を気遣い、そして叱って下さった。私は長く貴方の心を無下にし粗末にしてきたのに、それでも貴方は私のことを想い続けて下さっていた」
「……」
「お許し下さい。我儘ばかり申しました。私は自分が思う以上に貴方を苦しめてきたのだと…」
「……」
「貴方は、公瑾は、いつでも寛大であったのです。私はいつでも傲慢でした。貴方の愛を足蹴にしながらそれに甘え続けてきた。お許し下さい、兄上、どうか」
伝える。
伝わる、心が通じたとわかる。
兄と妹は初めて互いの魂に真正面から向き合った。
「遠いぞ。お前の目指すところはあまりに遠い。それでも行くのか、尚香」
「行きます。必ず辿り着くでしょう。私は江東の雄々しき虎の妹です、誇りを失いはしません」
「そうか……そうだな、お前は俺の妹だ」
血と魂の絆は永遠のものだ。
決して消えることはない。
「たとえ名を変え国を変え、姿が変わったとしても、忘れはしません。貴方と長兄、母上、父上、すべて私の誇りです」
尚香は拱手し、孫権に向け深くその頭を垂れた。
孫権もまた妹に深い返礼で応える。
「さらばだ尚香、我が妹よ。健やかにあれ」
「お別れ致します、兄上」
こみ上げる熱さを堪えるようにきつく目を閉じる孫権。
彼は思い返していた。
遠く懐かしい日々の軌跡。
父と、兄と、母と、妹と―――おぼろげに、しかし確かにあった、あの安らぎと愛の日々。
(………)
再びその目を開けた時、尚香の姿はすでにその場には無かった。
月光と梅の香だけが知っている。
永の別れのひとときはあまりに穏やかで静かだ。
長江の祭壇に続く道を行く、呉妹・孫尚香の葬列。
空の棺の中にはただ小弓のみ納められる。
小高い丘の上に立ち、自身の弔いの儀を見送った。そしてから、尚香は彼方の建業城を見遣り、祈る。
兄に、多くの人々に、己を育み慈しんだ故郷の山河に別れを告げる。
とても言葉にはならない。
悲しみの記憶は掻き消え、切ないほどの愛おしさだけが残る。
―――と、踵を返し、一歩を踏み出したその時。
「あっ」
尚香は眼前に立つその人物に驚きの声を上げていた。
甘興覇。
忘れじの師がそこに在った。
「興覇…」
懐かしさのあまり胸が苦しいほどになる。
向き合う甘寧の瞳は静かに深い。
「蜀へと?」
「ああ」
「そうですか…かの地への道は険しく遠い。姫、どうか充分に気をつけて」
「ありがとう。大丈夫だよ、そなたに見送ってもらえる、私は心を強く持てる」
ありがとう、本当に。
多くを教えられてきた。
私を鍛え、この手に力を授けてくれた。
甘興覇。
我が師よ、お別れ致します。
「感謝している、心から。離れていてもそなたを思う」
「もったいなきお言葉…」
「なぁ興覇、私は強くなれたかな。私の剣は士のそれか?」
「…志は?」
「ある」
「道は?」
「見えている。進んでいきたいと思う」
「では、姫、貴女はすでに士であるのです。貴女は強い。望むものにはすべてなれる、必ず成し遂げられるでしょう」
甘寧は尚香を送り出す。
別れの言葉は希望の灯りに形を変えて旅立つ者の胸に宿る。
「姫、どうか御達者で」
「ありがとう、興覇…さらばだ」
今ならわかる。
師であり父であったのだ。
十三歳のあの日から貴方は私の指標だった。
遠ざかっていく尚香の背を見つめながら、甘寧の胸にもまた万感の思いがあった。
日輪と月の化身の娘。
初めてまみえたあの日から十年の月日が経っていた。
嵐のような道行きの先、金色の光があると思う。
志を果たせるようにと祈り、願う。
長江を西へと上る。
商船の中、人々の声に耳を傾け目指すかの地を思い描く。
甘寧の生まれ育った巴の地に降りた。
狭く険しい陸路を行く。
晴れの日も、時に雨の日もあった。
吹きつける風の激しい日もあった。
かの人、劉備が踏んだであろう道を踏みしめ、進む。
近づくほどに胸は高鳴り、恋の埋め火はその揺らめきを強くした。
(玄徳様)
江東でのあの三ヶ月。
瞬きのようなあまりに短い時間であったかもしれない。
だが、あの日々の記憶が今、尚香に確かな希望と力とをもたらしている。
愛する人の眼差しがその魂を強くする。
(あの三ヶ月、江東で過ごした日々こそ貴女と私の誠の時であったのだろうと思います)
劉備の言葉を思い出す。
反芻し、心に深く刻みつけた。
(会いたい)
劉玄徳。
貴方こそ我がさだめ。
この手も、力も、すべての理由は貴方に還る。
共に朝日の中に在った。
金色に染まる世界を教えてくれた。
尚香は望む。
魂の底から劉玄徳を。
資中の宿亭で一晩明かしたその翌日。
尚香は通りを行き交う商人達が景気の良い笑い声を上げる様子をなんとはなしに見つめていた。
靴紐を締め直しつつ彼らの言を細切れに耳に拾っていく。
「成都のお殿様」…「おめでたい」…
「…!!」
次の瞬間、ハッとしたように面を上げる。
尚香は背筋を走る悪寒に眉根を強く寄せていた。
(今なんと言った?)
つかつかと歓談する商人達に歩み寄り、強張る声で「もし、」と問う。
「その、今…申し訳ない、成都で何かあったのですか?」
漢服を纏う見目麗しい“胡人の男”が血相を変えて訊いてくるのに面食らった商人達ではあったが、ややあって愛想良く応じてきた。
「ええ、成都でね、益州牧の室に御子がお生まれになったのですよ」
「あなたも一度は耳になさったことがあるのでは? 先頃蜀に入られた劉皇叔のこと」
「めでたい話じゃありませんか、聞けば双子の男児だそうで。祝いの市も立つそうで商売人の我らとしても喜ばしい限りです」
全身の血が凍りつくような感覚。
尚香はその面を蒼白にして立ち尽くす。
異変に気づいた商人達が「どうなすった」と口々に声をかけてくるが、その声もどこか風鳴りのごとく響く。
ふらつく足で通りを一歩、踏み出した。
かき乱された思考のままで歩み行く。景色も、何も目に映らない。
商人達の言葉が脳裏をぐるぐる回る。
益州牧の室、
皇叔の妻、
双子の男児、
―――悪い夢でも見ているような思いがした。
(違う、まさか、)
そんなことが、どうして。
嘘だ、そんなと、独り胸中で繰り返す。
巴の地を黒雲が覆う。
雨粒がポツポツと黄金の髪に跳ね、やがて激しい雨脚に変わる。
雨に打たれてなおその足は止まらない。
頬を流れる雨の雫は尚香の心が流す涙であったかもしれない。
悲痛な魂はただひたすらに前を目指す。
ぬかるみに足を取られ、倒れ、泥にまみれてそれでも尚香は歩いた。
(会いたい。会うのだ、私はきっと、)
かの人の在るところ、成都を目指し暗闇の中を進んでいく。
劉備と呉香蘭の間に劉永・劉理の双子が生まれたその日から半月の時が経っていた。
続く
戻る