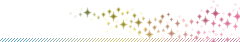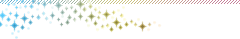
暁光・13
建安十九年五月。
二年半余の攻防を経て、ついに劉備の入蜀は果たされた。
その翌年、劉備・孫権両陣営は、荊州南部の領土を巡り武力衝突へと至る。
幾度かの戦闘、交渉を経て、劉備と孫権は再び同盟を結んだ。和議の条件は南部の分割譲渡である。東の三郡、長沙・江夏・桂陽は孫権に。そして西の三郡、零陵、武陵、南郡は劉備の手に。
両陣営の駆け引きは次第に血の色を帯びる。
剣戟の音は止まず猜疑と憎悪は日に日に膨れ上がっていく。
建安二十年十月。
孫尚香は病に伏した母・呉栄の寝所に在った。
窓の外、飾り格子の向こうから、鳥のさえずりが聞こえる。
尚香は目を閉じ、その声に耳を傾けた。
羽ばたきの音。
次いで静寂が訪れる。
「……」
目蓋を上げて格子に透ける光を見る―――そしてから、ふいに穏やかな視線を感じ、傍らの寝台に目を向けた。
仰臥した母が静かに己を見つめている。
立ち上がり、卓上の盆に張られた水を綿布に含ませ母の唇を湿らせてやる尚香。彼女は牀を呉栄の枕元へと引き寄せて、再びそこへ腰掛けた。
そんな娘へ呉栄が痩せた左手を伸ばす。
尚香は母の手を取り、両手で包み込むように握った。
「何か欲しいものは?」
娘の問いに、微笑みながらゆっくり頭を振る呉栄。
母娘はしばし無言の問いかけを続ける。
子は母に、母は子に、
喜びのこと。悲しみのこと。苦しみのこと。そして…
「遠くにあっても思いは尽きぬようですね」
唐突にも思える呉栄の言に、尚香はその目をわずかに見開いた。
沈黙の後、彼女はどこか寂しげに笑う。
母は娘の寂寥を知る。
虚しく、そしてひどく哀しいことと思う。
今の娘には何も無い。
日輪の熱も月の気高い光も、すべて。
「そなたが生まれた時のこと、生まれる前の夢のこと、私は何度も話し聞かせてきましたね。覚えていますか、尚香」
「ええ、母上」
「父上はそなたに会いたがっていた。生まれ来る日を本当に楽しみにしておいででした」
父が死なずにいたならば。
今もって孫文台が江東を統べていたならば。
もしやの夢、叶わぬ物語ではある。
しかし、もし父が生きていたのなら―――その時は長兄・孫策、次兄・孫権のさだめは大きく変わっていただろう。無論尚香の生もだ。
生と死と、人と人との巡り合わせと、思う程にこの胸の苦しさはいや増していく。
「私も父上もどれほどそなたの顔を見る日を待ち焦がれたか。私の尚香、可愛い子よ、そなたには自由に生きて欲しかった。自由に、ただ幸福の内に、尚香、」
母の手に力がこもるのを感じる。
「母上……私は、」
かすかに震える尚香の唇。
青い瞳にうっすら情動が宿る。
「不肖の子です。一体私は母上と父上の思いをどれほど無下にしてきたことか。お許し下さい、母上、私は何にもなれぬのです。愚かで…こんなにも愚かな、」
「愚か? なぜそのようなことを、尚香。そなたは決して不肖の子でも愚か者でもありません」
「……」
「何にもなれない、そう思うのも間違いです。そなたはなれる、何にでも。願うものにはすべてなれる」
「……」
「孫尚香、愛する子よ。自分を愚かと思わないでおくれ、それはとても不幸なことであるのだから」
「……」
「信じなさい。信じて、そして生きるのです。必ずなれる。望むもの、願うものには、すべて」
「…母上、」
「私の尚香。どうか幸福であるように。どこにいても母はそなたを思います」
数日後、季節外れの粉雪が舞う秋の日に、国母・呉栄は長い旅路へと発った。
二ヶ月後―――明けて建安二十一年正月。
国中が呉栄の喪に伏し静寂が支配するその中を、尚香は独り長江に向かい歩み行く。
岸辺に立ち、携えた白椿の枝を流れに投じ、祈った。
手向けの花だ。
母の元へと届くように、その傍らでいつまでも白く美しく咲き続けるようにと願う。
霜を踏み、江山へ登った。
かつて劉備と暁光を見たあの頂き。
記憶は鮮明に残る。
これほど遠く離れてもなお彼との日々は極彩色でこの胸の内に甦る。
冬の真白い静けさの中、尚香は独り、在る。
宵闇が降り、やがて瞬きだす星々。
いつしか尚香は月光の内に幻を見ていた。
(公瑾)
周公瑾、今では遠いかの人の懐かしい顔、笑い声。
なぜだろう。
あれほど憎み軽蔑していた、だのに。
(会いたい。もう一度会って話がしたい。公瑾、貴方はあの時私に何を言おうとした?)
ふいに激しい悔恨が尚香の胸に押し寄せる。
あの日、己が周瑜にぶつけた辛辣な言を思い返してのど奥をカッと熱くした。
なぜだ、なぜあのように酷いことを、
苦しげな周瑜の面を思い出すだに心が痛む。
(聞けば良かった。語れば良かった。もう遅いのだ、公瑾、二度と貴方には会えない)
まことの心を告げられぬまま二人は死に別れていった。
憎しみと苦しみと、そしてそれ以上に互いを結ぶ確かな絆があったのだと今、痛い位に理解する。
私は貴方を兄と慕った。
貴方は私を妹のように見守り導いてくれた。
なぜ勇気をもって言葉を交わさなかったのか。悔やんでももう戻れない。あの日にはもう、二度と。
(玄徳様!)
今なお焦がれ、欲してやまぬあの眼差し。
そうだ、あの夜もやはり己は何も言えぬまま別れていってしまったのだ。
星のきらめきを映した青がふいに涙を溢れさす。
遠い周瑜へと詫びる。
貴方の、己自身の苦しみと真正面から向き合うべきであったのだと。
彼方の劉備に呼びかける。
あの夜、私は貴方に告げたい真の思いがあったのだと。
言うべきだった、伝えるべきであったのだ。
凍えた心の奥底にあるかすかな熱こそ真実だった。
朝日が昇る。
いつかのように金色の光と共に在る。
まぶしい輝きの向こう、懐かしい劉備の笑みを見た。
愛する人よ。
もう一度会い、その声を聞き、そして告げたいことがある―――尚香の胸に宿った金色は静かな、しかし確かな決意へ変わる。
二月。
梅香る中庭にぼんやりとした眼差しを向けながら、孫権は私室に独り居た。
燭台に灯火のゆらめきは無く、ただ宵闇の静けさだけがそこにある。
「……」
ふと、彼は御簾の向こうに視線を向け、そしてから独りごとのように言った。
「来たか」
思ったよりも遅かったな―――そう続ける孫権の眼前、姿を現した尚香。
今はもうこの世に二人きりの血族、血を分けた兄と妹が、静寂の内に向き合った。
「行くのか」
兄の問いに小さく頷いた尚香。
わずかな逡巡のひと時。
月の光は別離の庭を音も無く照らし出す。
続く
戻る