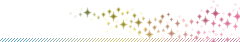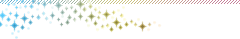
暁光・5
彼、否、彼女の名乗りに劉備はその目を見開いた。
予想だにしない邂逅に動揺を覚える。
孫尚香もやはりうっすら緊張の面持ちではあるが、努めて平静を装い、劉備の前へと歩み寄った。
傍らに立つと互いの目線がほとんど同じ高さにあることがわかる。この身長が劉備に尚香を少年武将と思い違わせていたのだ。
と、尚香が二つに裂かれた石を見下ろし問うてくる。
「何故にお斬りあそばした」
純粋に疑問に思って出た言葉だ。
「願掛けをしていたのです」
「願掛け?」
「私は齢四十九になりますが、未だ本懐は成らずいたずらに月日を重ねゆくばかり…今日この時、我が志が天に通じたものならば、逆賊を討ち漢室を再興出来たものならばと、そう願いを掛けてこの石を斬りました」
「なるほど。皇叔の願いは天に通じたようですな」
劉備の剣の一閃によって斬り開かれた断面を見る。しばしの間石を睨めつけていた尚香であったが、つと腰の長剣を引き抜き頭上に高々と掲げた。
白銀のきらめきがヒュンと鋭く空を裂く。
「おぉ…!」
劉備の口から感嘆の息がもれる。
尚香の振り下ろした剣は、劉備のそれに重なって深々とした十字の跡を石へと刻みつけていた。
「……斬れた」
まさかの思いが滲む声。
尚香は剣を握った自身の手指がかすかに震えるのを感じた。
月光に照らし出された十字紋石。
劉備の瞳の深緑と尚香の瞳の青とがお互いの光を捉え、不可思議な兆しを予感する。
「……」
ふと我に返ったように劉備から視線を外し、二、三歩後ずさる尚香。
抜き身の剣を手に下げたまま踵を返し、足早にその場を立ち去っていった。
闇の向こうに消えゆく背中を見送る劉備―――その面には虚無と困惑とが入り混じった複雑な色が浮かんでいた。
彼の後ろに立つ趙雲。
秀でた目元にかすかな煩悶が宿る。
劉備と孫尚香の婚礼は贅を尽くした盛大なものとなった。
城を挙げての華やかな宴。祝辞の声と歌舞音曲はいつ終わることなく続いていたが、夜の更けるにつれ参列の客人達も三々五々に散っていく。
やがて、二連の紅燈が彩る城の大広間を静寂が支配した。
深紅の婚礼衣装を纏った花婿と花嫁は、秋風が揺らす燈籠の音にじっとその耳を傾ける。
しばしの沈黙を経て、劉備は尚香に向け「赤壁の折は、」と口を開く。
「船軍に出ておいでで?」
「いえ、敵本陣を焼いたのち烏林へと出向いておりました」
「そうでしたか。昔から南船北馬とは言うものの、江東の兵はなかなかどうして陸上の戦も強い」
「劉皇叔は北のお生まれと聞きました。河北はやはり馬術が盛んであるのでしょうか。匈夷の馬をご覧になられたことは?」
尚香の問いを受け、生まれ故郷の景色を淡々と言葉少なに語る劉備。
乾いた風。
黄土の砂塵。
異国の人々が行き交う通り。
そしてから彼は尚香に問うた。生まれてからこれまでに見た風景を、人のことを。
尚香は語る。
長江の青。
果ての見えない大海原。
焼けつくような夏の日射しと花々の彩。
時を違えて北と南の地に生まれ、数奇な巡り合わせによって二人は今、ここに在る。
城を抜け出た劉備と尚香は、馬を駆り甘露寺の立つ江山へ登った。
「何を願われたのですか」
背後の劉備のその呼びかけに、尚香はおもむろに振り返る。
「何を、とは…」
「あの晩、石を断ち斬られた。やはり貴女も願掛けを?」
口ごもる尚香。視線が泳ぎ、どこか落ち着かぬ風だ。
「願い…私は…」
「?」
「その……わ、わかりません」
「…わからない?」
「わからぬのです。なぜ斬ったのか、なぜ斬れたのか」
少女の面には明らかな焦燥の色が浮かんでいる。
「何を言うかとお思いでしょう。いや、お笑いあるな劉皇叔、本当にわからないのです。私の中には何も無い、願いも、そして志も」
「……」
「己自身、何を思って今の今まで生きてきたのかわからない。最近つとにそう感じます。拠り所なく剣を振るってきたようにも思う…」
「…武の道は貴女にとって一体なんであるのです? 剣と弓とは真に貴女を生かせるものであるのですか」
「真に…? いえ、今となってはそれすらもよくわかりません。ほんの幼い時分から刃の輝きに惹かれていたのは確かです。しかし、別段己の筋としてきた訳ではない」
ああ、一体私は何を言っているのだろうと、尚香は肩の力を落とす。
「皇叔、貴方もすでにご存知の通り、私は刺客であったのですよ」
「……」
「貴方を殺せと、そのように兄から命を受けていた。こうして貴方に面と向かって打ち明けることも、兄への、そして国家への重大な裏切りであるのでしょう」
「……」
「貴方が喬国老と母とをたきつけこの計略を破って下さったことに、私は正直感謝している。心底ホッとしましたよ、これで私も死なずに済んだ、ああ良かったと……なんとも情けない話だ」
「……」
「私を軽蔑なさいますか。半端者だと、愚か者だと思われますか」
「いいえ」
「……」
「軽蔑はしません。愚か者とも思いません。尚香殿、貴女は随分と長くお苦しみであったのですね」
尚香はハッとしたようにその顔を上げ、劉備を見遣る。
そのまなざしは劉備の内に既視感を―――かつて見た少年の姿を思い起こさせた。
少年は、齢十五の趙子龍。
青春の嵐の中にその魂をさ迷わせ、見えない明日に怯えて立ち竦んでいた。
今、眼前の尚香の青い双眸に、遠いあの日の趙雲のすがるような瞳の色を重ね見る。
(同じだ。苦しんでいる。己の道行きに迷い、怖れて、魂をすり減らしている)
この瞬間に至るまで、劉備もやはり苦しみの内に在った。
計略によって引き合わされた少女と何を語り、どのような心でもって接したらよいものかと、思い悩んで苦しんだのだ。
鴻芙蓉の死と共に自身の愛もまた潰えた。
潰え、ひび割れ、枯れた心で一体なにを愛せよう。
だが今自身の目の前で、ひとつの若い魂が煩悶し闇を彷徨っている。
必要なのは虚無ではない。
伝えるべきは絶望ではなく希望と誠実であるのだと、劉備は自己に言い聞かせる。
「尚香殿、剣がお好きか」
「己の質に合っているとは思いますが……まぁ、その……好きです、ええ」
「戦がお好きか」
「戦? 楽しいものではありません、好きになることなどないでしょう」
「死が恐ろしいとお思いか?」
「む、無論…」
「私もです。私もやはり戦と死とが恐ろしい」
「貴方が…? 貴方は長きに渡り戦の庭に在られたはずだ、それだのに、」
「確かにそうです。戦の中であまりに多くの死を見てきた。だがしかし、人の死に心が慣れることなど決してありはしない」
「……」
「貴女は私を臆病者と思われますか」
「…いいえ、皇叔」
「死にはなんらの意味も無い。そこに理由をつけたくはない、納得したくはないのです。生きたいと思う、生きてさえいれば道は開ける、そこに願いと志とを見い出せるのだと私は思う」
言霊は若い魂に波紋と共鳴をもたらす。
尚香は己の内にくすぶり続けてきた埋もれ火が音もなく燃え上がるのを感じていた。
深緑の双眸に宿る静謐な熱。暗闇の中でもハッキリ見える。
心が通じたとわかる。
十七歳の魂が願う。知りたいと、貴方のことを、自身のことを。
知って欲しいと切に願う。
やがて東の空の彼方に金色が宿り、暁光が江山の頂に立つ孫尚香と劉備を鮮やかに照らした。
まぶしさの中、尚香は“自己の夜明け”を知覚する。
続く
戻る