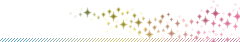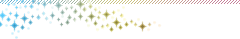
暁光・3
「何故にまたそのような…」
尚香は戸惑いがちな声音でもって兄に問う。
確かに己はもう十七、嫁に行こうが婿を取ろうがおかしくはない年となった。
だが、なぜ相手があの劉玄徳なのか。
正直訳がわからなかった。
何よりも、幼少の頃より剣と戦の世界に在った少女にとって、「結婚」の二文字はあまりに現実味の感じられない言葉であった。
「…まあ、なんだ、その」
思い違いをするなよと前置きをして孫権が言う。
「結婚とは言うがな、それはあくまで名目に過ぎん。建前上、劉備の気を逸らせる為だ」
「名目? 建前?……おっしゃる事がいまいちわかりかねますが」
「うむ……ではこの際ハッキリと言おう。妻として彼奴めの室に入り、隙を見て首を取ってこい」
「なんと!」
尚香は驚きに目を見開いた。
「私に刺客になれと仰せですか」
「む、いや…刺客だなどと人聞きの悪い」
「…それは兄上のお考えですか、それとも公瑾の策、」
「余計な詮索は無用だ! 尚香、これはそなたの武を見込んでの計略である。考えてもみよ、合戦しいたずらに兵を損なうよりもそなたの剣の一振りで劉備を仕留めるが遥かに良策ではないか」
孫権の語気は荒いが、そこには多分に迷いと後ろめたさがにじむ。
“兄”と“呉公”、ふたつの立場で揺れ動く彼の心情は尚香にも容易に感じ取れたが、しかし…
「…たとえ劉備を討ったとしても、その時はこの私めも生きてはおれませんでしょう」
尚香のその言に、孫権と周瑜の面がかすかに引きつった。
確かにそうだ。劉備の周りには数多の戦場を駆けた一騎当千の士が集う。刺客の務めを果たしたところで尚香を待つのはただ死の運命のみだ。
(これが、このようなことが私のさだめであろうとは)
天を仰いで嘆息し、呉公の書斎を辞する尚香。
(………)
晩夏の濃い影の落ちる回廊を独り行く。
兄の言葉は至極もっともだと思う。戦によって兵を失い国を疲弊させるよりも、己と劉備が相打ちになれば話は早いというものだ。
(ですが兄上、劉備が死のうが私が死のうが彼奴らとの戦は決して避けられますまいぞ。ただそれが遅いか早いかの違いだけ………ああ、虚しい、悔しい! なんと馬鹿げた話だろう!)
言葉にならない憤り、苛立ちが、少女の内に渦を巻く。
(私はこの江東、故国と民の為死ぬのだ! 父と長兄と同じに国家の礎となるのだ! なんと喜ばしいことではないか、なんと…)
自嘲する。
もう何もかもどうでもいいとすら思う。
自室に戻り愛用の剣を掴み締め、やり場のない怒りにその身を焦がす。
(何を嘆く、孫尚香、これが己の選んだ道であるのだろう。剣に生きる事こそ本懐であると信じて生きてきたではないか)
必死になって己に言い聞かすほどにやりきれなさは増していった。
翌日、南徐の城の一角で、周瑜は尚香と出くわした。
昨日の件の気まずさからただ黙って礼をし道を譲った周瑜ではあったが、すれ違いざま尚香が放ったその言葉に思わず立ち竦んでしまう。
「己の妻の為になら大軍を出すことも辞さぬ貴公が主の妹は平然と死地へ送り出すのだな」
淡々とした、しかし確かな怒りのこもった声音。
周瑜はしばし呆然として遠ざかる尚香の背中を見送っていたが、ふとした瞬間、胸に激しい痛みを覚え咳き込んだ。
人目を避けるようにして物陰にうずくまる。
「…!!」
ゲホゲホと嫌な咳が続く。
ややあって口元を押さえていた手に視線を落とした周瑜は、愕然とその場に凍りついた。
赤黒く染まった己が掌。
唇も、華奢なおとがいも、べったりと血に濡れていた。
九月に入り、公安の劉備のもとに江東より“呉妹・孫尚香との縁談”が持ちかけられた。
紅の絹布につつまれた書状を手に、微苦笑を浮かべつつゆるゆるとかぶりを振る劉備。
「また突飛な策を仕掛けてきたものだ」
諸葛亮は主から手渡された書状にサッと目を通す。
「………」
しばし羽扇をたゆたわせていたが、やがて居ずまいを正し、劉備に向け「お受けなさいませ」と告げた。劉備の面があっけにとられたようになる。
「受けよ、とは……孔明、これは孫呉の策略ぞ。そなたとてわかっていようものを」
「無論先方の思惑は重々承知の上のこと。我が君、ここは策略に乗るふりをして相手の裏をかいてしまえばよいのです」
「裏をかく?」
諸葛亮の唇にフッと冷たい笑みが浮かぶ。
「ご案じあるな。何もかもよろしいようにしてみせましょう。しかし周瑜という男は見下げ果てた愚か者ではありますな…よりにもよって主筋の女を美人計に用いるなどと」
「……」
諸葛亮の羽扇―――彼が江東に赴く直前、劉備より贈られた守りの品だ。劉備は今、眼前の純白の揺らめきをどこか虚ろな眼差しで見遣る。
この瞬間、彼の胸中に去来する、亡き妻・鴻芙蓉と二人の娘、劉永・劉理らの面影。
生涯をかけて愛した女と血を分けた娘達の死から一年の月日が過ぎていた。
続く
戻る