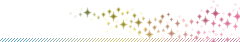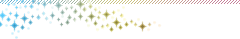
暁光・1
◆孫尚香(192年生)
◆甘寧(166年生)
◆呉国太が孫策・孫権・孫尚香の生母です。
初平三年・春。
呉郡曲阿の地において孫堅の第三子・孫尚香はその産声を上げた。
父親の死から三ヶ月後のことだった。
「奥方様、お嬢様ですよ、まぁなんて元気でお可愛らしいことでしょう」
侍女の言葉に呉栄はホッとしたように息をつき、そしてから小さく微笑んだ。
「……」
産褥の床で生まれたばかりの娘の泣き声を聞きながら、呉栄はかつて亡夫と交わした不可思議なやり取りを思い出していた。
それは先年、呉栄が夫に“ある夢の話”をした時のことだ。
(この子を身ごもりました時、天から日輪と月とが私の腹に落ちてくる夢を見たのです。何かの兆しであるのでしょうか)
身重の妻のその問いに、孫堅は明るい声で答えたものだ。
(奥よ、腹の子は必ずやひとかどの人物となろうぞ。日月はこの世の理、陰陽の精髄を極めた高貴の人の兆しであろう)
日輪と月の化身に早く会いたいものだと黄金の髪を陽射しにきらめかせながら笑った最愛の人も、今はもう彼方に去って帰らない。
ふと、呉栄の胸に惜別の念が押し寄せる。
亡き父の魂を引き継ぐようにこの世に生まれ来た命―――その生気に満ちた泣き声は、彼女の内に宿った哀愁を明るい春の色へと塗り替えていった。
孫家の末子・尚香は、果たして日輪と月、陰陽ふたつの性を合わせて生まれた者であったようだ。
上の二人の兄達同様、孫堅ゆずりの金髪碧眼と人並み外れた武人の質を持っている。幼い頃より剣と弓術に親しみ、季節を問わず水練に励んだ。
十歳上の孫権は闊達な気質の妹にそれほど干渉することもなかったが、建安五年に兄・孫策が不慮の死を遂げた後は、事あるごとに「剣を捨て家に入れ」と孫尚香に説教をするようになった。
それはひとえに兄として妹の身を案じる心から来るものであったが、当の孫尚香はひたすら疎ましがるばかり。
時に二人は母・呉栄の眼前で盛大な兄妹喧嘩を演じることすらあった。
「尚香、お前はなんて聞き分けのない! まったくこの性悪な子虎めが!」
「ええそうです、私は虎の子、たとえ兄上にだっておいそれと捕まるものですか」
虎狩りを趣味に持つ孫権に対し、からかうような口調でもって言い返す。カッとなった孫権が掴みかかってくるのをひらりと避けて卓上に飛び乗り、母親の部屋をあちらこちらに逃げ回った。
その後をバタバタ追いかけ回した挙句に息切れを起こしてしまった兄に「失礼します」と舌を出し、窓から逃げ去る孫尚香。
床に膝をつきうなだれる孫権。呉栄はやれやれと言わんばかりに頭を振ってため息をついた。
孫尚香の内には自身にも皆目見当のつかぬ煩悶と焦燥があった。
若くして志半ばに死んでいった父、長兄――――彼らの存在は物心ついた頃から尚香の道行きに大きな影を落としている。
彼らと同じく己も長くは生きられまいと、漠然とした思いを胸に少女は日々を過ごしていた。“死”に甘美を見出すほど退廃的な思考は持っていなかったが、それでもやはり“生”に対して子供らしからぬ懐疑を抱き続けている。
尚香、このひねくれ者めと次兄が浴びせてくる怒声を思い返しては(私はひねくれているのか?)と自問し、(そんなはずはない)と自らにまた言い聞かせる。
そんな葛藤からわずかに解放されるのが剣を振るっている瞬間だ。そして剣と槍とが切り開く先には間違いなく血濡れた終焉が待っていることも知っている。
死は恐ろしい。
終焉は望まない。
しかし、今日も己が手は剣を握って弓の弦を引き絞る。荒ぶる心が欲するままに少女は武の道を極め続けた。
建安十年。
この年、孫家の宿敵ともいうべき黄祖の陣営から出奔した武人が一人、江東の地に身を寄せる。
その武人―――甘寧興覇は、寡黙でありながらも周囲を圧倒する凄味を纏った長身の男だった。
十三歳の孫尚香と流浪の士・甘興覇。両者の間に生まれたものは、決して人には解されぬ孤独と焦燥を抱えた者同士が共有する“感傷”であったのかもしれない。ともあれ、尚香は甘寧を武芸の師と仰ぎ、彼に付いて頻繁に賊徒の討伐に出ることとなった。
長江沿岸に跋扈する賊の掃討から帰還した将兵をねぎらう孫権は、甘寧の傍らで具足についた返り血を拭う妹の姿にあからさまに眉をしかめる。
兄の不興を前にして平然とした様子の孫尚香。
甘寧もまた、兄妹の軋轢にこれといった反応は示さなかった。
「よく手懐けたものだなぁ」
甲板の上、帆柱に寄りかかったまま尚香が言う。
視線の先にいるのは一羽の子烏を腕に乗せ、何事か話しかけている甘寧だ。
彼は尚香を見やり、フッとかすかな笑みを向けてきた。
「そなたの家の軒先で鳴いていただって? 親の烏は一体どこへ行ったのか…」
「親の姿は辺りには見えませんでした。迎えに来る様子もないし、まぁ、成り行きで飼ってみただけです」
「興覇に子供を押しつけていったのか、あきれた親もいたものだ」
尚香の言葉にうなづくように子烏がカァカァと鳴く。
ヨタヨタとおぼつかない足取りで甘寧の腕から肩へと這い上り、首の近くでうずくまった。
厳つい容貌の武将と小さな烏の取り合わせがどうにも可笑しく感じられ、尚香はクスッと小さく笑ってしまう。
甘寧自身も可笑しさをこらえきれないようで、その口角がいつになく大きく上がっている。二人は互いに声を殺して肩を震わせていたが、ふいに船首より響いた「右岸の五里先、賊の船団が見えます」との声に瞬時に口元を引き締めた。
矢筒を革帯に備え、小弓の弦の張りを確かめる尚香。種々の暗器…十三歳から甘寧に厳しく指導された武具の装備を済ませたところで、背後から「よろしいですか」と声をかけられた。
振り返り、「大事ない」と甘寧に返す。
「連中との水上戦は陸上のそれの何倍も危険だ。くれぐれも無茶はなさらぬように」
「ああ、わかっているよ」
「足場の確保には充分に気をつけて」
「ああ」
手甲の紐を締め直す孫尚香を前に、(この二年で姫も随分と背が伸びた)と場違いな感慨にふける甘寧。
今年で十五歳になる孫家の姫君は、市井の人々に畏怖を込めて「弓腰姫」の名で呼ばれるようになっていた。亡き先代・先々代のそれとそっくり同じ勇猛果敢な戦ぶりは、ある種の刹那をはらんだものであるように甘寧の目には映る。
血と刃の飛び交う戦の庭に、この少女は一体何を見出そうというのだろうか?
「…姫、あまり、」
「ん?」
「あまりお命を粗末になさいませんように」
「なに……ハハ、興覇らしくもないことを言う」
「私は別段死にたがりではありませんよ」
「私とてそうさ、出来れば長生きがしたい。父や兄の轍は踏みたくないんでね」
「……」
「案ずるな。私には、そう…母上がおっしゃっていたんだがな」
「?」
「私にはな、興覇、日輪と月のご加護があるのだそうだ」
「日輪と月の?」
「私を身ごもった時、母上が夢を見られたそうだ。日月が腹に落ちてきて…まぁ、そういう訳さ」
なるほど、とひとつうなづいた甘寧。
尚香の顔は初の賊徒相手の水上戦を前にした者とは思えぬほどに晴れやかなものだ。
「興覇よ、そなたにもやはり日輪のご加護があるぞ」
「私にですか?」
「さしずめあの子烏は天上よりそなたの元へと遣わされた金烏の化身であろうよ」
「ほぉ…フフ、なるほど」
蒼天を支配し照らす太陽の中には三本足の金烏が住まう。
二人は再び笑い合い、そしてから、船首の先に見えてきた水賊の黒い軍船に向き直った。
四肢に破壊の衝動が宿る。
尚香と甘寧を乗せた戦闘艇は水上を加速し死地へと突き進んだ。
兄・孫権の意向はどうあれ、尚香は日々確実に実戦の経験を積み戦功を重ねていく。
現場の将兵にとって呉公の妹君はまぎれもなく“優秀な戦力”だった。一度たりとも軍議を欠席することなく、さりとて指揮にあれこれ口を出すこともなく、ただ黙って与えられた任務を着実に遂行していく弓腰姫。彼女は極めて特異な存在でありながら、ごくごく自然に呉の軍営に馴染んでいった。
そして建安十三年九月――――夏口の劉備と孫呉との間に対曹操の同盟が結ばれ、江東の地は一気に戦時下に置かれることとなった。
十六歳の孫尚香は従来通り“無官の将”として大都督・周瑜の指揮下に入り、連日軍議の席に連なる。
(………)
水軍の配備に関する周瑜の言に耳を傾けながらも、尚香の視線は斜め向かいの道服の青年へと向いている。
純白の羽扇を手にした端正なその容姿―――劉備のもとから参謀として出向している諸葛亮だ。
彼が江東に赴いてから早ひと月。直接言葉を交わすことなど決してありはしないのだが、尚香はなんとはなしにこの青年を(苦手だ)と思うようになっていた。
静謐な水面のような美貌の裏に、何やら得体の知れないものを秘めている…訳も無くそんな思いに囚われ、心が薄ら寒くなってしまうのだ。
血と刃に彩られた青春、その只中を生きる十六歳の少女は、泰然自若とした佇まいの内に人一倍過敏で繊細な“本能”を隠し持つ。それはまた“直感”とも呼ぶべきものだ。
孫尚香はその直感で諸葛亮という人物に不穏の兆しを感じ取った。
(諸葛亮……この男は)
この男は、月だ―――脳裏にふっと浮かんだその言葉に、尚香はかすかな動揺を覚える。
自己に宿った“月の陰”が同類の匂いを嗅ぎ取ったのか?
異質であり、異形である。
青春の嵐は尚香の煩悶を増幅させていく。
続く
戻る