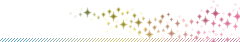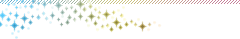
日蝕・7
劉備とその子供達、親族らは、公安城の行政府にほど近い区画に居を構えている。この日、祝いの品への礼を述べるため劉備のもとを訪ねた魏延であったが、未だ城内の間取りに不慣れなこともあり、うっかり奥の間へと迷い込んでしまっていた。
どうしたものか、案内を頼めば良かったかとまごついていたところ、生け垣の向こうからふいに幼い歓声が響いてきた。
見れば、中庭に赤子が一人、土の上をついばんで歩く鳩の後ろをヨチヨチ這って追っていた。鳩の仕草が面白くてならぬのか、キャッキャと笑い声を上げる。
「凍えてしまうよ、お待ち、阿斗」
赤子の兄とおぼしき少年が中庭へと降りてきた。
鳩を追うのを止めて兄の足にまとわりつき、甘えてくる赤子を胸元に抱き上げる。
魏延はアッと思った。あの少年には見覚えがある。主君・劉備の嫡男の劉封だ。
「…?」
弟をあやしていた劉封の目が、ふと、生け垣の向こうに立つ魏延の姿をとらえた。
「…あなたは確か、」
とっさのこともあり、なかなか新参の将の名前が出てこない。困ったような顔になる劉封に、魏延は慌てて頭を下げた。
この時、劉封は魏延より五つ下の十八歳。
三年後の益州攻略戦において、二人は共に武勲を掲げる盟友となる。
劉封に取り次いでもらったことで、ようやく劉備への目通りは果たされた。
「我が君、先日は過分なお祝いを頂きまして…恐悦至極に存じます」
「よい、よい。妻女と共に健やかにな。互いにいたわり幸多き家庭を築くのだぞ」
穏やかな笑みを浮かべて言う劉備。
その眼差しの奥に宿ったひっそりとした哀しみに、魏延は思わず口をつぐんだ。
そうだった、劉皇叔は先の長坂の一戦において、奥方様とお嬢様お二人を亡くされている……主君がその胸に秘めた悲哀を敏感に感じ取り、魏延の心もまた痛む。
「黄忠はそなたに期待しておるのだな」
穏やかな声で言う劉備。
「え…期待、でございますか?」
「大事な姪御の婿にと望んだのであろう?」
「はぁ…いやしかし、それがしごとき若輩者、」
「私もそなたに期待している」
魏延の鼓動が跳ね上がる。
一瞬、その胸の奥に、炎がカッと燃え上がるような熱い衝動を覚えた。
「こうして向き合っていると、そなたの炎の熱を感じる」
「…我が君、」
「今はまだ幼く、未熟で小さな灯火であるやもしれぬ。しかし、いずれは意気も盛んに燃え上がり、大きく伸びて、暗い道行きを明るく照らす光となろう」
「我が君、」
「決して戯言ではないぞ。そなたの澄んだ眼差しを見ると、私は遥か彼方に過ぎ去った若かりし日々を思い出す。青春の熱が甦るのだ」
嘘いつわりなき劉備の本心であった。
彼はまた、若き参謀・諸葛亮からも、魏延が胸に秘めたと同じ“灼熱”を感じ取っている。
諸葛亮と魏延。どちらも二十代の輝く青春のさなかを生きる若者だ。
彼らが持つ熱い心と純粋な理想とは、齢五十を目前にした劉備にとって、自らの志を堅固に保つ道標であったのだ。
壮年が青年を支え導くと同時に、青年が壮年を支え、励ましているのである。
「襄陽でのそなたの言葉を忘れたことは、玄徳、一日とてありはしない。魏延よ、私はあの時救われたのだ。さまよう我らを、民達を、見捨てはせぬと声を上げてくれる者が、まだこの世にはいたのだと……私は人を恨まずに済んだ」
その言葉に、魏延は思わず感極まって涙した。
あの血みどろの長坂の戦いで妻と血を分けた娘二人を失ってもなお、この御方は人を信じ、部下を労わることを止めぬのだ。
(この方だ、やはり、この御方なのだ! 劉皇叔をおいて他に天下の民を安んぜる者などいはしない、俺は皇叔の理想と大義の為ならば、この命すらも惜しくはない!)
「あれは、長坂は………あの時、私は人でなくなっていた。心を見失いかけた。魏延、そなたは私に人を信じる心を思い出させてくれたのだ。礼を言う…心から」
「もったいなきお言葉…我が君、魏延は今ここに、改めて我が君への生涯の忠誠を誓います。この命、髪の一本までも、すべてを捧げ奉ります」
「嬉しいことを…そうだ、私はそなたを信じている。期待させてくれ、魏文長」
劉備は足下にひざまずいた魏延の手をとり立ち上がらせた。
柔らかく冷えたその白い手の感触が、魏延にはなんとも心地良い。
頭ひとつ分高い長身の青年を無言で見上げ、劉備は自身の“熱”を、“志”を、幾度も反芻していった。
己をまっすぐに見つめてくる深緑の眼差しに魅入られて、魏延は身じろぎも出来ない。
やがて、どちらからともなく、手が動いた。
互いの背中に腕が回され、固く、きつく、抱擁し合う。
遠き洛陽での出会いから、十七年の歳月を経て成された邂逅。
幼かった子供は気高い理想に燃える武人に、青年はあまたの悲しみを内に秘めた乱世の雄となっていた。
決して思い出されることのない、陽炎のような儚い記憶。
だがそれは、確かに今この時へと続く、遥かな軌跡の始点であった。
去り際、魏延は、弟の劉禅を胸に抱えた劉封が、霜の降りた冬の庭をわらべ唄を歌いながら歩く姿を見た。
長坂の死地を父親と共に生き延びた二人の子供。
やがて魏延のその生涯を、愛と涙と憎悪をもって支配し、翻弄していく者達だ。
「おお、帰ったか」
公安城から帰宅した魏延に、庭先で矢羽の手入れをしていた黄忠が声をかける。
魏延は事実上の“舅”に歩み寄り、「戻りました」と一礼した。
「重々御礼申し上げたか」
「はい、我が君が舅殿にもよろしくと」
「舅?……フフ」
己の姪と娶わせた青年を一瞥する黄忠。
凄味のある、それでいてどこか愛嬌のある笑みをこぼし、再び視線を手元の武具へと移すのだった。
魏延の口元もうっすら緩む。
「…漢升殿は、」
「ん?」
「私に期待して下さったんですね」
「なんだ、いきなり」
「そうでしょう? 私を見込んで下さった、ですよね?」
「なんだなんだ、何を言い出すかと思いきや」
フフフと含み笑いして、黄忠は肩を震わせる。
嬉しげに、そして誇らしげに問うてくる魏延の額を、指先でチョイチョイつっついた。
「自信過剰な若僧は嫌いじゃないからな」
「ありがとうございます。期待して下さい、鍛えて下さい。弓だってもっと上手くなります、いつかはきっと漢升殿より上手くなります、だから」
「こいつ、言ったな。よし、忘れんぞその言葉」
信じ、信じられ、期待されることで大きく成長する魏延の質を、黄忠も劉備もハッキリ見極めていたのだろう。
冬の太陽。
その日射しは眩く澄んで暖かい。
続く
戻る