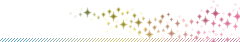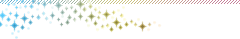
日蝕・6
◆夏侯蘭が夏侯夫人(張飛の奥さん)と兄妹です。
◆夏侯纂と夏侯博が夏侯蘭の従兄弟です。
◆魏延と黄忠が姻戚になっています。
魏延、劉備、諸葛亮。
今日この時、長沙の県城において四ヶ月ぶりの邂逅を果たした三者。
十七年前の洛陽の夜は記憶の底に埋もれている。
“二人の子供”も“椀の将軍”もそれぞれに歳月を重ね、姿形にかつての面影は欠片ほども見られない。
ただ、遠い昔に結ばれた縁が、どこか奇妙な郷愁を彼らの胸にもたらした。
「魏延、改めて礼を言うぞ。此度の戦、第一の功はそなたをおいて他にない」
「もったいなきお言葉…」
「これよりは玄徳のもとで存分にその力を奮ってくれい。のう、頼りにしておるぞ、魏延」
その頬を真っ赤に染めてハイと応える魏延の様に、劉備は愉しげな笑いを上げた。
青年のうぶな立ち居振る舞いが可愛く思えて仕方ないのか、口元を袖で覆っていつまでも肩を震わせている。
「わ、私はかねてより、政道を正し万民を安んじて下さる劉皇叔の御為にこそこの身を捧げ奉ろうと、そのように願っておりました…我が君、魏延は生涯、我が君に忠誠をもってお仕え致す所存にございます」
恥ずかしさと照れくささにその声をうわずらせながらも、思いの丈を精一杯に劉備へと伝える魏延。青年の真摯な心は劉備の内にじんわりと温かさを伴って染み渡る。
愛い奴、とつぶやく劉備の傍ら、諸葛亮の表情は固い。
右手の羽扇を揺らめかせつつ、魏延の頭から足先までをじっと睨めつける諸葛亮―――唐突に、硬質な声音でもって年下の武人へと問いかけた。
「そなた、蔡瑁のもとでは税官を務めていたとのことだが相違は無いか」
慈愛に満ちた劉備のそれとは正反対の、重く冷たい声だった。咎めるような響きを含んだその物言いに、魏延は思わず身を強張らす。
「は…相違ございませんが、」
税官の前歴が一体なんだというのだろう。汚職に関わった覚えは無い、やましい事など何ひとつとして有りはしないが。
魏延の面が戸惑いの色を履き、劉備もまた(何事か)といぶかしげな視線を諸葛亮へ向けている。
諸葛亮は詰問のような口調でもって、立て続けに魏延に問うた。問われる内容は税官の役務に始まり、襄陽において師事した学者、修学した法典、兵書、更には父・魏兆の官軍師範の経歴と、多岐に渡った。
口頭での尋問を終えたのち、諸葛亮は魏延を城の中庭へと連れ出し、幾人かの兵士を相手に組み手をするよう命じるのだった。
実父を師として魏延が修めた通背の拳は、戦国の末期に河北に起こって以来幾多の流派を生み出してきた極めて実戦的な武芸術である。その刀・剣・棍・槍の兵器術から五行掌三十六手の拳術までひと通りの演武を見、体系化された鍛錬法を魏延に述べさせた諸葛亮は、劉備へと向き直り、言った。
「この者に騎兵五十と歩兵二百からなる師団をお与え下さい」
その言にあっさりと頷いた劉備が、主簿を呼び寄せまたたく間に曲校の印璽を下す。かしこまって拝命しつつ、新たな緊張に背筋を伸ばす魏延。そんな彼を白い羽扇の毛先で指しつつ、諸葛亮は下命した。
「魏延、よくよく士卒を鍛え、精兵を成せ。三ヶ月の後に演習を行う、左様心得ておくように」
長沙を離れ、劉備に従って公安に入ってからは、軍属に関わる諸々の手続きや同僚への挨拶回りでアッという間に日が過ぎていった。
軍正・夏侯蘭より二日に渡って軍規の教授を受けた魏延であったが、同じく新参の黄忠共々、どうにも彼の“夏侯姓”が気になって仕方ない。
「腑に落ちません、夏侯といえばご主君の仇敵・曹操めの一族でしょう?」
「わしも不可思議に思うておった。どうも合点のいかぬこと……そうだ、おぬし、ここはひとつ軍正に正面きって尋ねてみてはどうだ」
「えっ、私がですか?」
黄忠から半ば強引にせっつかれた魏延が、夏侯蘭に(やや遠慮がちに)曹操との関係を問うてみたところ…
「そうですね。私の伯父というのが曹孟徳の従弟でして。ええ、確かに私は曹操の族子に当たります」
事も無げにアハハと笑ってそう言う夏侯蘭に、魏延と黄忠は思わず目を丸くした。
聞けば、夏侯蘭の実妹・夏侯蓮が、張飛の妻であるとの話。
先の博望坡の戦いにおいて、まったく偶然にも劉備陣営の捕虜となった夏侯蘭は、妹と共に劉備のもとで生きる道を選んだ。加えて、彼を捕えた趙雲とは同郷の幼なじみであるという。魏延と黄忠は顔を見合わせ、「人の縁とはまこと異なもの」と驚嘆の息をついた。
折りしもそこへ、長江沿岸警備の一隊が帰還する。夏侯蘭はその隊を率いる将を魏延と黄忠に引き合わせた。
「こちらは従兄の夏侯博です」
人好きのする笑顔を見せる偏将軍・夏侯博。彼と礼を交わしながらも、魏延達の面は驚きを隠しきれていない。
たたみかけるようにして、長史・夏侯纂と引き合わされた。彼もまた夏侯蘭の従兄に当たる。ほがらかで快活な人となりである。
夏侯博・夏侯纂ともに、劉備が許昌の曹操のもとに身を寄せていた半年の間に彼と親交を深め、ついには主従の契りを結んだとのことだった。
魏延は夏侯蘭に、曹操とのつながりを疑うような問いをしたことを素直に詫びた。
「軍正、大変失礼を致しました。先程はなにやら詮索するような物言いをしてしまい…」
「いやいや、ハハハ、かまいませんよ。我が君と曹孟徳の因縁を思えば無理からぬこと…しかし、我ら夏侯の一門が劉家をお助けすることになんの不思議がありましょう。かつて滕侯(夏侯嬰)は高祖を奉じ漢朝の礎を成しました。我々は祖先に倣いひたすら主に忠節を尽くすのみです」
「ごもっともです」
黄忠が、なんとはなしに夏侯蘭に問いかける。
「遠くにあって御一族を思い出されることもおありでしょうな」
皮肉でも何でもない、しみじみとしたその声音に、夏侯蘭が遠くを見るような目になった。
「ええ。ふとした拍子に思い出します。伯父達のことなど、色々と」
このやり取りから十年後の建安二十四年、黄忠は定軍山の戦いにおいて“夏侯蘭の伯父”である夏侯淵を自らの手で討ち取ることとなる。
さらには定軍山より時を経ること三十年の後、夏侯淵の子の夏侯覇が、夏侯蘭・夏侯蓮・夏侯纂・夏侯博ら一門の縁を頼って蜀漢への亡命を果たす。
人の世は、合縁奇縁の糸が織り成す錦の絵図だ。
その“不思議な縁”とやらは、どうやら魏延と黄忠の間にも生じたものらしい。
魏延は自らの率いる師団を鍛錬する傍ら、黄忠から度々弓術の指導を受けた。南郡一と謳われる弓の名手の教えは厳格を極めたが、魏延は持ち前の負けん気をもってこれに喰らいつき、みるみる内にその腕前を上げていく。
日々めざましい成長を遂げる若者の姿は、老年にさしかかった武将の心を揺さぶり動かす輝きに満ちていた。
「魏延、おぬし、年はいくつになる」
「は、二十三になりますが」
青年の応えに、黄忠は「そうか」としみじみとした声音で返す。靴紐を締める手を止めて、「?」と目をしばたたかせる魏延。
黄忠の胸に、齢二十で夭折した一人息子・黄叙の面影が去来する。黄忠自身は年を重ねてなお矍鑠としているが、親族はみな早世の質であったのか、兄弟妻子とも揃って黄忠に先立った。黄家は今や黄忠の末弟が遺した娘を始め、わずかに幾人かを数えるのみである。
「そうかそうか、二十三か。よい年頃だ」
うんうんと一人でうなずいている黄忠に、魏延の頭上の疑問符が増していく。
「のう魏延」
「はい」
「ひとつ見合いをしてみんか」
「み…見合い!?」
あまりに唐突な黄忠の言に、魏延は思わずその声を裏返す。
「君を戴き忠を尽くす、祭祀を絶やさず孝を尽くす、どちらも人士の重大な務めであることぞ」
「は、はい」
「そこで、だ…わしの姪でな、今年で十四になるのがおってだなぁ」
「はい…」
「伯父のわしが言うのもなんだが、まぁ気立ては良いし頭もそれなりに良く回る」
「はい…」
「わしに似て器量もすこぶる良い」
「うっ」
黄忠の強面に浮かぶ怖いような笑み。
魏延の背筋を冷や汗が伝っていた。
見合いの席で向き合った黄忠の姪・黄嬋玉。伯父とは似ても似つかぬ可憐なその容姿に、魏延はホッと胸をなで下ろす。
魏兆はこの縁談を「良縁だ」とひどく喜び、見合いからわずか五日の後には、ごくごく近しい身内のみで婚礼の儀が執り行われた。
この時、どこから聞きつけたものか、主君である劉備から祝辞と祝いの品とが届けられ、若い夫婦をおおいに恐縮させた。
劉備への仕官、文から武への転身、結婚。建安十三年の冬は、魏延の人生の大きな転換期であった。
続く
戻る