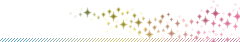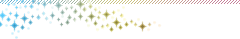
日蝕・4
閨房を包み込む穏やかな闇。
傍らに馬岱の寝息を聞きながら、魏延は独り、夢とうつつの境を迷う。
(……)
沈澱した記憶の沼底に、ふと、白く輝く光源を見た。
淡光はゆるゆると人の形を成していき、やがて、魏延の瞳に忘れえぬかの人の姿を映し出す。
――――玄徳様!
手を伸べ叫ぶ。
届かない。
無音の世界を乳白色の光が満たし、かの人もまた自らも、光の渦に溶け、呑まれていった。
諸葛亮の生誕より五年の月日を経た中平三年―――荊州新野の南に位置する郷村に、魏延は生まれた。
生家は南陽に土着し複数の小作を抱える士族の家柄であったが、代を重ねるごとにその財をすり減らし、魏延の祖父の代に至ってついに田畑のすべてを失った。
魏延の父・魏兆は幼少より“武門の本分に立ち返ろう”と志し、襄陽の通背拳の名手に師事して見事その奥義を皆伝し得た。
息子が二歳になった年、魏兆は突如、洛陽の官軍校尉より召集を受ける。黄巾賊の残党が各地を騒がし、洛陽の周辺に白波賊が跋扈して帝都の民を脅かしつつある現状に、朝廷は軍の練兵強化を促進せざるをえなかった。中原全土の武の匠が一堂に洛陽に会し、官・禁軍の師範代として将兵の鍛錬に当たったのである。
召集の前年に妻を病で亡くした魏兆は、幼い魏延を伴って、父子二人きりで故郷を発った。
絢爛たる頽廃の都、洛陽。魏延にとって郷愁なき原風景である。
父の赴任から三年が経った初平元年―――魏延が五歳の年の冬、長きに渡って繁栄を極めた洛陽の都は、董卓の手によって文字通り焦熱地獄と化した。
長安へ続く人々の列に父の姿は見当たらない。心細さに泣き出す魏延の眼前で、董卓配下の涼州兵が次々と家屋に火を放つ。ゴウゴウと燃え立ち、崩れゆく街の中を、父上、父上と泣きながら駆けた。
一昼夜が明け、廃墟となった洛陽に大挙して押し寄せた反董卓連合軍。焼け跡には魏延と同様、長安への強行軍から取り残され、見捨てられた無数の住民達がいた。連合軍の中枢は難民と化した彼らを顧みない。
肉親と引き離され、生活の基盤を根こそぎ奪われた人々の絶望。悲哀。
暴虐な為政者のもと、疲弊し嘆く民の姿は幼い魏延の胸底深くに刻まれた。
「向こうで兵隊が炊き出しをやってるそうだよ、行ってみよう」
そう口々に噂する人々の後を追い、かつて大小の商店が軒を連ねた大通りへと出た。
飢えと寒さに小さな体は細かな震えを帯びている。
炊き出しは、確かにあった。
幾人もの兵卒が、大釜で煮た雑穀の粥を群れなす難民に給していたのだ。
(…あ、)
どうしよう、椀がない、
まごついていたその時である。
ふいに、目の前にその椀が降ってきた。驚いて顔を上げればそこには甲冑を纏った年若い一人の将軍が。
将軍は手にした椀を魏延に持たせ、その背を広場に向かって押した。
「行っておいで。焚き火の近くで食べなさい」
火の側に腰を下ろして、粥を啜りつつ風にたなびく軍旗を見やる。
旗地に縫いつけられた、目にも鮮やかな「劉」の一字。
童顔ゆえに年より若く見られがちだが、この時「劉」の将―――劉玄徳は、すでに三十路の声を聞いている。
平原より引き連れた五百の騎兵は、みな劉備の思いに賛同して戦に赴いた奇特な有志達であり、貴重な兵糧を炊き出しに割くことに対しても不平をこぼしはしなかった。
が、難民に粥を給するその一方で、粛々と平原への撤退準備を進めつつある。
寒風の中すべてを失った人々を前に、劉備の心は揺れ惑い、その苦悩は深くなる。
「あの者達を平原にまで引き連れていくおつもりで?」
劉備の胸中を見透かしたのか…どこか咎めるような声音でもって関羽が言う。
「不可能です。無理な話だ。兄者、我々は董卓を討つため兵を挙げたのですよ。本懐はならず、その上無用の手枷を抱え込もうなど…」
「家をなくした哀れな民が私達の手枷になると?」
「少なくとも今の我らにとっては、です。民と将兵、双方を飢えさせぬ術を、我らは持ち合わせてはいない」
関羽の言は的を射ている。返す言葉が見つからない。
劉備は小さくため息をつき、幕舎を出て冬の夜空を仰ぎ見た。
ちょうどこの時、劉備の陣営にほど近い焼け跡の一画で、ちょっとした騒ぎが起きていた。
夜になり、厳しい冷え込みに耐えかねた魏延は、火種を求めて篝火に手を伸ばしていた。
鉄製の篝籠は丈高く、背伸びをしても籠中の木切れに指が届かない。悪戦苦闘の末、図らずも篝籠を地へと倒してしまう。
ガシャンという大きな金属音と共に、赤々と燃え盛る木切れがそこかしこに散らばった。まさかの事態に茫然とする魏延の耳に、「あっ」という叫びが飛び込んできた。
声の主は、少年だった。
一見して年上の相手とわかる、己よりずっと上背の高い少年である。
倒れた篝籠に駆け寄った“彼”は、散乱した火種の下敷きになってパチパチ音を立てている布包みを見て血相を変えた。
「ああ、僕の、僕の…!」
古布に包まれた竹簡が見る見るうちに黒焦げになっていく。
魏延はひどく動揺する。きっとあれは彼の大切な物であったに違いない、それを自分は愚かにも灰にしてしまった!…―――「ごめんなさい」と魏延が言うより数瞬早く、少年の平手が幼い頬に振り下ろされていた。
「馬鹿っ、馬鹿っ、お前、なんてことをしてくれたんだ!」
怒りもあらわに繰り返し殴打する。
打たれる痛みと恐怖とで魏延がワァワァ泣きわめくのもかまわずに、逆上のまま殴りつけてきた。
子供と子供のいさかいとはいえ、さすがに尋常でない現場の空気に「何があった」「なんの騒ぎだ」と数人の兵士や難民達が集まってきた。
「返せ、馬鹿、僕の本だぞ、僕のだったのに!」
激しい怒声に身がすくむ。
が、ふいに、打擲が止んだ。
「……」
煤と涙に汚れた顔を上げてみる。
そこに、椀の将軍と、彼に背後から抱き止められた少年の姿があった。
「ぶってはいけない。こんなに小さな子供じゃないか。何か理由があるのだろう、殴った訳を言ってごらん」
将軍のその言葉に、少年の顔が苦しげに歪む。
「こいつ、この火をひっくり返して、僕の荷物を燃やしちゃったんだ」
「そうだったのか、大事な物が入ってたのか?」
「僕の本だ! 父上から貰って、ずっと大切にしてたのに!」
「そうか、それは、つらかろう。とても残念なことだ」
「もう貰えないんだぞ…父上、もう…」
瞬間―――魏延と劉備は、少年と少年の父との死別を悟る。
「父上がくれたのに、父上の大事な本だったのに…」
握った両手を震わせながらうつむいた少年の頬を、涙の粒がいくつもいくつも伝って落ちた。
劉備にその身を抱えられたまま、少年は天を仰いで泣きじゃくる。
うずくまり、やはり涙で顔をグシャグシャにしながら、ごめんなさい、ごめんなさいと繰り返す魏延。
劉備はただ、言葉もないまま、悲しみに震える幼い体を抱きすくめていた。
頭上にきらめくあまたの星図。
紫微垣が青く燃えている。
翌日。太陽が中天にかかる頃、少年は肉親と奇跡にも近い再会を果たす。
廃墟に響く「亮、亮」の呼び声に、劉備の傍らでうつむいたまま石を蹴っていた少年が、ハッとしたようにその顔を上げた。
「…兄上!」
焼け落ちた洛陽の空の下、兄と弟は互いに駆け寄り、きつく固く、抱擁を交わす。
兄―――十七歳の諸葛瑾は、劉備や関羽、張飛ら平原の将兵に深い感謝の意を告げたのち、弟を連れ洛陽を発った。
去り際、弟―――諸葛亮は、何度となく見送りの人々を振り返った。
劉備を見、魏延を見た。
風に舞う「劉」の旗を見た。
遠ざかる兄弟の後ろ姿が、乾いた風が巻き起こす砂塵の彼方にぼやけて消えた。
それから数刻も経たぬ内、魏延の上にも父との再会というこの上ない奇跡が起きることとなる。
洛陽の焼け跡に息子の消息を求めに来た魏兆。遷都の混乱に乗じ、道々で民百姓を襲撃しては略奪を重ねる賊徒の討伐に不眠不休で当たっていたのだ。その体は乱戦のさなかに負った無数の斬り傷に覆われていた。
“椀の将軍”に繰り返し礼を述べる父の戦袍にすがりつき、上目で将軍の顔を盗み見る。
父と言葉を交わしながらも、将軍は魏延に小さく笑いかけ、片目を軽くつぶってみせた。つられて魏延の口元も緩む。
父と共に馬の背に揺られつつ、魏延は洛陽を後にする。
振り返るたび、見送りに立ったままいてくれる将軍の姿が見えた。
ほどなくして魏兆は官軍師範の任を辞し、父子は荊州南陽へと帰郷した。
続く
戻る