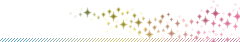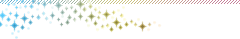
日蝕・3
「よせ、いきなりなんだ!」
抱き込んでくる強引な腕を振りほどこうと身をよじる。
束の間もみ合いが続いたが、唐突に馬岱はその腕の戒めを解き、動揺する魏延へと向き直った。
「冷たくされたよ」
「えっ?」
「涼姫も、承も…この俺がどのような思いでいるかまるで解そうともしない」
「…嘆いても詮無いことだ、それは」
年端もいかぬ者達に一体何を期待して…そう口ごもる魏延の頬を、馬岱の両の手の平が包み込む。
その青の双眸に仄暗い情念を宿して、男は言った。
「拒むな」
魏延の眉根がわずかに寄せられ、その顔が半ば諦めの色を刷く。目蓋が下りるか下りないかの内に、唇に男のそれが重なった。
執拗な口づけだった。
人肌の温もりに飢えていたのか、唇を吸いながら、馬岱は魏延の首筋に指を這わせてしつこい位に撫で回す。
「……」
己の肩をしきりに叩く魏延の手に、何事かと顔を上げる馬岱。
かすかに上気した顔を背け、魏延は肩で息をしていた。
「どうかしたのか」
「そう急くな…息苦しい」
声を潜め、そっぽを向いて言う魏延。
その物言いになんともいえぬ可愛げを感じた馬岱はさもおかしげに笑うのだった。
「今日は邸に戻るのか?」
「いや…月変わりまで詰める予定だ」
「そうか。俺も今夜はここに泊まるよ、かまわんだろう」
「好きにしたらいいさ」
劉林は動揺のただ中にあった。
数瞬前に目にした光景、脳裏に強く焼きついたそれが、幼い胸を困惑でかき乱す。
(お二方とも一体何を…)
遊び相手の魏攸が宿舎の長椅子に突っ伏したまま寝入ってしまったのがつい先程のことである。
手持ち無沙汰になった少年は、次の遊び場を漢中太守の膝上へと見定めた。
府内の回廊を渡り執務の間へと至ったが、そこに魏延の姿はない。
どちらにおいでか?
客間だろうか?
馬岱将軍と何事かお話に?―――なんとはなしに覗き見たその一室に、確かに二人の姿は在った、が…
「…!?」
思わず我が目を疑ってしまう。
丈高い馬岱の背の向こう、きつく目を閉じ眉を歪めた魏延の顔が見てとれる。唇が重なり、上体がもつれ合っていた。
見てはならないものを見た…幼心にそう悟り、慌てて回廊を引き返す。
宿舎へと駆け戻り、魏攸の眠る長椅子に這い上がって息をつく。動悸の乱れが治まらない。
「…魏攸、魏攸」
友人に小さく声をかけてみる―――が、果たして、聞こえてくるのは細くかすかな寝息のみ。
背もたれに寄りかかり目を閉じる。どうにも気持ちが落ち着かなかった。
夕餉の席は魏父子、馬岱と共になったが、劉林は努めて平静を装った。
好奇心いっぱいに旅の話をねだる魏攸に馬岱の機嫌は上々である。
平素に比べ幾分口数の少なくなった魏延の顔を、チラと横目で見やる劉林。心密かに“父”とも慕うその人の胸中を窺い知ることは、叶わない。
身の内を貫く男の熱に、魏延はかすかな呻きを洩らす。
肉筒を無遠慮に押し開き、奥へ奥へと突き入ってくる馬岱の雄が恨めしい。
久方ぶりの同衾だった。
性急な愛撫に強張り軋む魏延の肢体に、「いい加減慣れてもよさそうなものだ」と、馬岱の面が露骨に不興の色を刷く。
(いい気なものだ、受ける身の苦しみも知らないで)
思わずなじってやりたくもなる。
実のところ、劉備以外の同性と体を重ねることになるなど思ってもみないことだった。まして受け身に回るなど。
わりない仲におちいったのは、南中よりの帰還の直後。南方の暑気にあてられ体を壊した馬岱から、ほとんど泣き落としのようにして閨へと引きずり込まれたのである。
(そうだ…こいつ、確かあの時も)
「淋しい、拒まないでくれ」―――そんな言葉を臆面もなく口にして、こちらの言を封じてきた。
体が弱れば心も弱る。
何かにすがりたくなる気持ちもわかる。
だが、なぜ、自分なのだろう。
何度となく「妻を娶れ」と縁談を持ちかけてみたものの、馬岱は耳を貸そうとはしない。
(応じるべきでなかったのだ。今さら悔やんでどうなるものでもなかろうが)
同情の念は確かにあった。
馬岱の抱えた孤独を思い、その懇願に流されるように関係を持ってしまったが、時を経てなお同情が愛へ変わる気配は無い。
交わる度に憐憫が増すだけだ。
(間違っている。何もかも。こんな歪な関係は…)
己の矜持に照らしてみても、とても納得のいくものでない。むしろ恥すら覚えてしまう。何故だろう。何故、流され、受け入れてしまったのだろうか。
「……」
惑いと悔いとが魏延の体をこわばらせ、彼を組み敷く馬岱の身にも緊張の波を伝えてしまう。碧眼の男はじわじわと苛立ちを募らせていた。
「なぁ、おい、もう少しなんとかならんのか」
「なに…?」
「もうちょっと愛想を良くしてくれたって罰は当たらんと思うがね」
「……」
「張り合いがないよ、おぬしにそう頑ななままでいられては」
「……わからんだろうが、苦しいのだ、こちらは」
馬岱の雄は体躯に見合って太く長い。その張り詰めた凶器でもって腹を掻き回される方の身にもなってみろ、いいから早々に果ててくれ―――喉元まで出掛かった本音を飲み込んだ。
「文長、おぬし、いつになったら俺に心を開いてくれる。要は気の持ちようではないか。心を向けてくれたなら、自然、体もほぐれるものだ」
もっともらしい言い分ではある。
だが、もう、無理なのだ。
肝心のその心とやらは、とうの昔に“かの人”の御魂に捧げ、その死と共に永劫の完を得た。切なくも甘美な終焉である。
(そう、無理だ、叶わぬ話だ、伯瞻よ。このようなことは間違っている。俺は応じるべきでなかった、虚しさが積もるばかりではないか)
心通わぬ交わりであると、そう知りながら求めに応えた罪がある。魏延は自身の愚行を悔いた。
「…!!」
ふいに、のしかかる男の動きが激しさを増す。思わず小さな悲鳴が洩れた。
一向にほぐれぬ魏延の体に腹を立て、馬岱はことさら責め手を酷くする。
どうにか苦痛をやり過ごそうとすがったものは、男の腕でも背でもなく。
失ってなお愛してやまぬ、かの人の遠い面影だった。
続く
戻る