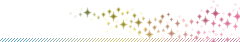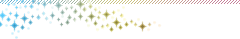
日蝕・1
◆劉林(218年生)
◆劉永・劉理(216年生、双子設定)
◆黄皓(215年生)
東宮の一画。
かつて在ったといわれる楼台はその土台をわずかに残して打ち壊され、周囲を石造りの壁に覆われている。
楼台の破壊と隔絶は、“彼”の叔父である今上帝・劉禅が、即位の後に真っ先に執り行ったものという。
彼―――劉林に父・劉封の記憶は無い。
己がまだ物心つかぬ幼児の時分、父はその楼台から身を投げ命を絶ったのだ。
失意と錯乱の内の死と聞いた。
ある人は、また、先帝に死を賜ったのだと囁き、ある人は丞相に害されたのだと声を潜めて噂する。
人目を忍び、幾度か壁を越えてみた。
父の血を吸ったであろう大地の上は、一面が緑と名もなき花々に覆われて、密やかな花園となっていた。
劉禅は今なお最愛の兄の面影を追って生きている。
長坂で死に別れた母・鴻芙蓉。その思い出を兄に語り聞かせてもらうひと時が、何にも代え難い喜びだった。
美しく優しい兄だった。
己のもとに劉林を遺し、ある日突然、この世界から消えてしまった。
その悲しみはあまりに深く、心の奥底には癒えることのない虚無が刻まれた。
叔父の悲嘆は、幼い劉林の胸をも苦しくさせる。覚えてもいない父の死が口惜しいというのではない。己を愛し慈しんでくれる叔父の涙がつらいのだ。
宮中の人々が己に向ける視線は実に様々なものだった。
憐憫、侮蔑、同情、嫌悪。
元を辿れば父へと還る―――先帝の義弟・関雲長の死に絡む一連の悲劇は、頑是無い劉林の上に重くのしかかるものだった。
関家の縁者が己を見る目の、なんと冷たく憎々しげなことだろう。
中でも関羽の遺児たる関興、関銀屏、関索は、ことさら劉林につらく当たった。
皇族が集っての催事の最中、面と向かって罵詈雑言を浴びせられたこともある。
皇帝を始め、年の近い劉永、劉理ら三人の叔父達は、その都度劉林をかばい続けた。先帝のもう一人の義弟・張翼徳の子ら―――張苞、皇后・張星彩、張紹の三人もやはり劉林を不憫に思い、与うる限りの情愛を注いだ。
桃園の三兄弟はそれぞれが三人ずつの子を遺した。が、今や三家の均衡は崩れ、姻戚となった劉家・張家と関家との間には、目には見えない深い溝が生じているかのようだった。
(私は諍いの元なのだ)
ひがみでも諦めでもない。
ただハッキリと、現実を悟った。
そんな甥の胸中を慮った劉禅は、事あるごとにこう言い聞かせた。
(言いたい者には言わせておけばよい、そなたがいじけることなどないぞ)
劉禅の思いは、「可愛い甥に過去の因果を背負わせてなどなるものか」…ただただその一念に尽きる。
その日、清和殿に続く廊下の角で劉林が遭遇してしまったのは、己を仇の子と忌み嫌う関興であった。
苛烈極まる気性を持った若い武人は、憎しみもあらわに幼い子供をなじり始める。なんとも間の悪いことに、近くに叔父や叔母達の姿はなく、近侍の者も誰一人として居合わせなかった。
関興という男の存在は、劉林にとってまさに“恐怖”の権化であった。彼の放つ怒りと悪意に満ちた声音は劉林の心身を極度に萎縮させてしまう。
袖の端を掴んでうつむき、必死に耐えしのんでいたが、ついにその頬を大粒の涙がボロボロと伝って落ちた。
「人非人の子供にも一丁前に流す涙があるというのか」
嘲笑し、小さな額を小突いて無理にその顔を上げさせる。
「似ているな。いっそ腹立たしいほどだ。まぁ、どうせ顔だけでなくさもしい性根も父親とそっくり同じであろうがな」
どうした運命の巡り合わせか、ちょうどこの時、少し離れた廊下の隅に、宮中に上がってまだ日の浅い少年宦官・黄皓のオロオロ惑う姿があった。
上役から「劉林殿下を内廷にお連れするように」との指示を受け、詰め所を出てきたところにこれである。
柱の影に身を潜め、どうしよう、どうしようとうろたえ爪を噛む。
廊下に響く関興の罵声…ひどく高圧的で恐ろしげなその響きに、我知らず足が震えを帯びた。
(劉林殿下…)
涙に濡れた幼い横顔。
なじられ、小突かれ、それでも唇を食いしばり必死になって耐えている。
一瞬、黄皓は、劉林の悲哀を己の境遇に重ね見る。
黄皓の生い立ちは不遇であった。その一族に罪人を出し、連座して親族離散の憂き目に遭った末に売られた先は宦官の家だった。
(泣いている)
それは同情というよりも、むしろ瞬間的な“同調”であった。
そうだ、あの涙は私が流した涙と同じ
ひとりぼっちの私と同じ
「…劉林様!」
突然己の名を呼ばれ、劉林はハッとなってその顔を上げた。
「…?」
関興も声のした方に目線を移す。
小柄な下位の宦官が一人、こわばった顔をしてそこにいた。
「……何用だ」
「あ…あの、り、劉林様を、」
「なに?」
「その、劉林様をお連れするよう…」
「知ったことか、失せろ」
「で、でも…あの…」
関興の険しい視線に怯えるあまり、黄皓は舌もまともに回らない。
腰は引け、声は震え、情けない程に萎縮していた。
関興は関興で、宦官などは畜生以下の下等な存在であるといった認識しか持ち合わせていない。その畜生以下が、一体何をのたまうつもりでいるのだろうか?
「失せろというのがわからんか」
「でも、あの……こ、皇帝陛下のお召しでございます」
皇帝の名を出したのは咄嗟の思いつき…むしろ出任せに近いものだった。
が、それは図らずも、関興の矛先を劉林から己へ向かわすこととなってしまう。
「皇帝が…だから、なんだというのだ」
「え…」
「宦官風情が差し出た真似を!」
不快感もあらわに睨めつける。
異様なまでの怒気を纏う筋骨逞しい長身。
黄皓の面はすっかり血の気を失っていた。
茫然とする劉林の目の前で、関興はゆったりとした足取りで黄皓へ歩み寄り、おもむろにその首元を掴んで吊り上げた。
華奢な喉首がヒィ、とか細く悲鳴する。なんのことはない、家畜を一匹くびり殺す、その程度の冷めた感覚があるだけだ。
「…!!」
宦官の家に売られたわけは、ひとえに容姿の美しさから。黄皓のその少女のような愛らしい造りの顔が、今は苦悶に歪みきっている。
この蛮行に、劉林は身じろぎはおろか声を上げることも出来ぬまま、無言で涙を流すばかりだ。
首を絞め上げる武人の指が一層力を増しかけた、その時…
「安国!」
歪な私刑の空間を裂くその一喝。
「やめよ、安国」
今上帝・劉禅その人であった。
傍らには皇后・張星彩と数人の近侍達。みな一様に青ざめた表情で此方を見やる。
「これはこれは、陛下」
「安国、そなた、宮中でなんたる狼藉を…その者になんの咎あってかような無体を働くか」
「なんの咎、ですと? 卑賤の分もわきまえずそれがしに無礼を働きました故」
「いかなる訳があろうとも官人への私刑は許されぬ!」
劉禅の声音は常になく激しいものだった。
先帝の面影を色濃く宿す白珠の容は、静かな憤怒に険しさを増す。
張星彩は、初めて目にする夫の怒りの形相に、思わず身をすくませていた。
穏やかで優しい幼なじみの少年は、長じて愛する伴侶となった。声を荒げることなど知らぬ人だと思っていた。
(公嗣様…)
関興は、フンと鼻を鳴らして黄皓の首の戒めを解く。
幼い宦官はそのまま床にへたり込み、うつむいて苦しげに咳き込んだ。
「で、如何なさるおつもりか」
皇帝に向け、挑発的な口調でもって問いかける。
「それがしに罰をお与えに?」
劉禅の柳眉がかすかに歪む。
ニヤニヤと不遜な笑みを浮かべる同い年の従兄弟。胸底に激しい嫌悪が湧き上がる。
幼少の折りから常に己を見下し嘲ってきた男。
鈍物、暗愚と、幾度となく侮蔑を受けた。
ああ、だが、この身ばかりか亡き兄の子をもかように惨く苛もうとは!
(除けるものなら除いてやりたい)
お前が関雲長の子でなかったら。
我が従兄弟でさえなかったら。
澱んだ憎悪は胸底で黒い沼になる。
「……不問だ」
「左様か」
暗愚めがでしゃばった真似をして…武人の顔には苛立ちの色が見てとれた。
拝礼もなしに立ち去る関興の背に、劉禅はうっすらと、しかし明確な害意すら抱いてしまう。
「叔父上!」
涙ながらに駆け寄ってきた劉林を、固く強く、かき抱く。
「怖い思いをさせた」
許せよ林…なだめるように耳元で囁けば、肩口にまるで猫の子のように頭をこすりつけてきた。
甥の背を撫でつけながら、劉禅は傍らの近侍に少年宦官の介抱を指図する。
ややあって、どうにか落ち着きを取り戻した黄皓―――眼前に居並ぶ皇帝と皇后に、改めて平身低頭の礼をした。
「よい、おもてを上げよ」
「は、は、はい」
「惨い目に遭うたな…大事はないか」
「は、はい、大事ございません」
「……見かけぬ顔だが、宮入りしたばかりかな?」
「はい、十日前に…」
「そうか。そなた、名は」
「黄皓と申します」
ほどなくして、黄皓は皇帝とその家族が暮らす内廷へと転属になった。
その後、関興が若くして肺病を患い没した際も、劉禅は涙のひとつも流すことはなかった。
葬儀の席では兄を亡くした悲しみに取り乱した関銀屏がやはり劉林を手酷くなじったが、劉林は努めてその苦行を耐えた。
ああ、ようやっと解放されたと、
恐ろしい鬼は去ったのだと、
ただただ安堵の念のみあった。
また、関興の喪が明けたのちは、張星彩が従姉妹の愚痴に頭を痛めることとなる。
関銀屏は今や皇后となった従姉妹相手に、泣き言、恨み言を切々とこぼすのだった。
「皇后陛下、こう申してはなんでございますが、張苞様が伏せっておいでの折は、陛下は二日と空けずお見舞いされたというではありませんか。それが我が兄の病床にはただの一度も足をお運び下さらなかった。あまりな仕打ちと思われませぬか。これが国家の功臣に、幼き頃より共に育った身内に対するなされようとは…」
これではわたくしも弟も世間に面目が立ちません―――参内の度にこう泣きつかれ、星彩も大概辟易である。
銀屏をなだめ慰めるその面には、うっすらと疲労の色が見てとれた。
続く
戻る