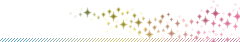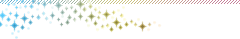
落日・12
時は流れた。
吹き荒れる時代の嵐と共に多くの者が散っていく。
関羽が死んだ。
義父に殉じるかのように、関平も、そして玲綺も死んでいった。
(剣は玲綺を幸福にするものですか?)
あの日、夏侯蓮が口にした言葉の意味を、趙雲は独り考える。
わからない。
彼女は、剣を手にして戦に生きたあの娘は、果たして幸せであったのか。
劉封も死んだ。
張飛も死んだ。
簡雍も、麋竺も、孫乾も、劉備を愛しその生涯を支え守った人々が、二度と帰らぬ旅路へ発った。
彼らの死は劉備の心を凍てつかせ、身の内に抱えた狂気に拍車をかける。
夷陵を焦がす紅蓮の炎。
多くの命が消えていった。
黄忠も、馬良も、麋芳もみんな死んでいった。
章武三年一月。
白帝城・永安宮の中庭に、音もなく雪が降り積もる。
皇帝の病床。その傍らに置かれた牀に掛けながら、趙雲は過ぎ去った優しい日々の記憶を辿る。
時折、横たわる劉備の手を取り浮き出た骨をなぞってみる。
細く冷たい白い指。趙雲は自身の両手にそれを挟んで何度か擦り揉み込んでみる。血の巡りを良くしてやりたいと思った。だのに、痩せ衰えた劉備のその手は、冷たく凍えきったままだ。
愛する人のかすかな息の音を聞く。
目を閉じ、微動だにしない劉備をのぞき込み、敷布に流れる真っ白な髪を撫でつける。
この半年で劉備の緑の黒髪はその艶やかさを完全に失った。空の上から落ちてくるあの雪のような銀色と化した。
元より白い柔肌が、生気を失い透き通るようになっていく。
やがて消えゆく淡雪のそれだった。
壊れやすい透明な玻璃の指、その先端に口づける。
趙雲の唇にうっすら残る淡い冷気。
劉備の部屋へと至る永安宮の渡り廊下。
諸葛亮はその背に妙な寒気を感じ、ふいにその歩みを止めた。
(……?)
雪のせいではないと思う。
悪寒だ。なにやら嫌な予感がする。
(………)
変だ。
おかしい。
どこか、何かが不自然だ。
この城の中に異様な“気配”が降りている。
「…!?」
ふいに中庭に目をやって、次の瞬間、戦慄を覚え立ち竦む。
桃だ。
舞い散る雪の白さの中で、桃の木が一本、目にも鮮やかな花弁を咲き誇らせていた。
(馬鹿な、一体……ありえん事だ)
今朝方までは無かったはずだ。
すべての樹木が沈黙を守る中、なぜ桃の木だけがただ一本、あのように花をつけている?
羽扇を握る右の手がかすかな震えを帯びている。
どうした事だ、何が起きようとしている?
「え…」
桃の木の向こう、雪化粧された東屋の屋根のその下に、なにやら人影があった。
諸葛亮はその黒い影に目をこらす。
(まさか、そんな、)
鼓動が跳ねる。早鐘を打つ。
諸葛亮の全身を瞬時に駆け巡る悪寒。
東屋の下に、張飛がいた。
いつかのように牀に掛け、咲き誇る桃に見入っている。
(そんな……嘘だ、嘘、なぜ、)
怜悧な頭脳が惑乱する。
なぜだ?
どうして、どうしてだ、
あなたは死んだ、死人となった、この世にあってはならない者だ!
(なぜ居る、なぜ今ここに迷い出る!)
桃は張飛が連れてきた。
現世の花ではないのだろう。舞い散る花弁が空気に溶けて消えゆく様が、あまりに儚く美しい。
死んだ男がこちらを見やる。
諸葛亮の薄い唇が震え、呼吸の音さえも凍った。
おもむろに死人が立ち上がる。
ふいっとその身をひるがえし、白い空気の中へと溶けた。
東屋は、庭は、無人となった。
桃の花弁も消えている。
(……まさか、)
強張っていた体をビクと震わせて、諸葛亮は石の廊下を駆け出した。
いつの間にやらうたた寝をしてしまったようだ。
趙雲はその目を開けて寝台の上の劉備を見やる。
と、次の瞬間―――自身の体に生じた“異常”を感じ取り、胸の鼓動を跳ね上げる。
(…腕が…!?)
動かない。
腕だけでない。
足も、首も、指先さえも動かせない。
己の体であるはずなのに、どこもかしこも石と成り果ててしまったようだ。
唯一自由に動かせるのは眼球ばかり。
趙雲は見る。劉備の傍らに佇む、黒く巨大なその人影を。
(…!!)
黒い影。横たわる劉備をのぞき込んでいるのがわかる。
身じろぎもせぬ劉備。
なぜだ、吐息が聞こえない。先程までは確かに聞こえていたはずなのに。
趙雲は恐慌状態に陥る。
嫌だ、怖い、大声を出して叫びたい、だのに体が動かない!
(玄徳様!!)
起きて下さい、目を開けて!
声なき声で趙雲は叫ぶ。
魂のすべてをもって劉備を呼んだ。
恐れ、怒り、憎しみ、愛――――ありとあらゆる感情が凍った体の内側を黒炎となって駆け巡る。
黒い人影、“彼”の手が、ぐにゃりと伸びて劉備の白い手を掴む。
やめろ、
その人に触れるな
(知っているぞ。俺はお前の名を知っている。一体何を間違えた。なんのつもりでこんなところへ迷い出た)
影の手に掴まれた劉備の白い指先が、徐々にぼやけて透け出した。閉じた目蓋は動かない。
趙雲は知っている。
その影の名を、“彼”のその名を知っている。
動け!
早く、腕も、足も、唇も、
早く、早く、早く!
「―――っ!」
弾けるように右手が跳ねた。
五本の指がビクビクしなって宙を掻く。
解放された怪物の牙。
鬼神の呪縛を引きちぎり、怪物はその爪を“彼”の手首に突き立てる。
―――――関羽!
叫ぶ。
その名を告げていた。
死して鬼神となった男と生きながら怪物となった男の間には、今はただ、劉備一人が在るのみだ。
他には何も在りはしない。
他には何も望まない。
劉備の手を取る関羽の腕を、趙雲は砕けよとばかりに掴み締めた。
「!!」
掴んだ右手に走る激痛。
空気の波が刃となって趙雲の手を切り裂いた。血が迸る。続けざま、髪も頬も唇も切れ、赤い飛沫が飛び散った。
弾かれた右手を伸ばし、鬼神が捧げ持っていた劉備の手首を鷲掴む。
「玄徳様!」
揺さぶる。
何度も何度も繰り返し名を呼んだ。
起きてくれ、早く、その目を早く開けてくれ!
――――突如、鬼神の首がグルンと回って趙雲に向く。
趙雲は思わず息を飲む。
無い。
関羽の顔がそこに無い。
かつて関雲長という名の生を送った男の顔は、真っ暗闇の虚ろな穴であったのだ。
ぽっかり空いた果ての見えない井戸底だ。その奥、遠い彼方より、怒りを湛えた低音が響く。
“趙雲、憎らしい奴め”
鬼神は己に手向かう怪物に敵意を抱いたようだった。
「立ち去れ、関羽、その手を離しここを去れ」
関羽と趙雲。
死者と生者の対峙が続く。
「俺を殺すか? やったらいいさ、やれるものなら。俺は離さん、この手を決して離さんぞ。生きても死んでもこの人は俺のものなんだ、誰にも渡したりはしない」
死者の怒りが趙雲の唇をブツン、ブツンと引き裂いた。
空気の刃に斬りつけられて、趙雲はその顔面を血塗れの惨状にしていく。
「去れ、関羽、去れ! 迷うな、ここは人の世だ!」
その刹那、趙雲に掴まれていた劉備の手首がピクンと動く。
かすかに聞こえる呼吸音。
乾いた白い唇が小さく震え、息をした。
―――鬼神の黒い影は消えた。
皇帝が伏したその部屋を、いつものように静寂が支配する。
宙に透け、消えかけていた劉備の細い指先が、淡い紅色を刷いていた。
趙雲は見る。ゆるやかに上下している劉備の胸を。そして、深く、安堵した。
切れた目蓋とこめかみと、唇と頬と、そこかしこから音もなく血が垂れ落ちる。
いつかの長坂と同じだ。
俺はこうして血まみれだった。
貴方は強く抱いてくれた。
嬉しかった。命を感じた。確かに俺は生きていた。
バン、と強い音を立て、部屋の扉が開かれる。
振り向く趙雲の視線の先に、その美貌を蒼白にした諸葛亮が立っていた。
肩で荒く息をしている。
唇は血の気が引いていた。
「趙雲殿…!?」
「…丞相」
血塗れの趙雲の面に、諸葛亮は思わず息を飲む。
「いかがなされた趙雲殿、その顔…その傷は一体!?」
足早に駆け寄り、懐中から取り出した薄絹でもって武将の顔面を拭う。
諸葛亮は血の付着した劉備の腕も続けて拭き清めてやった。
趙雲と劉備、双方を交互に見やる諸葛亮。しばしの沈黙を経た後に、独りごとのように言った。
「誰か来ましたか、ここに」
薄絹をこめかみに押し当てながら趙雲が答える。
「関雲長。懐かしいような気もしましたよ。だが、あれはもうかつての雲長ではないな。ハハ、奴め、陛下と私を手にかけようとしましたぞ」
奇妙なほどに明るい笑顔を見せてくる。
そんな武人の瞳の奥を、黙ってじっと見つめる諸葛亮――――やがて小さく息を吐き、劉備の寝台にのろのろとした動作でもって腰掛けた。痩せ衰えた皇帝の白い手を取り握りしめる。
「…庭の桃の木、」
「桃の木がどうかしましたか」
「春になる前、この冬の内に、すべて切り倒してしまおうかと…」
「それはまた…なぜです、陛下が嘆かれるのでは?」
「なにやら気分が悪いのです。良からぬものを呼びそうで」
「ハハ、魔物を招く桃ですか、ハハハ」
笑う男の唇が赤い雫を滲ませる。
趙雲は思う。
己は関羽という男のことを何ひとつ知らないままでいたのだと。
彼の抱えた漆黒も愛執も、なにもかも理解せぬままこれまで生きてきたのだと。
関羽は人でなくなった。
現世を離れ、人智を超えた神となった。
神と魔物の違いとは一体なんであるのだろう?
もう一度あの巨大な影と対峙して、俺は、果たして自己を保てるか?
(……何を恐れる。何に怯えることがある。俺の掟は劉玄徳だ。俺を生かすも殺すのも、支配するのもすべては劉玄徳なのだ。たとえ神にも俺は決して従わない)
――――口内にじんわりと血の広がるのを感じつつ、趙雲は諸葛亮に向けきっぱりとした口調で言った。
「わかりました、切りましょう。雪が止んだら衛兵を呼んでやらせます」
「申し訳ない。お願い致す、趙雲殿」
劉備のその手を握り続ける諸葛亮。
趙雲も背後の牀に腰を下ろし、背もたれに寄りかかって大きくひとつ、息をつく。
開かれた扉の向こうに白くまぶしい光が見える。
舞い散る雪はまるで桃花のそれだった。
続く
戻る