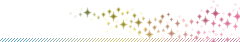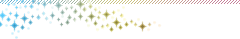
落日・7
◆夏侯博、夏侯纂が夏侯蓮の従兄弟です。
的盧は劉備の危機を救った。
蔡瑁の計略により檀渓の急流へと追い詰められた劉備だったが、この絶体絶命の窮地において、的盧はゆうに三十尺はあろうかという断崖をひと飛びにしてみせたのだ。
ある者は「劉備の馬が龍に変じて天駆けた」と言い、またある者は「これは劉備が天下を統べる天啓である」と言う。
その一方で、的盧を凶馬と呼ぶ者もいた。「額の星が乗り手に不幸をもたらす」と。
劉備にとっても趙雲にとっても、そんな噂は取るに足らないものだった。
趙雲は自身の目利きに確固たる信念を持ち、劉備は的盧を心の底から信じて慈しんでいた。
的盧は主人の愛と信頼に見事に応えたのである。
そして建安十三年。
春の訪れと共に、劉備陣営に新たな面子が加わっていた。
「ちくしょう、あの水野郎めが」
ふてくされた様子で吐き捨てるように言う張飛。
趙雲と張飛の二人は今、東屋の牀に腰を下ろして、練兵の合間の休息をとっている。
「水野郎? なんのことだ?」
「アイツだよ、あのすました顔の若僧さ」
「諸葛亮殿のことか。なぜあの御仁が水野郎なんだ?」
「兄者が言うんだ、私は魚で孔明は水、魚は水がなくては生きられぬってさ…ちぇっ、まったく面白くもない!」
ブスッとしたまま貧乏ゆすりを始める張飛。
彼の全身から発せられるこれでもかと言わんばかりの嫉妬の念に、趙雲は思わず吹き出していた。
それを見咎め、張飛はさらに声を荒げる。
「やいやい子龍、何が可笑しい! お前は悔しくないのかよ!? あんなポッと出の若僧に兄者を独り占めされて!」
「悔しい…?…うん、まあ、おぬしの怒る気持ちもよくわかる。たしかにああ朝晩ベッタリされてはな」
「だろ!? 兄者はどうかしちまったんじゃないのかね! 長年苦楽を共にしてきた俺達のことをほっぽり出して、いつでもどこでも孔明、孔明…あーっちくしょう、腹の立つ!!」
屋外にまでグワンと響く不満の叫び。
と、向こうから石畳を渡って一人の青年が歩いてくるのが目に入る。
白地に黒襟の道服をまとったその長身。
「来たよ。来やがったよ水が」
張飛は敵意を全開にしてその青年をにらみつけた。
東屋の前を通り過ぎるその一瞬、諸葛亮は、チラリと二人に視線をやった…が、先輩方に対して挨拶するでも会釈をするでもないままに、スタスタ遠ざかっていく。美しく整ったその横顔はどこか不遜で、いっそ高慢ですらある。張飛のこめかみに血管が浮いていた。
「見たか子龍。見たかあの野郎の態度。あっっっったまくんなぁちくしょうめ!」
「落ち着けよ翼徳、ここに来たばかりで緊張しているのかもしれんじゃないか」
「なんだよ、あんな奴のこと庇うなよ! お前だってくやしいくせに!」
荒れる張飛を苦笑しながらなだめる趙雲であったが、彼の心の内はといえば、“諸葛亮への嫉妬”なるものは欠片も存在していなかった。
自分でも不思議で仕方がない。
なぜだろう? 彼、諸葛亮に対しては、愛する劉備を一日中独占されているにも関わらず、嫉妬や怒りといった悪感情が微塵も湧いてこないのだ。
これはもう相性、波長の問題になってくるのかもしれない。
端的に言って、趙雲と諸葛亮とは、“人間同士の相性”が良かった。
両者のその良好な人間関係は終生に渡って続き、趙雲はあらゆる局面において諸葛亮から全幅の信頼を寄せられることとなる。
(別にくやしくなどないさ。だって翼徳、俺はあの若者よりも、おぬしの大事な姫君の方がよほど憎らしいのだから)
ふくれっ面の張飛の横で、趙雲は密かに思う。
鴻芙蓉は元はといえば張飛の主君であったのだ。劉備と張飛の出会いというのも、芙蓉に縁有っての出会い。幼少の頃より仕え、兄妹のようにして育った芙蓉のことを張飛は今でも「姫」と呼び、深く敬い慕っている。
劉備と芙蓉の結婚を誰より望み、また祝福したのも、他ならぬこの張飛である。その事実を思うにつれ、趙雲は張飛に対してさえも、うっすらと苛立ちを覚えてしまう。
(水野郎など可愛いものさ。翼徳、俺はな、おぬしの姫が大嫌いだよ。憎くて憎くてたまらんのだ。おぬしは何も知らんだろう、この俺の胸の内、苦しみなどは何ひとつ)
趙雲の面はあくまで涼やか、翳りのひとつも見当たらない。
その胸中に渦巻く歪な憎悪に気づく者など誰一人としていないのだ。
と、今度は、夏侯博と夏侯纂の二人が連れ立ってこちらにやって来るのが見えた。
二人は東屋に張飛の姿を見つけると、「おーい」と呼びかけ手招いてきた。
「翼徳殿ーこちらにおいででござったかー」
「蓮が呼んでおりますぞー」
途端、牀からガタッと立ち上がる張飛。
「じゃあな子龍」と一言残し、妻方の親戚に当たる夏侯博、夏侯纂のもとへと駆け寄っていく。三人は連れ立って渡り廊下の向こうへ去っていった。
(夏侯蓮殿もまた随分と亭主をこきつかう…)
一人残った趙雲は、自分よりもずっと年下の妻・夏侯蓮に尻に敷かれっぱなしな張飛を思い、可笑しいような気持ちになった。
おおかた息子の張苞絡みの何やかやだ。
今年に入って新野の城は一日中赤子の泣き声がそこかしこに響くようになっていた。
四月の始めに鴻芙蓉が劉禅を産み、その半月後に王貂蝉が関興を産み、五月に入ってすぐ夏侯蓮が張苞を産んだ。父親三人はもちろんのこと、劉封、関平、関玲綺らも三人の弟達を目に入れても痛くないほど可愛がり、熱心に面倒を見ている。
それは嵐が訪れる前の、束の間の幸福だった。
趙雲子龍、当年とって三十二歳。相も変わらず見合い話を断り続ける日々である。
博望坡が燃えている。
辺り一面、見渡す限り火の海だ。
諸葛亮の策に従い、夏侯惇率いる曹操軍の先鋒を劫火をもって退けた趙雲。谷を、山を、敵兵を、あらゆるものを呑み込み焼き尽くす炎。
視界のすべてが紅だった。
風上にいる己の頬にもピリピリとした痛みが走る。
(………)
趙雲はふと、何かの予感にかられるように、愛馬・白竜を駆って燃え盛る博望坡へと下っていった。
黒煙の中を這いずりながら落ち延びていく数多の兵。
見回す。
視線を四方に走らせる。
「……?」
それは、ある種の超常的な勘であったのかもしれない。
趙雲の目が、舞い散る火の粉の向こう側に、一人の男の姿を捉えた。
混乱の中で冠を失ったのか、結い上げた髪がひどく乱れて顔面も煤まみれになっている。加えて煙にまかれて袖で口元を覆っているものだから、どうにも顔がよく見えない。
が、趙雲は、その奇妙なまでの確信に従って“彼”のもとへとまっすぐに駆け寄っていく。
“彼”はゴホゴホせき込みながら黒煙の中に突っ伏した。
「!!」
その束帯を趙雲の手がグイと掴む。男の体が軽々と宙に浮き、瞬く間に白竜の背へと担ぎ上げられていた。
文官服のその男は、突然のことに声も出ぬまま鞍上で身を強張らす。
趙雲は、ひとまず炎の谷を抜けることにした。
劉備が待機する自陣、その少し手前の道で、趙雲は男を鞍から下ろす。
続けて自らも馬を下り、茫然としてその場に膝をつく彼に目線を合わせ、しゃがみ込んだ。
「………」
「…夏侯蘭殿」
「……え、」
「久しいな、夏侯蘭殿…私は趙雲、趙子龍だ」
「え……あ、え、」
「そうだ、道を挟んだ向かいの家の趙雲だ。覚えているか、あの日、君は私を見送ってくれたね。風の冷たい冬の日だった」
「趙雲さん……まさか」
夏侯蘭は額にかかる乱れた髪をかき上げて、信じられぬといった様子で趙雲を凝視した。
故郷の村でのあの別れから、ゆうに十七年の歳月を経た再会だった。
夏侯蘭を連れて帰陣した趙雲に、劉備はその目を丸くした。
慌てて新野にとって返し、留守居役の夏侯博、夏侯纂を呼びにやる。
知らせを受けて飛んできた両名は、趙雲の横に立つ煤だらけの従兄弟の姿に、歓声を上げるやら号泣するやら大変な騒ぎである。夏侯一族の従兄弟三人がこうして一堂に会すのは八年前の許昌以来だ。
少し遅れて、夏侯蓮が息を切らして広間へと駆け込んできた。
「兄上!」
「おおっ、蓮!」
兄妹は涙ながらに固い抱擁を交わす。
八年ぶりの再会に感極まって二人はひたすらに泣いた。
瞬間、趙雲の脳裏に、常山・真定の遠く懐かしい山河がふっと甦る。
幼い時分に夏侯蘭、夏侯蓮と共に遊んだ生家の庭が、陽炎のように浮かんでは目蓋の奥へと消えていった。
夏侯蘭は劉備に投降の意を伝え、即日、軍の法務を司る軍正に任じられることとなった。
「子龍よ、夏侯蘭から話は色々と聞いたぞ。いやいや、まこと人の縁とは、かように不可思議なものよのう」
しみじみと感慨深げに言う劉備。
主君に深く一礼し、暮れゆく西の茜の空を無言で見やる。
黒い嵐が間近に迫った建安十三年六月―――それは炎が導いた奇跡のような邂逅だった。
続く
戻る