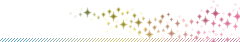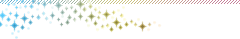
落日・5
◆劉封の字が「公徳」、関平の字が「長生」です。
◆張飛と夏侯蓮の結婚は『最強武将伝三国演義』設定に従います。
建安十一年五月。
河北の四州が曹操の支配下に入り、趙雲の故郷・常山も遥か彼方の地となった。
毎年のように各地で戦乱が起きた。
諸侯の軋轢、豪族同士の競り合いに賊徒の跋扈。国土は荒れ果て、民衆の疲弊は増す一方だ。天下は未だ混迷の内にある。
流浪の末、劉備とその一族郎党は、劉表の庇護のもと荊州新野にひと時の安住を得た。
鴻芙蓉は建安八年の夏に双子の娘を産んでいた。齢四十二にして初めて我が子をもうけた劉備、その喜びはひとかたならぬものがあり、情愛のすべてを二人の娘へと注いだ。
劉永と劉理、三歳になる可愛い盛りの姉妹の手を引き、春の花咲く野に遊ぶ。幸福な時間であった。それは波瀾続きの劉備の生涯において、もっとも優しく、穏やかな日々であっただろう。
一方、趙雲はといえば、まったく幸せでなかった。
念願叶って愛する劉備の側に在るにも関わらず、彼は不幸せなのだ。
鴻芙蓉が憎かった。
双子の娘が疎ましかった。
母親にそっくりな顔をした劉封までもが邪魔くさかった。
歪んだ嫉妬は趙雲の内なる獣、その牙を、ゆっくり研ぎ澄ませていった。
誰も知らない。
気づくこともない。
趙雲子龍の特異な精神構造は、その凄まじいまでの悪感情を微塵も面に滲ませない。
内心密かに怨みつらみを溜め込みながら、趙雲は鴻芙蓉にひたすら忠実に振る舞った。どこから見ても家臣の鑑そのものだ。彼は劉備の妻子にとって、誰よりも頼りに出来る清廉な忠臣だった。
春の日射しが降り注ぐ新野の城の庭先に、カンカンと乾いた音が鳴り響く。
鍛錬用の杖を手にして趙雲相手に棒術稽古に励むのは、関羽の養女・関玲綺である。
七つの年に実父の呂布と死に別れた少女は、先日めでたく十五の誕生日を迎えた。端正な容姿で体つきも娘らしく優しげではあるものの、人並み外れて筋力があり、背も高い。義母である王貂蝉も七尺という女としてはかなり長身の部類になるが、玲綺はまた、その貂蝉の背丈を追い抜かんばかりの勢いで日々育ちゆく。
完全に実父の血だ。
その細腕のどこにそんな力があるのかと思うほど、尋常でない握力、腕力を持っている。
玲綺は持って生まれたその力を持て余すかのように武芸の道に勤しんだ。
幼い頃から共に育った劉封と関平は、長じるにつれ「女のお前が俺達と一緒に剣の稽古をする必要があるのかね?」と度々玲綺に尋ねていたが、そんな問いにも彼女は“どこ吹く風”である。
王貂蝉はしょっちゅう玲綺に説教をした。剣を振り回すヒマがあるなら歌舞音曲と礼儀作法を学びなさいと、三日に一度は激しく柳眉を逆立てている。
妻の剣幕に恐れをなしている関羽だが、さりとて可愛い娘に説教をして自分まで疎まれたくはない。張飛もやはり貂蝉の怒気にすくみ上がって玲綺に稽古をつけようとしない。
自然、玲綺が武芸の師として頼る相手は、趙雲ただ一人となった。
「化粧は嫌いか?」
打ち合いの最中、趙雲はなんとはなしに問うてみる。
杖を振る手を止めることなく玲綺が返す。
「好きですよ」
「簪は? 金の腕輪や耳飾りは?」
「もちろん。どれもみんな好きだし、欲しい」
「歌うのは? 舞は? 母君について学べば国一番の舞姫となれようものを」
と、玲綺が困ったような笑みを浮かべた。
「歌舞はダメです。なんだか性に合わなくて。公徳にやらせておけばいいでしょう」
「書物はどうだ、父君に春秋を学べば徳と道義を究められるぞ」
「長生にやらせておけばいいでしょう」
事も無げなその返答に、趙雲は思わずクスッと小さく笑う。
少女の自由なその心持ちが、三十路を迎えた己の目には眩しく感じられるのだ。
(十五か。若いな。本当に若い。大人なようでまだまだ子供、自由と不自由の狭間に遊ぶ年頃だ)
ふと、眼前の少女に、関羽と張飛に稽古をつけてもらっていた当時の自身が重なった。
十五歳。苦悩と焦燥に満ちた灰色の世界を生きていた。劉備と出会った。すべてが変わった。愛と苦悩と、なにもかもすべてあの日に始まった。
「……」
急に黙りこくってしまった趙雲に、訝しげな様子で声をかける玲綺。
「…趙雲殿」
「……」
「趙雲殿、いかがされました?」
「…なに、昔の事を思い出していた」
「昔の事?」
「そなたと同じ、十五の頃の自分をな」
「へえ、なんだか興味深いですね!」
好奇心もあらわに身を乗り出して訊いてくる。
「教えて下さい趙雲殿、昔はどんな子だったんですか。十五の頃から豪傑やってたんですか」
「気になるか?」
「ええ、気になります」
「そうか、そんなに気になるか。フフ……そう、今のそなたの年の頃、私は…」
「はい」
「十五の私は…恋をしていた」
間髪入れずブフッと吹き出した玲綺。
ウフフアハハと笑い出し、次第に加速していって、ヒーヒーゲラゲラ爆笑に発展していった。
よっぽど可笑しかったのか、手を叩き、腹を抱えて涙目になっている。
趙雲はニヤニヤ笑いでそんな玲綺を睨めつけた。コイツめ、よくも笑ったなと言わんばかりの面持ちだ。
「アハハハ、ハハハ…フフ、恋ですか」
「ああそうだ」
「ウフフ……そうか、わかった、わかりましたよ」
「ん? 何がわかったというんだね」
「趙雲殿が結婚なさらない理由」
「なに、」
「その十五の時の恋の相手が忘れられずにいるのでしょう。当たりでしょ?」
図星であった。
しかし、趙雲の白皙の面に動揺などは見られない。
彼は薄ら笑いで玲綺に返す。
「勘が良いな、その通りだよ」
「いやいや、納得、納得です。見合い話を次々蹴られるその訳がようやく理解出来ました……趙雲殿は未だにそのお相手を想ってらっしゃるのですね」
趙雲子龍の頑なな独身主義に合点のいった十五の少女、感心することしきりといった様子になった。
「どんな方です? よっぽど素敵な方なんでしょう?」
「無論だ。素晴らしい方だ。後にも先にもあの方以上の存在はない」
「うわっ、そこまでおっしゃいますか。大恋愛をなさったんですねぇ。で、その方は今どこでどう、」
玲綺がそこまで言いかけた時…
「玲綺、一体何をしているのです!」
庭先に響くその一喝。
驚いた少女がピョンと猫の子のように飛び上がる。
趙雲の目も丸くなった。
「あ…これはどうも、母上…」
苦笑いで振り返る玲綺の視線の先に、怒りの形相もあらわな王貂蝉がいた。
彼女の後ろには、趙雲と同じく驚きに目を丸くした小柄な娘が立っている。張飛の妻の夏侯蓮だ。
「なんです、そんな棒切れなぞを振り回して! そんな事をしている暇があるのなら桑摘みをなさい、糸紡ぎをなさい! 刺繍の課題は済んだのですか!?」
「いや、まあ、それはその…」
「そなたは女の本分をはき違えてはいませんか!? 武芸などと物騒なことはそなたに必要ありません!」
義母の怒声に縮み上がり、その場から脱兎のごとく逃げ出す玲綺。
「あ、これ、待ちなさい!」
説教から逃走した娘のあとを追う貂蝉。
すれ違いざま、趙雲に向け「あの子にはお構いなきように!」と厳しい口調で言い放つ。
趙雲は神妙な態度でもって貂蝉に頭を下げた。
母と娘が去った後には、趙雲と夏侯蓮の二人が残された。
「とばっちりでしたね」
苦笑混じりに言う夏侯蓮。
趙雲はフッと笑って肩をすくめる。
「親の願いと子の願いとはなかなか噛み合わぬものです」
「難しいですね、色々と……あの子、玲綺の腕前は趙雲殿から見ていかほどで?」
「腕は確かだ。太刀筋も良い。そもそもあの子は生まれ持った資質が違うのですよ、腕力だけでも大人の男と同等かそれ以上のものがある。鍛え、磨けば、ひとかどの将と成りうるでしょう」
趙雲のその言に、夏侯蓮はフゥとため息をついた。
「そうですか…きっと義姉上はその事に気づいておいでなのですね。なればこそあのように声を荒げて…」
「……」
「趙雲殿、私も義姉上と同じくあの子が気がかりでなりません。十五の娘が剣を手にして果たして幸せなものか? 武芸は玲綺を幸福にするものですか?」
「わかりません。それは私にもわからない。何が幸せで何が不幸せなのか、それはあの子が決めることです。我々大人の思うようにはいきますまい」
夏侯蓮は沈黙し、どこか寂しげな眼差しでもって遠くを見やる。
許昌における夫・張飛との出会い、それはまさに、彼女が十五の年の出来事だった。
意に沿わぬ結婚を棄て、曹操と共に栄華を極めつつあった夏侯一族の家を捨て、想う相手のもとへと飛び込んでいった。
好いた男と安らぎのある家庭を作る。
それが女の幸せと思う。
戦の庭に馬を駆り、剣を振るうは、男の仕事であると思う。
なぜだろう、なぜ玲綺は自ら進んで危険な道を選び取ろうとするのだろう?
「趙雲殿からもあの子を諭してやって頂けません? やはり女が武器を持つというのはどうも…」
「私が言っても聞かんでしょうな。なるようにしかならんでしょう」
趙雲には趙雲の、夏侯蓮には夏侯蓮の“十五歳”がある。
その青春も、生き様も、人の道はみなそれぞれだ。若者に己の枠を押しつけてみても詮無いことなのかもしれない。
と、ここで趙雲が唐突に話題を切り替える。
「二十一、ですか」
「え? ああ、私の年のことですか…ええ、気づけば二十歳を超えてたりして…嫌ですね趙雲殿、女に年の話を振るなんて」
「その若さで何をおっしゃるのです。安心なさい、貴女はまだまだ立派な小娘だ」
「まぁ…」
「それはさておき、時の経つのは早いものだとつくづく思う。夏侯蘭殿の背におぶさっていたあの貴女が、いつの間にやら二十一とは」
「確かに…真定の村で趙雲殿を見送ったのは私が六つの時でしょう? うっすら覚えているような……ううん、兄の話を自分の記憶に置き換えているだけかしら」
夏侯蓮は兄を、趙雲は幼なじみの少年を、それぞれ懐かしく思い出す。
遠く離れた許昌の都に在る夏侯蘭。
再び会う日が来るのだろうか。
玲綺と夏侯蓮との語らいは、趙雲に“自己の幸福”を鑑みるきっかけを与えた。
(俺の幸福? 決まっているさ、劉玄徳だ。十五の頃から何ひとつ変わっちゃいない。あの方の存在こそが俺の幸福そのものなんだ)
趙雲殿は未だにそのお相手を想ってらっしゃるのですね―――先程の玲綺の言葉が脳裏にフッと甦る。
まったくもってその通り。
このままいけば多分一生独身だ。
朝晩に劉備の顔を見て、その声を聞き、仕草に魅入り、たまに同衾させてもらって、それで自分は充分幸せな人生…
(…そうなのか?)
本当にそれで幸せなのか?
「……」
趙雲はふと足を止め、色とりどりに咲き乱れるツツジの垣根に目をやった。
美しく咲く花弁の向こうに視線を移す。
その先にある、連れ立って春の庭を散歩する仲睦まじい夫婦の姿。
桃花と白芙蓉とが並んで咲いたその様は、たとえようもないほどに気高く麗しいものだ。
(…駄目だ!)
震える足で後ずさり、踵を返して足早にその場を立ち去った。
劉備と芙蓉の談笑に、耳をふさぎたくさえあった。
(駄目だ、ちっとも幸せなんかじゃない…俺は、俺の人生は、)
最低だ。
どうにかしてくれ。
あの女がいちゃダメなんだ。
あの女が玄徳様の側で笑ってる限り俺の人生はドン底だ。
惨めだ。きつい。つらい。虚しい。
(こんなはずじゃなかったのにな。戻りたい。戻してくれよ十五の時に。十五歳から人生やり直させてくれ。何が何でも玄徳様についていく、這ってでも後をついてくからさ)
春は狂気を育む季節。
日射しの中に膝を折り、花々の芳香に包まれながら、澱んだ呪詛を繰り返していた。
続く
戻る