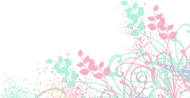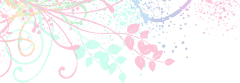
※少々お触り描写がございます

「ちょっと。折角仕事を持ってきてあげたってのに、もうちょっとしゃんとできないの?」
レディは呆れたように眉を吊り上げ、ソファに寝そべる大男を見下ろした。
「なんか、ダルイんだよ…アレだ。休みボケ」
ダンテは収まりきらずにソファからはみ出している足をぶらぶらと揺らし、半分寝ているようなぼんやり眼でのろのろとレディを見上げた。
クリスマスとニューイヤーのお祝いムードもすっかり落ち着いた1月中旬。世間はとっくに通常営業を開始しているというのに、この店の店主は未だ冬休み気分でいるらしい。
「普段から週休6日のバカンス状態のくせに、何言ってんのよ。もう依頼主には話してあるから、頼んだわよ?」
レディはメモが記された紙をダンテの眼前でひらめかせた。
反応の無いダンテに代わってネロの腕が伸ばされ、それを受け取る。
「『地所に生えた気味の悪い木を伐採してほしい』…?何だこれ、こんなの庭師か、業者にでも頼めよ」
「その木に夜な夜な悪魔がたかるんですって。襲われた人間はいないけど、気味が悪いから何とかしてくれって言うのよ。眠気覚ましの散歩代わりにはなるでしょ」
ネロはレディを見上げ、次に散らかった事務所内とキッチンの扉に視線を移し、そしてダンテの頭を見下ろしてこう言った。
「おい、ダンテ。行ってこいよ。ピザ解禁にしてやるぜ」
要するに、いつもながらの経営難で緊縮財政な台所事情をどうにかしろということだ。
「あら。2人で行ってきたら?って意味で話してたんだけど。ネロ、あなたも休みボケしてるみたいだし」
「俺が?どこがだよ」
「まぁ、私はあんたたちのプライベートには興味無いしどうでもいいけどね」
ソファに座り太股にダンテの頭を載せ、その髪を左手で撫でつけているネロにそう言い放ちレディはDevilMayCryを後にした。
紫がかった光沢のある蔦が幾重にも絡み合い、うねうねと波打った枝が方々に伸びている。高さは約3メートル。枝先に赤黒い花や緑色の実を纏ったそれは、まるで悪趣味なクリスマスツリーのようにも見えた。
「これこれ、こいつが生えてから周りの木はみんな枯れちまうし、夜には化け物が出るしで、散々ですわ。私もチェーンソーで切ってやろうとしたんだけど、全然だめでね。それで困ってたら、そういうの専門の人がいるって言うから、今回知人に頼んで紹介してもらったんだが…」
依頼主の老人はネロとダンテを案内しながらぺらぺらと喋り続けていたが、一呼吸置いて立ち止るとネロを見た。
「坊や、大丈夫かい?親父さんの手伝いは感心だが、無茶はいかんよ。お茶とパイを用意しておくからね、終わったら寄りなさい。女房の作るパイは近所でも評判で…」
ネロの眉間がぎゅっと寄せられ、ダンテは口元を押さえて顔を反らした。
2人のハンターの様子など気にも留めない老人のお喋りの内容が自宅で開かれている料理教室の生徒の事にまで及んだ頃、ようやくダンテが助け船を出して依頼主を家へと戻らせた。
「おい、ニヤニヤするな」
「まぁまぁ、いいじゃないか。あの爺さんからみれば、お前は10歳のガキと変わらないんだろうさ」
「クソ…俺はああいう年寄りは苦手なんだよ。逆らえない雰囲気が…」
ネロは孤児院のシスターを思い出し、呟いた。あの老人はおそらくネロが怪我をしているとでも思っていたのだろう。
するすると右腕の包帯を解き、悪魔の腕を解き放つ。
ネロが右手で掴んで引き千切ると、木はあっさりと折れて薄紫色の断面を覗かせた。
「何だ?随分脆いな」
「お前の腕だからだろう。こっちでも試して…」
ダンテの声が途切れた。ネロが振り返ると、右手にリベリオンを握ったダンテが地面に座り込んでいる。
「おい?」
ネロは切り裂いた枝を手に、ダンテの元に駆け寄った。
急にどうしたんだ、とダンテを覗き込む。するとダンテがネロの胸元に頭を擦り付け、そのまま凭れかかってきた。リベリオンが滑り落ち、ガランと音を立てて土の上に転がった。
「ダンテ?」
返事は無い。
「おい、俺一人にやらせるつもりか?ここまで来たんだから、あんたもいい加減に…」
仕事しろ。と続くはずだったネロの言葉はダンテの唇に塞がれて、飲み込まれた。
しっとりと柔らかい感触はすぐに離れ、去り際にネロの唇を軽く食んだ。情愛と性欲を混ぜ込んだキスではなく、じゃれつくような、甘えるような仕草だった。
固まるネロに構わずダンテは鼻先を目の前にある少年の首筋にぐりぐりと擦り付けてひとしきりその感触を味わうと、今度は舌でちろちろと舐め上げた。
さすがに堪らずネロはダンテを引き離したが、眦を薄紅に染めたとろりとした表情で見つめられ、反射的に喉が鳴った。
ぺたりと地面に座り込んだままのダンテの両腕がゆっくりと持ち上げられ、ネロの首に回される。ダンテはネロを抱え込むようにして地面に転がり、足を絡めてしがみ付いた。
全身を擦りつけ密着してくるダンテの感触に、ネロは身体の奥が徐々に熱くなってくるのを感じた。すぐ傍には依頼対象の木がそびえていて、あの老人がいつ様子を見に来るかもわからない。何よりダンテがこんな風にいきなり盛り出したのは初めてで、ネロは何から始めるべきなのか混乱する。
いや、もちろん依頼だ。分かっている。だがそうしている間にもダンテの太股がネロの股間を刺激し、背に回された両手がコート越しに背骨をなぞるように蠢いて、唇が頬や耳に押し付けられる感触と、荒い吐息に混じる微かなかすれ声と共にネロの意識を混濁させていた。
「ちょっと…待て、ダンテ、」
「ん…」
ネロの声など聞こえないかのように、ダンテは啄ばむ様な口付けをネロの頬に繰り返した。
「…ダンテ!」
ネロがダンテの肩を掴んで地面に押し付けると、あっさりと拘束は外れ、ネロの身体は解放された。
クソ、軽く勃っちまったじゃねぇか。と思いつつ、より状況を悪化させないためにとネロはダンテから目を反らし、視界から消した。
「とりあえず、今はあっちを終わらせようぜ。事務所に帰れば、いくらでも…」
言いながら立ち上がりかけたネロは、くいくいとコートを引かれて動きを止めた。
しまった、と思ったが遅かった。
「ネロ、」
まるでここが寝室のベッドの上だと錯覚させるような無防備な体勢で横たわるダンテと目が合い、ネロは思わずジーンズの尻ポケットを探った。
ゴム持ってたかな、と。
いつもは油断していると総て持って行かれそうになる舌技を仕掛けてくるダンテが、今日はたどたどしくネロに応えるので精一杯だという様に、何度も顔を反らして息継ぎをした。
それに煽られたネロが強引に口付けて舌を吸うとダンテはぴくぴくと身体を仰け反らせて鼻を鳴らし、益々ネロを喜ばせた。
「ふぁ…ネロ、ネロ…」
「ダンテ、かわいー…気持ち良い?」
「ん…ネロ、気持ち良い…」
うっとりと眼を伏せるダンテのインナーの前を開き、既に立ち上がっている突起を指先でなぞる。
熱い吐息を吐き出しているダンテの髪を軽く撫で、ネロは上がった体温で色付いている胸元に顔を寄せた。
「ん――…」
ネロの背に回されていたダンテの手が、コートを掴む。強請る様に腰を浮かせる仕草にネロの口元が綻んだ。未だかつてない可愛らしいダンテの姿を、今はとにかく楽しませてもらおうという気分だった。
ダンテの胸の突起を口に含んで弄りながら、震える腰をゆっくりと撫でる。窮屈そうなボトムのフロントに手を掛け、ジッパーを下ろして下着ごとずり下げた。
「すげぇな…。今日、どうしたんだよダンテ?」
「知、らない…っあ、ネロっ」
いきなり急所を握り込まれ、ダンテはネロにしがみついた。
「あ、あ、」
「一緒に弄られるの、イイ?」
ネロはこくこくと頷くダンテの硬くしこった乳首を舌で押し潰し、ヌルついて熱を持ったペニスを同時に扱いた。アナルと陰嚢の間をぐりぐりと刺激し、サオの括れと先端をなぞるとネロの手に熱い粘液が吐き出された。
「ネロ…」
忙しない呼吸を続けるダンテの頬に口付け、ネロは濡れた左手でダンテの後孔を探った。驚いたように指を絞めつけてくるそこを宥める様に緩く動かし、右手でダンテの耳を撫でる。
「ダンテ、ここで最後までしていいか?」
耳と首筋を撫でるネロの掌の感触に浸っていたダンテがゆっくりと瞼を開き、ネロを見た。
ダンテの左手がネロの右手に添えられ、笑みを形作った唇が異形の腕の指先に触れる。繰り返し施される口付けに、ネロは笑ってダンテと額を突き合わせた。
「キャットニップ?」
「みたいなもん、だったな。悪魔用の」
「へぇ、面白そうね。それ、取っておいてないの?」
「香油掛けて燃やしちまった。あんたへの土産は、これ」
ネロはレディの前に紙箱を差し出した。受け取ったレディが蓋を開ける。
「……アップルパイ?」
「依頼人に1ホール持たされたんだよ。食いきれないから、やる」
遠慮しとくわ、とレディは箱をネロの手に戻した。
「ダンテに食べさせなさいよ。あいつ、どうしたの?」
「上で寝てる」
「まだ休みボケとか言ってるの?仕方ないわね。じゃあ、今回の報酬。仲介料はいつも通り…ねぇ、ネロ?」
「ん?」
レディは丸めた100ドル札の束を、パイの箱の上に載せた。
「そのニヤケ面、はっきり言って気持ち悪いわよ」
「おいダンテ、レディ帰ったぜ」
「…そうか」
「なぁ、いい加減起きろよ」
「いいだろ、放っとけよ」
「腹減らないか?」
「別に」
「…………」
「…………」
ネロはダンテが包まっているシーツの端をつまみ、引き上げた。
「なー、昨日のなら俺は全っ然気にしてないぜ。むしろすげえ嬉し」
ダンテががばりと起き上がり、叩きつける勢いでネロの口を塞いだ。
「もう一度確認する。ネロ、あの木は燃やしたんだよな?」
ネロが頷く。口元からダンテの手が外され、ぷは、と息を吐いた。
「あんたも見てただろ?俺の右腕で引っこ抜いて、引き千切って燃やしたの」
ダンテが再びシーツを被り、ベッドの上に沈み込んだ。
燃え上がる木の匂いを嗅いだダンテにもう1度、とせがまれたのを思い出して、ネロはシーツの塊をぽんぽんと撫でてやった。
結局その時は陽が落ちて集まりだした悪魔達を始末しなければならなくなったので、事務所に帰るまでお預けになったのだが。燃え盛る木に群がる悪魔の様子と、ダンテの有様を見てネロは先程レディに報告した結論を導き出したのだった。
自分にも効いてたのかもしれないな、とネロはポケットを探り細長い小瓶を取り出した。その中に収まっている紫色の小枝を眺めて唇の端を吊り上げる。
(ダンテが忘れた頃に、使ってやろう)
終。
虎→ネコ科→またたび!
ということで…失礼しました。