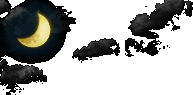
利戸鱒押し寿司
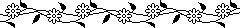
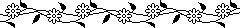
白木のカウンターだけの小料理屋は新しく、こじんまりとしていた。
5席しかなく、客は1組のカップルのみ。
それでも店がいっぱいに感じてしまうのは、女将がデ・・・・・・ふくよかだからだろう。
樽のような和服姿に前掛けをし、客に背中を向けてなにやら作っている。
「まってくれよ、妻に離婚したいって言ったんだから」
男が小さな声で、となりの女に囁いた。
「うそ」
男の首は細く、スーツの首根っこにはシワがよっていて、幅の合っていない肩にさらにシワを寄せながら女の方に体をねじった。
「本当だって。僕が愛しているのは君だけだ」
血走った大きなギョロ目で女を見つめるが、真剣すぎてかえってわざとらしい。
「もう2年同じこと言ってるじゃない・・・・・・」
女は男の方を向きもせず、箸を口に運んだ。
ゴーヤーの白和えをコリコリと噛みしめると、赤い口紅のついてしまった箸をそっと指先でぬぐった。
短い黒髪に、形のいい耳から伸びる首筋が白い。
のどが白和えを飲み込むうねりで蛇のようだ。
綺麗に上向きにカールされた睫毛は長く、薄っすら湿っていて、伏せると男の愛欲を刺激してしまう。
「赤ちゃんがほしいの」
「えっ」
大きな目をさらに見開いた男のこめかみに血管が浮き上がった。
女は馬鹿にしたように冷ややかに鼻で笑った。
「できてないわよ」
「なんだよ、びっくりするじゃないか」
男は椅子の背に沈み込むと、赤く脂ぎった顔を両手でこすった。
「あたし、もう35なのよ。産むのにもリミットがあるでしょ。早くしたいの」
「ああ・・・・・・うん、わかってるよ・・・・・・ちょっと、トイレ」
逃げるように男は席を立った。
女のため息が小さくカウンターを撫でた。
「お酒ください」
「はーい、はい」
のれんの奥にいた女将が腹を揺らしながら皿を持ってでてきた。
「お冷ね〜、おちょこふたつね」
氷のようなガラスの徳利と、おちょこを置いた。
みるみるうちに徳利の肌が白く曇り、女の手が徳利に伸びた。
男が戻ってくると女将はおしぼりを手渡し、奥から持ってきた皿をふたりの前に置いた。
「どうぞお。これサービス。鱒寿司作ってみたの。北海道から届いた、利戸鱒っていうのよお。結構珍しいのよお。高級魚ってやつ」
黒い皿に笹が敷いてあり、四角い押し寿司ならべられている。
「綺麗・・・・・・」
寿司の上に薄く乗っている鱒は、明るいピンク色だった。
「えぇ、鱒寿司ってさー、虫とかいるんじゃないの?」
「しっつれいねぇー!ちゃんと冷凍してるし、酢でしめてるわよっ!他に客がいたら叩きだすわよっ!」
女将は大きな頬をさらに膨らませて笑った。
女もつられて頬が緩んだ。
「俺、あんまり鱒寿司好きじゃないんだけどなぁ」
言いながらも、男は女の前にあった醤油の小瓶に手を伸ばした。
が、腕が徳利の口にあたって倒れた。
悪いことに徳利が倒れたのは鱒寿司の皿で、寿司は酒でビシャビシャの台無しになってしまった。
「あっ、あー、あー、あ、ああああ?」
皿の上で、信じられない事が起こった。
鱒の色が変わっているのだ。
それはどんどん変色し、青緑色になった。
「なんだこれ!?」
男は驚いて女将を向いた。
「あー、これね、利戸鱒の特徴なのよお。リトマス試験紙みたいなものよお。酸性だと赤くて、アルカリだと青ね」
女は動かない。
「へぇー、面白いな。これは珍しいよ」
男は感心した顔で何度も頷いた。
女は動かない。
「あれ・・・・・・日本酒ってさ、酸性じゃないのか?」
今度は女将も返事をしないで、おどおどしている。
男は何かに気づき、女の肩を掴んだ。
「お前!なんか入れたんじゃないだろうな!?」
沈黙が広がる。
鱒はさらに青くなり、それは強アルカリ性をしめしている。
強いアルカリ性の毒といえば、男にも想像がついた。
「だって・・・・・・だって・・・・・・」
俯いて顔が見えないが、膝の上でギュッと握られた彼女の手の甲に、数滴の涙が落ちた。
「・・・・・・一緒に死にたかった・・・・・・」
「ばっ、馬鹿野郎っ!なにやってんだよっ。」
男は女の肩を突き飛ばすと、女は椅子から崩れ落ちてうずくまった。
「だってぇ、だってええええ」
女の泣き声は、叫びに近かった。
「ふざけんなっ!冗談じゃねえよ。なんなんだよ、狂ってる・・・・・・お前とは遊びだったんだよ。二度と顔見せんな!」
鞄を掴むと、戸を激しく叩きつけるようにして男は出ていった。
女は鼻をすすりながらのっそり起き上がると、椅子に座りなおした。
女将は熱いおしぼりを差し出すと、首をかしげた。
「これでいいの?」
「ん、見たでしょ。・・・・・・すごいカス」
「好きで付き合ってたくせに」
女将がクスリと笑う。
「もう、悪い遊びは終わりなのっ」
女はおしぼりをひったくるように取ると鼻をかんだ。
「はいはい」
布巾を持った女将がカウンターから出てくると、濡れたカウンターを拭きはじめた。
「ね、利戸鱒ってすごいね?」
「うふふふふー、そんなの無いのよお。あたしのお手製。濡れてない?平気?」
「大丈夫。でもすごいわ。こんなの作れるなんて。おかげでアイツと切れられたし」
女は女将が持った皿の中の青い鱒をこわごわと覗き込んだ。
「紅芋の粉にまぶして、魚のリトマス試験紙作ったってわけよ。だてに、元理科の教師じゃないわよお」
誇らしげに大きな胸をはって、二重あごを反らせる女将は、トドのように頼りがいがある。
「あはは、でもアイツが自分でこぼすとは思わなかった。ウケるんだけど」
「うまくやったわねえ」
「お酒に何が入ってたの?本当に毒・・・・・・?」
「そんな怖いことするわけないじゃないのお。これよ、これ」
女将はビニール袋に入った白い粉を振った。
「ベーキングパウダー。じゅ・う・そ・う。それに、それお酒なんかじゃないわよお。水に重層溶かしただけ。お酒だったら、勿体ないでしょお」
「げ」
「飲んだら不味いだけ。苦いわよお」
ニタリと笑った女将は、
「よう子ちゃん、美味しい『わさび茶漬け』あるんだけど、食べる?冷やしで」
「うん、食べるぅー」
「永○園だけどね」
よう子も笑う。
戻る

