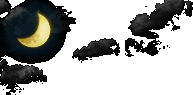
飛行場の見える海辺
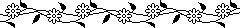
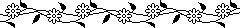
幸せになれない恋だから、逃げた。
衝動的に、A4のコピー用紙に書きなぐった退職願を上司の机に放ると、そのままの勢いで空港に向い、国内で一番遠い便に飛び乗った。
機内で、隣の老紳士が不思議そうにしていたが、不躾な視線は向けられなかった。
ひとみは事務服のままで、もっていたのは財布と化粧入れにしている、小さな巾着袋だけだった。
海の際にある滑走路に着陸したのは、夕方だった。
初めて来たその土地は、むっとした空気でひとみを包んだ。
行くあてもなかったので、タクシーに一番近いホテル、と告げた。
タクシーの運転手は、ホテルの名前を言うと車を走らせた。
ひとみはホテルの名前など、どうでも良くて、ただ早く眠りたかった。
空港から近いそのホテルは、小さな島の上に建っていて、その島は海中道路で大きな陸と繋がっている。
丸に近い形の島をぐるりと取り囲んでいるのは、南国特有の海で、観光客にうけそうだ。
幸いにもその時期は閑散期で、ホテルの部屋は沢山空いていた。
ひとみは部屋に入るなり、ベッドに倒れ込んだ。
体は元気でも、心の疲労感が半端じゃなかった。
考えることをやめたひとみの脳は、すぐに眠りの状態に落ちた。
潤一とは、同じ課だったがグループは違っていた。
だから、一緒に仕事をしたことはなく、歓送迎会や打ち上げなどの飲み会の席での彼しか知らなかった。
話が上手く、冗談が好きな潤一と酒を飲むのは楽しくて、気づくとひとみはいつも潤一の隣を陣取っていた。
潤一も満更ではないようで、そんなひとみを社の行事以外にも誘ってくれるようになった。
40を目前にしたひとみには彼氏が無く、他に飲みに行けるような男の友達も無かったから、潤一の誘いに特別な気持ちを抱くのは当然の流れだった。
ふたつ年上の彼は博識で、ひとみを飽きさせることはなかった。
この上ない優しさを持った男性をひとみは他に知らなかった。
理想のひとだった。
左手の指についた、余計なもの以外は。
何度か二人きりで飲みに行くようになり、そのうち体の交渉も持たれるようになった頃から、ひとみは夢をみるようになった。
それはいつも同じで、どこかの診察室で覚悟を決めるという夢だ。
両腕を切断しなければないという夢。
何度もみるその夢は、いつでも新鮮なショックと恐怖とあきらめをひとみに与えた。
毎回、あきらめを感じた瞬間に目覚める。
ごおという、雷にも似た音で目が覚めた。
開け放たれたカーテンからのひかりで、ひとみは朝まで眠っていた事を知った。
あの夢をみなかったのは久しぶりで、少し体が軽くなっていた。
仕事を辞めたからか、遠くまで来たからか。
起き上がり、ベッドの端に座って窓の外を眺めると、飛行場が対岸に見えた。
バルコニーに出てみると、長い滑走路の全体を見ることができた。
外に出ると自衛隊の飛行機が飛び立つ轟音がさらに大きい。
それから暫く、ひとみは旅客機が何機も降りて、飛び立っていくのをただぼうっと見ていた。
双眼鏡が欲しくなった。
双眼鏡で覗いたら、パイロットの顔が見えるだろうか。
地上で働くひとは。
機内の人は。
こんな朝から、見送りの人もいるのだろうか。
管制塔にはどんなひとがいるんだろう。
視線をおろすと、ホテルの駐車場から下に繋がる斜面のむこうに浜辺が見えた。
ひとみは無性に海に入りたくなった。
波打ち際であるはずのところで、ひとみはがっかりした。
遠くからは白い砂浜に見えたが、引き潮の時間帯らしく、波打ち際まで数十メートルがごつごつした珊瑚や岩だった。
海に入りたい。
裸足では怪我をしそうな足元に、仕方なく黒いプレーンのパンプスのまま進んでいく。
岩の窪みにヒールが嵌らないように、爪先だけに体重を乗せて海水に浸かっていくと、やがて膝の深さまできた。
事務服の裾が濡れたことには気をとめない。
ポケットから大事そうに取り出した携帯で、メールを開いた。
彼からの文字を味わうようにして読むと、画面にそっと口づけした。
そして、ゆっくりかがむと携帯を海の水に沈めた。
携帯を海の底に残したまま、ひとみは陸の方へ向きを変えた。
珊瑚礁か岩に躓いて転んだ拍子に膝をしたたかぶつけた。
立ちあがると小さな膝頭から血が流れていて、それは服から滴る海水でオレンジ色に広がった。
ひとみは痛くて泣いた。
戻る

