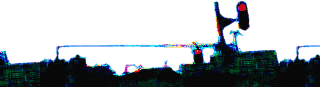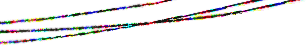
別に何を思ったわけでもなかったんだ。何も、ただ──そう。夜中になんとなく目が覚めて、寝返りを何度かうって、でも寝れそうにない。仕方がないから、水でも飲もうとリビングに出た。もちろんというか、特に違和感もなく真っ暗。けれど明かりをつけるほどじゃないな、少し目を擦って、暗さに目をならしてから、よし、と、そのまま流しまで向かった。
案の定辿り着いて、コップを出そうとした時に、僕はきっと油断していて、ガラスが手から滑り落ちていく感覚。しまった、と思ったはいいけど、反射の足りない僕は一瞬固まってしまって、ああ起こしてしまうかもしれないと、妙に冷静な頭はそんなことを考えていた。
予想に反して、しばらく経っても音はしない。確かに落としたはずだったのに、としゃがみこんだとき、額に冷たいものが当たった。そんなことを全く予想していなかった僕は、自分でも情けなく「うぇッ?!」と声をあげて、急いで口を押さえた。もう遅いんだけど。
前にいるであろう誰かによく目を凝らす。窓は向こうだから、ちょうど逆光で、流石に見えない。僕より大きいのは確かだけど、それは結構居るしなぁ、あ、これ考えるのやめよう。
ちょっと判断に困っていると、また僕の額にコップが当てられて、静かに調理台に置かれた音がした。まだ置いてなかったんだ。僕だって相当の良心はあるわけで、素直に「ごめんね、ありがとう」と礼を言うと、相手は一瞬止まって、それからクスッと笑い声が聞こえた。おかしいことを言った覚えは無いから、当然困惑して、けれど、けれどそれよりも、その笑い声は、過去に──もっと嫌な響きを持って、もっと嘲る調子を含んで、僕の記憶にこびりついていたものだった。
「お前──『冴える』…ッ!」
ソイツは少しの間を開けて、堪えきれないような笑いを漏らした。静かで、確かな。嘲笑う意思を持って。笑うのを止めたかと思えば、途端腕を掴んで持ち上げるように引く。バランスを崩し、倒れこむ僕を支える体勢で耳元に近付いて、囁いた。何度も聞いた、あのするりと這い寄る蛇のような調子。
「なんだ、気付いてなかったのか?随分夜目が利く様子だったのに、なぁ?」
「ッうるさいな、それよりなんで──」
こんなところで明かりもつけないで、と続けるはずの口は、わし掴むように塞がれた。
「あまり騒ぐなよ、他のが起きるかも知れねえだろ?」
さっき腕を引っ張られたときに少し向きが変わったのか、少しだけそいつの顔に月明かりが差す。見下ろす金色の目が淡く光っているように見えた。一気に気分が下がって他所を見る。手が離れる気配がないから、ついでに腕を叩いておいた。思ったよりもすんなりと手が退く。
「なんだよ、乱暴だな。ガラスコップ、落ちる前に拾ってやったのに」
「…、頼んでない。もう最悪、居るなら電気つけるなり居るって言うなりなんかできないの?」
「今は深夜…3時あたりか、消灯して静かにする時間だろ」
「そういうの屁理屈って言うんだよ。学んでよ、頭いいのが唯一無二の特徴でしょ」
「じゃあ君のそれは我儘だなあ、『欺く』。更に嫌味を覚えたか」
「どっかのクズのお陰でね」
そりゃいいなと笑うそいつ。何が楽しいんだ。僕は全く、まったく──なんだっていうんだろう?
もう半ばヤケになって、コップに半分くらい水を注いで、一気に飲み干した。冷たい感覚が身体を通る。でもすぐに消える。なんとなくモヤモヤする気持ちは消えなかった。いい加減部屋に戻ろう、布団を被っている方が絶対いい。コップを流しに置いて、さっさと踵を返す。けど、途中で立ち止まる。振り返ったりは絶対に、しない。
「…ねえ」
「なんだよ?コップ洗っとけとか言うなよ」
「じゃあ洗っといて」
「なんだそれ」
「……僕、キミのこと、好きにはなれないから」
もうなにも聞かずにそのままさっさと部屋に向かって、勢いよく…はならないようにドアを閉める。うるさくしちゃ意味もない。バフッ、とベッドに倒れこんだ。余計なことを考えないようにと努めるけど、そういうのは大体逆効果だと思い知っている。とりあえず目を閉じて、羊でも数えてみようか?いっそ寝ないのもいいかもしれない。とりあえず、変な時間に寝て、朝、キドに怒られなきゃいいけど。