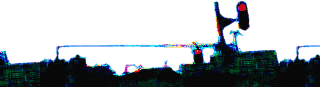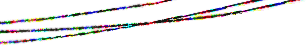
やることがない日、っていうのは、つまり、なんでもできる日だから、いい日だと思う。
冷蔵庫にコーラがまだひとつ残っていたから、手にとって、ソファーでテレビを眺めている彼を呼んでみた。彼と同じ色のヘビがこっちを見たけど、本人はなにも言わない。でも、それはよくあることだから、別におかしなことじゃない。
「ねえ」
「…どうした」
彼が座っているソファーの後ろまで行って、少しのぞき込むように呼んでみると、今度はこっちを見て、返事をしてくれた。僕は手に持ったコーラを少し揺らす。彼の視線はそっちにいって、また僕に戻った。
「なんだ」
「コーラ」
「それは知ってる」
「飲む?」
「……」
「おいしいよ」
シンタローが教えてくれたこと。暑い日は、特においしい。
僕が知ったことは、彼にも教えてあげたくなる。彼は、僕よりもずっと頭がいいから、教えてあげなくっても知っているかもしれないけど、思ったことは、一緒に持っていたい。
「…少しでいい」
「うん」
興味を持ってくれたみたいだった。蓋を回すと、プシュッとめずらしい音がする。そこも好きなところ。彼は少し眺めた後、ひとくち飲む。ちょっと味わうみたいに待ってから、喉が動いた。
「うーっす…お」
「あ、シンタロー」
「おうコノハ…と、クロハもか。他は?」
「わかんない」
「そうか」
ドアが開いた音がしたから、振り向いたら、シンタローが手をあげて入ってきた。来たときに話してないから、エネもいないのかもしれない。シンタローは歩いてきて、ちょっと考えた後、彼の隣に、少し空けて座った。ついでに僕も、シンタローとちょうど反対、彼の隣に座る。
「…ん」
「あ、ねえ、どうだった?」
「好んで飲みはしないな」
「嫌い?」
「じゃない」
「なんだ、お前もコーラなんて飲むんだな。珍しい」
「…勧められたからだ」
彼も味は嫌じゃなかったみたいだから、安心して、コーラを受け取る。そのまま僕も飲んで、テーブルに置いた。シュワシュワとする液体が喉を通る。コーラはおもしろいと思う。思い付いたひとは、きっとものすごい人なんだろう。
「あ、あのね、コーラはシンタローが教えてくれたんだよ」
「へえ、肥えるな『最善策』」
「失礼だな!そんなことねえよ!」
「君の不健康な生活で痩せるなんて思えねえけど?」
「うッ…コノハは基本体型維持だもんな…あんな食ってんのに…理不尽だ」
「『醒める』の蛇がそういう存在なんだよ」
「…じゃあ、一緒?」
「僕は違う、が、そもそもそんなに食わねえよ。動くしな」
「憐れんだ目でオレを見るなオレを!」
大きな声を出して反論するシンタローを、クスクスと目を細めてからかう彼は楽しそうで、見ていると僕も楽しくなる。
「2対1じゃ分が悪い…、…そういやクロハ、お前一人称 ”僕” なんだな」
「…女王に言われてんだよ、『醒める』に合わせろって」
「僕とおそろい?」
「何が楽しいのかはわからねえけど」
「口悪いのにな。楯山先生の移ったのか」
「それは仕方ねえだろ、普通は真似なきゃいけねえんだし、アイツが最後だったし」
「長かった恋人かよ」
「うるせえ」
「おそろい…」
「いつまで喜んでんだ」
おそろいには気付いてなかった。マリーが言ってくれたんだ、今度、ありがとうって言わなきゃ。
彼とシンタローはまだお話している。コーラはぬるくなる前に飲まなくちゃ、二人のお話を聞きながら僕は、やっぱり、今日はいい日だと思えた。