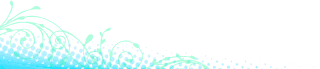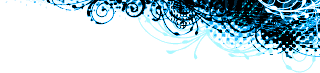
「どうしたの、ライドウちゃん」
其処には、さっき出掛けたばかりの書生が立っていた。
もう雷堂にあげる大学芋は買ってきたの、という言葉は笑って流し、実は、と続ける。
「自分は、鳴海さんに隠していたことがあるのです……」
鳴海は、おまえは隠し事ばかりだけどね、と笑う。
「それで?隠し事って?」
真っ直ぐ鳴海を見つめたまま、ライドウが笑っている。
「自分は、純粋な人の子ではないのです。狐の血が混じっているのです……」
一瞬、まさか、とも思ったが、この子ならおかしくもないか、と妙に納得もした。
「だから…、こんな満月の晩には、耳と尾が生えてくるのです……」
つい先程まで明るい時間の筈だったのに、夜空に月が輝いていた。
ゆっくりと学帽に手をかけたライドウに釘付けになる。
その弓月の学帽からひょこりと、白い耳が―――
「……っ!!」
がばっと顔を上げると、雷堂がびくりと一歩下がった。
「ら、雷堂……お、おかえり……」
「うむ、驚いたぞ。……しかし、こんな昼間から昼寝とは、此処の鳴海殿も彼方の鳴海もそう変わらぬのだな」
くすりと笑われた。
「いやあ、変な夢を見ちゃってね」
ライドウがさあ、自分には狐の血が混じっているとか言って、帽子をとるんだよ。
雷堂は馬鹿にするでもなく、真面目に聞いていた。
業斗が可笑しそうにしている。
「で、帽子の下から耳が出てきてさ……」
変な夢だよね、と笑うと、雷堂もにこりとした。
それは何時もの雷堂の笑みとは違い、どちらかと言うとライドウに近い笑い方だった。
「そうか……、果たして、それは本当に夢か?」
「え?」
くく……、と俯きがちになった雷堂が学帽を取ると、耳。
「え?」
* * *
「雷堂、帰っていたのですか」
収穫はありましたか、と聞いたライドウは長椅子で昼寝をしている鳴海を覗きこんでいる雷堂を不思議そうに見た。
「所長がなにか?」
「何やら魘されているので、気になってな」
「へえ……、ところで雷堂、大学芋を買ってきたので、お茶にでもしましょう」
その言葉を聞いて、雷堂は、まあそのうち起きるだろうと、さっさと鳴海から離れた。