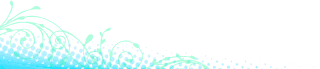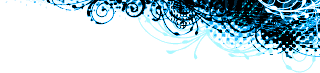
最近は帝都も、其の場所以外も、あまり目立ったことは起こらない。
だから自分が葛葉ライドウを襲名して、彼の人物と同じ様に帝都守護の任につけたのは運が良かったのではないか、とも思っている。
最も優秀だった葛葉ライドウが居た時代が、一番と言っても良いほど沢山の事件があったらしい。
葛葉の老人達が口を揃えて「十四代目の様に強く為れ」と言いつつ、「十四代目の様には為ってはいけない」とも言う。
「十四代目葛葉ライドウ」は歴代のライドウの中でも飛び抜けて優秀だったと聴かされている。
其の実力は初代と並ぶかも知れぬ、と老人は洩らした。
其の十四代目の様には為ってはならないとは。
昔は混乱し、手当たり次第に十四代目とはどの様な人物だったのか聞いたことがある。
しかし、其の誰もが口を濁し、はっきりとは教えてはくれ無かった。
今でも理由が気になる事もある。
あるが、考えてはいけないのだと思っている。
目付役は、そんな事はどうでもいいのだとしか言わなかった。
彼は本当にどうでも良さそうで、興味が無いらしかった。
そ、と横を見ると目付役の姿が目に入る。
尻尾を左右に揺らして、ゆったりと歩いているのは何時も通りなのだが、どうも蒼灰の目で辺りを見回したりと落ち着かない様子だった。
「ゴウトさん……どうかしたんですか」
返事は無かった。
彼は何時だって言葉少なだった。
蒼灰の目。
業斗童子の目は、マグネタイトを帯びるが故に通常は翠だと言う。
然し、彼の瞳は美しい蒼灰だった。
彼には何と無く聞きづらいので、報告の際に老人に何故かと聞いた事があったが、「数多く居る業斗童子の中には多少変わったのも居る」としか言われなかった。
「…………?」
三歩程、前を歩いていた目付役がいきなり立ち止まって、様子を見れば毛を逆立てている。
悪魔に其の小さな身体を掬われそうに為ってもあくまで飄々としていて、そんな姿は一度として見た事が無かったので酷く驚き、同時に目付役の視線を辿った。
「…………!?」
前から歩いてきたのは一人の男だった。
殺意も感じられないし、敵のようでもない。
何故目付役はこんなに警戒しているのだろう。
分からない。分からないが、目付役がこれほどまで警戒するという事は、何かあるのかも知れない……
立ち止まって居るのもおかしいので、また歩き出し、そして、然り気無く何時でも刀を抜けるように体勢を整えた。
男はどんどん近づいてくる。
もう少しですれ違う……
「警戒しているのが見え見えだぞ」
はっとして男を見ると、口の端をあげていた。
其れはまるで猫の様な微笑みで、何故か目付役を彷彿とさせた。
「そう警戒せずとも良い。昔おれは葛葉だったんでな。つい懐かしくて声をかけてしまった」
そう言って、ちらりと管を見せて、また口の端をあげた。
「…………」
目付役はまだ毛を逆立てている。
「でも、ゴウトさんは……」
男は目を細めて、すっと目付役を抱いた。
其れは素早い動きで、目付役は反応出来なかったのかしなかったのかは判らないが、身体を緊張させたまま大人しく抱かれていた。
「ゴウトさんを、知っているんですか」
男は小さな目付役の背中を労るように撫でながら、まあなとだけ答えた。
「……おまえで、何代目だ?ライドウは」
ふと顔を上げたかと思ったらそんな事を聞かれた。
「一五代目、ですが……」
ふむ、そうか。
其れだけ呟いて、おまえは馬鹿だなあと、誰に言ったかと思えば目付役に言っている。
「どうだ、此奴は。気難しいか」
からかう様に尋ねてくるものだから、目付役の手前、どう答えたらと思わず男の腕の中へ助けを求める。
目付役は、余計な事を言うなと無言で此方を睨んでいた。
男は肩を揺らして可笑しそうにしている。
「ええと……、厳しいですが、たまに褒めてくれますし……言葉は少ないですが、……み、見守ってくれます」
機嫌の悪そうな目付役を抱いて、とうとう男は声を出して笑った。
「ふっ、……はは、……そうかそうか、くくっ」
顔が熱くなるのを感じながら、はてどうしたものかと立ち尽くす。
「……そうだおまえ、大学芋は食べるか」
「…………?……いえ、あまりそういう物は……」
何だってそんな事を聞くんだろう。
男は此方の様子など気にした風も無く、また一寸目付役に笑いかけると「其処の角の店のは美味いから食ってみろ」等と言う。
「此奴にも食べさせてやれ」
「ゴウトさんは大学芋がお好きなんですか」
目付役に聞いても答えてくれ無さそうなので男に聞く。
今は腕の中に大人しく納まっている目付役は恐らく機嫌が悪い。とても。
「まあな」
男は終始愉しげで、目付役の喉を擽ったり爪を出し入れさせては口の端を上げていた。
暫く沈黙したかと思うと、
「……さて、おれはもう行くよ。邪魔したな」
と、唐突に別れを告げた。
そして、すっと目付役の耳に口を寄せ、何事か囁いた。
「……じゃあな」
何か言う暇も無く、目付役をすとんと下ろして去ろうとする。
「……あ、」
せめてものと思い、さようなら、と口を開きかけたら、目付役が猫のように鳴いた。
にゃおん、という小さな声に、軽く手を振って男は去っていく。
じっと見ていたつもりだったのだが、瞬きをする間に其の姿は消えていた。
帰ってからの目付役はずっとぼんやりしているようだった。
夜、目付役がふらりと散歩か何かに出掛けてしまって、独りで剣の手入れをしている時に会話を盗み聞きしていたらしい仲魔が教えてくれた。
「あの男がね、ゴウトちゃんに『必ず迎えに来る』って言うてたんよ」
迎えに来る。
一体どういう事なんだろう?
目付役に聞いても、きっと答えてはくれないだろう。
なんで最後に猫みたいに鳴いたんですか。
聞いた所で答えは無い。
明日は、大学芋を買ってみようと思った。