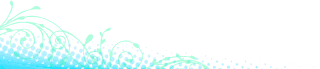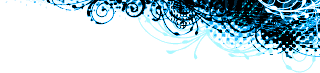
その底知れぬ気配は今まで対峙したどんなものとも似つかないものだった。
「……業斗よ、これは一体なんだ?」
刀に手をかけつつ訝る雷堂に、業斗はふうむと吟味するような声をだした。
「悪魔のようでいて、違うような……掴みきれんな。まあ、邪悪なようではないようだし、取り敢えず進んでみろよ」
警戒して辺りを見回す雷堂とは対照的に、のんびりとした様子で目付け役は言った。
雷堂は、業斗がそう言うならば間違いないとは思ったが、それでも念のため慎重に気配がする方へ向かった。
するとなんと其処には大学芋を持ったライドウが座っている。
こんな場所でなんと呑気なのだと、ぎょっとし、そしてライドウが一人でないことにさらに驚く。
様子を窺うと、どうやらその横にいる者こそが先ほどの気配の持ち主のようであった。
「おや、雷堂じゃないですか」
少し離れた場所からじっと動かずにいた雷堂に気づいたライドウが振り返ってやさしく笑んだ。
彼方の十四代目のことだからとっくのとうに雷堂には気づいていただろうなと業斗が雷堂を見上げると、どうしたものかと此方の十四代目は固まっていた。
悪魔の幻術に騙されているとでも考えているのかもしれない。
「そんなところに立っていないで、此方に座ったらどうです?」
いつの間にか近づいてきたライドウが、ほら、と手を引くがままに雷堂はぎくしゃくと足を進める。
雷堂にはこれは夢かと疑いたくなる光景だ。なんといっても此処はアカラナ回廊である。
しかし夢でも悪魔の仕業でもないだろう。
彼方の十四代目の気配は間違いなく本人の其れだった。
お前はこんな処で何してるんだという思いはぐいぐいと強引に手を引くライドウに上塗りされる。
そうして、雷堂はライドウに「はいどうぞ」と渡された大学芋を反射的に受け取り、反射的に礼を述べ、次に何とはなしにライドウの横でゴウトを撫でていた少年に目をやると相手も此方を見ていた。
上半身裸の少年は面白そうな顔をつくると、おもむろに口を開いた。
ちらりと覗いた犬歯がやけに尖っている。
「ライドウとそっくりだな」
雷堂がじっと観察の視線を走らせても、少年は笑みを崩さなかった。
其の少年の身体にはしる刺青のような紋様はぼんやりと光っており、また首の後ろにある角も人あらざることを示している。
恐らく悪魔だ。
ライドウに使役されているのかは知らないが、横で大人しくしているということはおそらく無害なのであろうと踏んで、「座ったらいいじゃん」と少年に促されるまま雷堂もその隣に腰を下ろすことにした。
「……ライドウは、我でもある。異世界の己なのだ」
雷堂がそう言うと、その悪魔はふうん、と言って、好奇心たっぷりにじろじろ雷堂を見た。
「姿かたちは何もかも似てるけど、気配はまるで違うんだな」
そう言って細められた金色の瞳は猫のようだが、犬のような親しみやすさを持った、不思議な少年であった。
悪魔であろうに。
戸惑いを隠せていない雷堂だったが、少年は気にもしていないようだった。
やがて二人のことを和やかに眺めていたライドウが口を挟んだ。
「雷堂にも、いずれ紹介しようと思っていたのでちょうど良かったです」
そう言ったライドウが最後のひとつである大学芋をつまもうとした横から、ひょいと悪魔の少年がそれを奪ってしまった。
「あ」
「うまい」
悪魔の少年は眦を下げて大学芋を味わっているが、雷堂はライドウが怒り出すのではとひやりとした。
なんと言ってもこの十四代目は大学芋に目がないのだ。
いくら一つの入れ物から食べ物を共有していたとしても、自分が食べようと思ったもの、ましてや最後の一つを他人にとられるなど良しとはしないはずだった。
それこそ刀を抜いても銃を構えてもおかしくない。
が、ライドウは「もう、仕様のない人ですね」なんて笑っているものだから、雷堂は目を瞠る。
どうやら、よほど気を許しているらしい。
「……使役しているのか?」
主従関係の割には仲が良すぎるので違うとは思ったが、どう聞いて良いものかと悩んだ末にそ結局そう聞いた。
ライドウはその辺りの線引きには厳しいし、今も少年に撫でられているゴウトはもっと厳しい筈だった。
一体どういった関係を保っているのだろう。
判断を下しかねる雷堂の頭の上には疑問符が浮かんでいた。
いいえと首を微かにふった異世界の己に、ではなんだと首を傾げる。
少年は横で妙におかしそうにしている。
ライドウはそっと口を開いて、歌うように囁いた。
「友達です」
ともだち。
聞き慣れぬ単語に、雷堂は鸚鵡返しにともだち、と繰り返す。
思わず目付役を視線だけで探すと、業斗はゴウトの横でライドウの手を避けながら目付役同士なにか話をしていた。
「そう、友達。ライドウは俺のただ一人の人間の友達なんだ」
だんだんと2匹の黒猫に集中し始めたライドウの代わりに少年が続きを答える。
それから少年は、自らを人修羅と名乗った。
元は人間だったとも。
「俺、らいどう……雷堂とも、友達になりたいんだけど」
いいかな、なんて照れる様は、とても悪魔には見えなかった。
自分の目付役をまんまと膝に乗せることに成功したライドウは口辺に笑みを漂わせて雷堂を見ている。
困った雷堂が業斗を見やれば、「別にいいんじゃないか。おまえも友達がいないのだし」と返され、少しむっとした。
確かにそうだが。
「…………宜しく、な」
こういう時、なんと言えば良いのかわからなくて、歯切れ悪くもごもご雷堂は言った。
一言では素っ気なさ過ぎたか?とちょっと心配して人修羅を見やると、嬉しそうに微笑んでいた。
「握手しよ」と、すっと人修羅が手を差し出す。
握手なんて、片手に数えるほどしかしたことが無かった雷堂は、おずおずと自らも手を差し出す。
ぎゅっ、と握り返された手は、悪魔にしては、温かだった。
雷堂がともだち、とまた口の中で呟くと、人修羅の笑みが深まった気がした。
「そ、友達。よろしくな、雷堂」
ニカッと笑う人修羅の後ろで、ライドウが微笑んでいた。