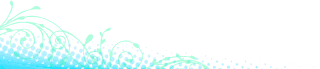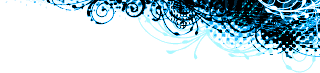
男が僅かに身動ぎすると、其の膝に頭を預けていた少年の手に更に力が込められた。
「…………痛い」
はあ、と息をつく。
少年に強く掴まれた手首が痛む。
「馬鹿力め」
むに、とあまり肉のついていない頬を摘まんでみても、余程深く眠っているらしくぴくりともしない。
其の癖、ひとの手首は掴んだままなのだから始末が悪い。
動こうとすると、逃がさぬという様に更にその手に力を込めるのだ。
男は、昔は猫の身体だった。
其の小さな身体で何時だって少年の傍に居た。
だが、今は違う。
猫の姿のままだったらなあと思う。
おれはずっとゴウトのままで良かったのだ。
そっと学帽を取って、少し汗ばんだ額に手を当て、其れから頬を撫でて、顎に沿わせると少年は気持ち良さそうに口許を弛める。
此奴の方がよっぽど猫のようだ、と思う。
だが人間の身体では膝を貸してやることは出来ても、昔のようにはいかない……
してやれる事は猫だった時より大分増えた。
代わりに猫だった時にしてやれて、今はしてやれない事もある。
そちらの方が、重要だった。
……おれが、昔の事を考えるなんてな。
己が今までした事を後悔した事も無い。
懐かしむ事はあっても、此れ程まで其の頃に焦がれた事も無かった。
「…ん……、ゴウト」
身動ぎしたと思ったら、とうとう少年は男の手を離した。
直ぐに、代わりと言わんばかりに着物の裾を掴んだのだが。
「…………」
手首には赤くなって痕が付いていた。
「なんて執着心の強い奴なのだ」
でも、つかまえていて欲しい、とも思う。
寝言でしか、呼ばれる事が無くなったゴウトの名。
次に目を開けたら、きっとおれの事を「ライドウ様」と呼ぶのだろう。
其れでも良い。
「……其の手、離すなよ…ライドウ」
不意に何処までも澄んだ蒼灰の瞳が恋しくなって、目の前の子供が早く起きないかなあと思った。