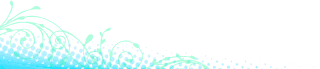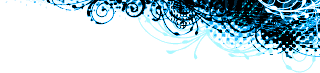
目線を合わせるように片膝をつき、腕を広げてライドウを迎える準備をした探偵に、子供は眉を寄せた。
「いきません。子供あつかいしないでくれませんか」
「んじゃ、オレが行く〜」
「あっ、ちょっと……!」
素早く脇の下に差し入れられた手に反応仕切れないうちに、ライドウの身体はぶらりと宙に浮いた。
「軽いなあ。そして可愛い」
「おろしてください……」
珍しく弱気な様子の子供の要求は笑って流し、しっかりと抱き抱える。
「おさな子なのは、みた目だけです。なかみまで後退してはいませんので」
何時もより少しもたついた口の動きに、鳴海の頬は弛みっぱなしだった。
「はは。ライドウ可愛い。いくつ位かな?4つ……よりは大きいか。5、6……?」
既に諦めたらしいライドウはその肢体を鳴海に預け、静かにしている。
「子供はあったかいなあ」
「子どもではありません」
わかったわかったと背中をぽんぽん叩くと、心地良いのか、頭も預けてきた。
「ライドウちゃん、眠いの?」
ライドウの身体は更に熱を持ち、冬は湯たんぽになるなあと鳴海は笑った。
「ねむくなど、ありません」
そうは言ってもどうやら寝る体勢に入っているようで、呼吸も静かになってきている。
鳴海は、ゴウトは猫の身体の習性に引っ張られるって言ってたけどライドウもそうなのだろう、と想像しては可笑しくて声を殺して身を震わせる。
子供なんて居ないし扱った事も全く無いので、子供の事は分からないが、なんか良いなあと一人ごちた。
「おやすみ、ライドウちゃん」
ちゅっ、と後頭部に接吻けると、腕の中の幼子は甘えるように首筋に頭をこすりつけた。