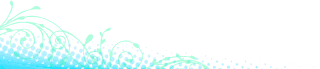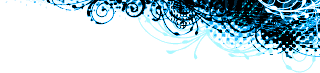
傷口がまるで心臓其の物に為ったかのように、身体の方々から痛む。
中でも酷いのは左足の太股で、其処は敵を薙いで息の根を止めたと同時に、最期の力を振り絞った相手にやられたところだった。
恐らく貫通している。
痛いし、動けない。
まるで木に縫いとめられたかのように、ぐったりと四肢を投げ出している。
誰彼構わず怒鳴り散らしたいほどの痛みだが、どうやって怒鳴るのか、そうしたら痛みは無くなるのかもどうかも血濡れの学生服が重くてよく解らなかった。
ただ、葛葉ライドウなら、葛葉ライドウとしてしなければいけないことはわかる。
すみやかに傷の応急処置をし、帰宅することだ。
こんなところで無様な姿を晒し続けるなど本来なら有り得ない。
「ライドウ……」
心配したゴウトが触るのも憚られる、といった様子で、そっと血と泥に汚れた骨ばった手に、柔らかな毛並みのその手を重ねてきた。
「ゴウト……大丈夫だよ……」
右手を伸ばして己の左手に重ねられた猫の前肢を握ろうとして、未だ刀を握ったままだった事に気づき、溜め息をついた。
手が固まってしまって、指が離れない。
刀を手放す努力も、今はする気力が無かった。
「無理をして動かなくて良いから……取り敢えず、まずは足を止血して、少し寝ろよ。休め」
手の僅かな動きで何をしようとしていたか解ったらしい。
其の悲痛な声に頷きながらも、ライドウは未だ瞼を閉じずにいた。
「ゴウト……」
其の掠れた声に、傍らの黒猫が目を伏せる。
「少し寝たら体力も少しは回復するだろう。止血した部分も大分マシに為っている筈だ。――だから」
何時もより口数が多い。
致命傷に直結する傷ではないのに、珍しくゴウトが慌てているのが可笑しくて、思わず口の端があがる。
まさか、投げ遣りに為って死のうとしているとでも思っているのだろうか。
この十四代目葛葉ライドウが……
何だか急に馬鹿馬鹿しく為って、哀しいような気持ちに為って、嗚呼此れが投げ遣りと言う状態なのかもなとぼんやり考えた。
傍の猫を抱き締めたくとも出来ない己が両手を呪い、また溜め息をついた。
その小さな溜め息に、傍らの小さな黒猫の耳がピン、と動いた。
「ゴウトに答えて欲しい事がある……」
「先ず寝ろ、その後に答えてやる」
知らない振りをして続ける。
「……僕と、ずっと一緒に居てくれるか」
「…………な、にを、いきなり……」
狼狽えた声。
ゴウトは答えられぬだろう。
其れは質問が唐突だっただけではない。
其れにもし答えるならば、其れは子供騙しの嘘かライドウの胸を切り裂く真実だ。
知っていてこんな事を言うだなんて、やはり自分は子供なんだろうなと思う。
「…………」
ゴウトは未だ口を開かない。
目も伏せったままだ。
嗚呼あの美しいマラカイトの瞳が見たいのに。
其れでも良いと、ライドウは殆ど諦めたような気持ちで瞼をそっと下ろした。
次に目を開ける時には、自分は十四代目葛葉ライドウに戻るのだから。
其の時だった。
「良いだろう。おまえが望む限り……此の身はおまえの物だ、……」
最後に真名で呼ばれた事に、はっとしながらも、ライドウは猫を見ることは無い。
ゴウトが此方を向いているかの気配も敢えて探らなかった。
たた、其れで良かった。
「うそつき…………」
子供は嬉しそうに只一言だけ呟いた。