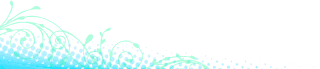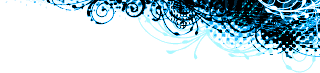
日は未だ傾こうともしない、そんな午後、少年は同じ白いシャツ姿の少年の膝に頭を預けていた。
そのうち傷のある方の少年が、弛くひとつふたつと左右に開かれたボタンをなんとなしに弄っていた手を、そっと膝の上の己と全く同じ容貌をした、だが傷のない少年の顎へと伸びて優しく擽った。
「………」
傷のない少年が、ぐいと其の指に顔を擦り付けた。
然して更に身体を丸める。
「……貴様はまるで猫のようだな」
何と無く戸惑った様子を漂わせながらも、傷のある少年は嬉しそうであった。
「そうですか?貴方は犬みたいですけどね……雷堂」
雷堂の手をとり、綺麗に摘まれた爪の一本一本に軽く歯を立てる。
「我が犬……まあ、貴様が猫ならそうだろうか」
指を自由にされながら、ふむと真剣に考え出す雷堂の様子を見てライドウはくすりと笑った。
「業斗殿に跪く姿なんて忠犬そのものじゃあないですか」
「貴様はまたそういう事を言う。だから我は貴様が厭いなのだ」
そうして意地悪を言う口に指を突っ込んでやる。
途端に尖った犬歯に嬉々として歯を立てられた。
「今日はあまり怒らないのですね」
意外そうに目を丸くした顔が面白かったので、雷堂は気を良くした。
「貴様は時々そんなだから我は厭いになりきれんのかもなあ」
瞼を優しく覆って、上から接吻けた。
たまにどうしようもなく、ライドウの事を愛しいと想う気持ちが溢れるときがある。
其れはきまってこんなふうにライドウが気紛れに甘えてくる時だという事を雷堂は知らない。
「何……、言っているんですか……」
不意打ちを食らって腹を立てたらしいライドウが学帽を掠め取って部屋の隅に投げた。
「こら、貴様」
代わりにライドウの学帽を奪って被る。
折角大学芋を買って来たのに分けてあげませんからね、と叫ぶ声がした。